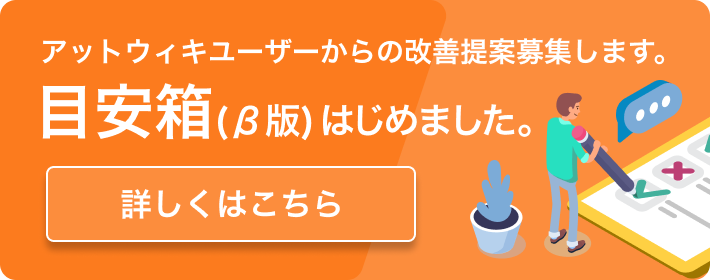「◎平和をつくるための本棚08Ⅰ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「◎平和をつくるための本棚08Ⅰ」(2009/06/07 (日) 11:27:19) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
#contents
最新の記事は [[◎平和をつくるための本棚]] に
- 初めてコメントします。 &br()こちらで紹介されている、土井敏邦さんの『沈黙を破る』がドキュメンタリー映画になりました。 &br()その名もズバリ『沈黙を破る』です。本作は5月2日(土)より東京・ポレポレ東中野にて公開が決定しています。 &br()よろしければ、ぜひご覧下さい。作品詳細はこちらhttp://www.cine.co.jp/chinmoku/ &br() -- にしあきこ (2009-03-28 09:59:48)
- ホテル行く前に外で2発イカせてもらいますた! http://ston.mlstarn.com/247384 -- てれれん (2009-06-02 12:23:37)
- セフしさまさまだなwマジ天国www &br() &br()http://sersai%2ecom/hosakimenma/28463602 -- 大日にょ来 (2009-06-05 23:57:28)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*苦難の昭和が示す教訓 [朝日]
[掲載]2008年8月17日
[評者]半藤一利(作家)
■夏の読書特集 新書を読もう!
戦争中、私たちはどんなに新聞に扇動され、集団催眠をかけられたことか。しかし敗戦の日、責任を痛感し白紙で発行した新聞はただ1紙。毎日新聞の西部本社版で、「昨日まで鬼畜米英を唱え、焦土決戦を叫びつづけた紙面を、同じ記者の手によって百八十度の大転換をするような器用な真似(まね)は良心が許さない」という理由によってである。
その、新聞が頬(ほお)かぶりしてきた責任問題を、タブーを破って検証したいい本が出た。朝日新聞「新聞と戦争」取材班の『新聞と戦争』(朝日新聞社)である。潰(つぶ)されるのを覚悟で、勇気をもって戦争反対を書け、そうすれば戦争終結後に朝日は堂々と復活する、といった石原莞爾の話が本文中にある。それに対応しての、いまの新聞人の勇気と覚悟が感得された。
昭和史の中心にあったのは、いうまでもなく昭和天皇である。最近刊の松本健一『畏るべき昭和天皇』(毎日新聞社)は過去の諸書なんかと違い、とにかく昭和史における昭和天皇の存在のいちばん核心のところを深く考察した野心的な論考である。二・二六事件のさいの天皇の畏(おそ)るべきところは、北一輝から軍隊を奪い返したところにある、といったそれこそ恐るべき記述にぶつかり、驚倒させられることしばしばであった。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808190101.html
*大量虐殺の社会史 [編著]松村高夫ら
[掲載]2008年02月24日
[評者]酒井啓子(東京外国語大学教授・中東現代政治)
■虐殺の隠蔽や相対化に対抗するには
歴史家が虐殺の事実を明らかにしようとするとき、二つの障害がある。加害者の国家による史実の隠蔽(いんぺい)と、記憶を重視し実証に懐疑的な歴史学による虐殺の相対化である――。
こう主張する『大量虐殺の社会史』が編まれた動機は、明確だ。近年のポストモダン的歴史学は、歴史的事実を究明不可能とする不可知論に陥ってしまい、国家による虐殺という史実を隠蔽するのに加担しているのではないか。改めて史実の実証分析に力点を戻し、記憶ではなく記録に基づいて虐殺を分析し、比較研究の俎上(そじょう)に載せ、生命の尊厳を守ることに寄与したい。こうした歴史家としての編者の意気込みが伝わってくる編著である。
そこでは、ユダヤ人へのホロコーストやポル・ポトの殺戮、ルワンダ内戦などがあげられているが、朝鮮戦争直後の米軍による韓国避難民攻撃や、クロアチアの対セルビア人虐殺など、知られざる事件にも光を当てる。
出版社:ミネルヴァ書房 価格:¥ 4,725
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200802260140.html
*壊れゆくアメリカ [著]ジェイン・ジェイコブズ
[掲載]2008年8月10日
[評者]柄谷行人(評論家)■集団的記憶喪失が文明を暗黒へと
本書は2006年に亡くなった著者の遺作となったエッセー集である。著者が90歳に近づいて活発に考え、かつ活動していたことを知って、私はあらためて感銘を受けた。本書には格別に新しい考えはない。著者が50年間いい続けてきたことと同じだといってよい。しかし、同じでないのは、50年前と現在である。
現在、多くの人々は昔の都市を覚えていない。たとえば、ロサンゼルスに、かつての東京と同様、路面電車が街中を走っていたといっても、誰も信じないだろう。「モータリゼーション」が都市や都市の生活を根こそぎ破壊したのに、もうそのことに気づくことさえできない。過去を覚えていないからだ。そのような集団的記憶喪失が、各所におこっている。
本書の原題は「暗黒時代が近づいている」という意味であるが、暗黒時代とは、ローマ帝国が滅んだあとのゲルマン社会で、ローマの文化がすぐに忘却されてしまったことを指している。そのような事態が現在おこりつつある、という著者の予感に、私は同意する。それをひきおこしているのは、いうまでもなく、グローバルな資本主義である。
出版社:日経BP社 価格:¥ 1,995
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120141.html
*暴走する資本主義 [著]ロバート・B・ライシュ
[掲載]2008年8月10日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)■消費者・投資家の権力を市民の手に
本書は、クリントン政権で労働長官を務めた政治経済学者である著者が、現在の資本主義を「超資本主義(スーパーキャピタリズム)」と規定した上で、その特質や対応のあり方を包括的に論じるものである。著者の議論の骨子は次のように要約される。(1)第2次大戦が終わった1945年から70年代半ばまで、アメリカの資本主義はある種の黄金時代を享受したが、それは「経済と政治の融合」と総括しうるもので、多くの政府規制や調整、労使交渉のシステム、企業ステーツマンと呼ばれる公的役割を担う経営者等々によって支えられていた。(2)70年代後半からすべてが一変し「超資本主義」へのシフトが始まった。その本質は「消費者と投資家が権力を獲得し、公共の利益を追求する市民が権力を失ってきた」という点に集約される。(3)超資本主義を準備したのは冷戦期の輸送・通信技術などの革新であり、それらがグローバル化、新しい生産様式、規制緩和といった事象と相まって、「安定的な寡占システム」としての民主的資本主義を終焉(しゅうえん)させた。(4)なされるべき対応は何か。鍵は「民主主義」であり、我々の中にある二面性(市民としての自己と、消費者・投資家としての自己)を自覚しつつ、前者をいかに回復していくかにかかっている。
以上が概略だが、一方で、現在の資本主義ないし経済のあり方についての先鋭な分析であり、またアメリカのもっとも「良心的」な部分を代表する書物ともいえる。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120163.html
*「百人斬り競争」と南京事件―史実の解明から歴史対話へ [著]笠原十九司
[掲載]2008年8月10日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)■メディア・国民の喝采で英雄視
「百人斬(ぎ)り競争」とは、南京攻略戦の途上で日本軍の将校2人が、どちらが先に中国兵100人を軍刀で斬り殺すかを競った事件をさしている。南京事件を否定する人たちは、これを報道した新聞記者の創作だったと主張し、2人の将校の遺族は、この事件を改めて紹介した本多勝一らを名誉棄損で訴えた。
06年12月、裁判は原告側の最高裁での敗訴で終わる。確定した判決は「百人斬り競争」について、新聞報道には誇張があったかも知れないが、決してでっち上げではなく、斬殺競争の事実が存在したことは否定できないと認定した。この裁判で被告側を支援して史実を検証したのが著者であり、本書はその裁判での成果をまとめたものだ。
本書によればこの2人の将校に限らず、日本軍将兵が1人で数十人の中国兵を軍刀で斬り殺したという話は、日中戦争期には数多く見られ、将兵の出身地の地方紙上で報道されていた。だがそれは実際には、敗残兵や捕虜など無抵抗の中国人を斬った場合が多いと推測されるという。
衝撃的なのは、その当時こうした斬殺を、将兵の家族を含む地域社会が称賛し、彼らを郷土の英雄扱いしていたことだ。事件を裏で支えていたのは、マスメディアも含む国民の喝采だったことを、本書は明らかにしたのだった。
出版社:大月書店 価格:¥ 2,730
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120115.html
*世界を不幸にするアメリカの戦争経済―イラク戦費3兆ドルの衝撃 [著]ジョセフ・E・スティグリッツ、リンダ・ビルムズ
[掲載]2008年7月20日
[評者]久保文明(東京大学教授・アメリカ政治)■「驚くほど高くついた」戦争のコスト
戦争はとてつもなく高くつく。これが本書のメッセージである。イラク戦争開始前、ブッシュ政権関係者は、戦争はすぐに終わり、イラクの石油を売却すれば戦費もごくわずかしかかからないと主張した。「ところが実際には、戦争は生命と財産の両面で、驚くほど高くつくことになった」。本書の概算では、アメリカに課される財政的・経済的コストの総額は約3兆ドルに達する。
戦争の費用に含まれるのは、直接の武器・人件費はいうまでもなく、退役軍人の障害補償や将来の医療費、負傷した退役軍人を介護するために離職を余儀なくされる家族の収入の喪失、石油価格の値上がりによるマクロ経済的損失などである。ちなみに、本書では、日本が被った経済的損失は1010億ドルから3070億ドルの間と推定される。
それだけではない。著者によれば、ブッシュ政権はさまざまな方法でコストを少なくみせようとしてきた。これは国民を欺く行為である。
著者がとくに強く読者に訴えたいことは、アメリカが3兆ドル負担する能力があるかどうかではなく(著者はそれは可能であると言う)、「機会費用」、すなわち「その三兆ドルがあれば何ができただろうか」という問題である。
思うに、経済的コストは、いかなる戦争においても開戦にあたって重要な判断要因である。ただし、戦費が高いからという理由で、開戦の決定は一切行われないということになるであろうか。
アメリカによるアフガニスタンに対する戦争は、その総コストが政権と国民に認識されていたとしても、また事件当時民主党のゴア政権であったとしても、着手されていた可能性が高いと思われる。
超党派の議会予算局はより控えめな推測をしており、石油価格上昇までコストに含める本書には批判も多い。
しかも、本書では9・11テロがアメリカと世界に与えた経済的コストについては触れていない。こちらにも触れた上で議論を進めた方がより公平ではないか。いろいろな意味で読者の独立した思索を促す書である。
◇
楡井浩一訳/Joseph E. Stiglitz 大学教授、Linda J. Bilmes 大学講師。
出版社:徳間書店 価格:¥ 1,785
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807220232.html
*新聞と戦争 [著]朝日新聞「新聞と戦争」取材班
[掲載]2008年7月27日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)■なぜ、薄れたのか「新聞人の自覚」
日本の15年戦争は、マスメディアの協力なしには遂行できなかった。しかしこれまでその戦争責任を追及した研究は、外部の学者や元記者によるものであった。その点で朝日新聞が、自社の戦争協力を検証した「新聞と戦争」シリーズは、画期的な仕事といえるように思う。高齢の新聞社OBを探し出して取材する手法は、新聞社ならではのものであった。07年4月から1年間夕刊に連載されたそれは、日本ジャーナリスト会議の大賞を受賞し、連載をまとめた本書は570ページを超える大著となった。
朝日新聞社が満州事変を契機に戦争支持へ社論を転換させ、戦意昂揚(こうよう)を煽(あお)る紙面作りをしたことは、従来から指摘されていた。その際、緒方竹虎など朝日新聞の首脳部の意図は、軍との協調関係を築きながら、他方で軍への批判や抵抗の芽も残しておこうとするものだったのかも知れない。しかし彼らには、どの地点で踏みとどまるべきか、どうしたら反撃に転じられるかということへの、見通しも勇気も欠けていたように見える。
新聞社の戦争協力は、ずるずると多方面に広がっていった。戦争のニュース映画の製作と各地での上映、女性の組織化と国策協力への動員、文学者とタイアップした前線報道や帰国講演会など、そのいずれもが新聞の購読者の拡大につながるものだった。
さらに進んで朝日新聞では、満蒙開拓青少年義勇軍の募集を後援し、戦争末期には少年兵の志願を勧める少国民総決起大会も開催している。そして新聞社が植民地や満州で、さらには南方占領地などで、新聞を発行し経営の手を広げるのにも、軍との良好な関係は大いに役立ったのである。
新聞人は、戦争協力を当然と考えるナショナリズムに囚(とら)われていた。しかし他方で多くの現場の記者は、戦争の実情を公表できないことに矛盾や違和感を感じていたらしい。公表できないのは、軍や内務省の検閲や圧迫が次第に厳しくなっていったためである。しかし同時に官製報道が一般化して特ダネ競争もなくなり、軍の言いなりに書くことに馴(な)れてしまったという実情もあった。
本書は戦時期の新聞社の問題を、国家や軍との距離感が薄らぐ中で、新聞人が次第に軍と一体化していくことに無自覚になった点に見出(みいだ)しているようだ。従軍記者はしばしばピストルで武装し、朝日の社機と航空部員は海軍に徴用された形で、海軍の便宜を図る見返りに、海軍からガソリンを貰(もら)って前線で写した写真を内地に空輸していた。
その軍との一体化の極端な表れは、戦争末期に朝日新聞の社員と社屋がそのまま軍需産業に使われた場合があったことである。新聞製版上で開発された技術が、軍用機の設計図の拡大複写に転用されたのである。技術開発に携わった東京本社の写真部長が中心になって、「護国第4476工場」と呼ばれた軍需工場が造られた。そこでは新聞人としての職業意識も希薄化していった。ジャーナリストがジャーナリストでなくなっていったことにこそ、その最大の悲劇があったともいえよう。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807290119.html
*不平等国家 中国 [著]園田茂人
[掲載]2008年7月27日
[評者]天児慧(早稲田大学教授・現代アジア論)
中国はこれからの国づくりのカギとして「和諧(わかい)(調和のある)社会」実現を掲げている。それは今日、格差・不平等の問題が極めて深刻であることを意味しているからに他ならない。
本書は、自らが行った多くの社会調査をフルに活用し分析しながら、鋭くかつ説得力のある独自の格差・不平等論を展開している。市場経済の導入が経済発展とともに、格差・不平等社会を生み出した。高学歴化がその不平等な収入を生み出す要因でありながらも、学歴社会に対する中国人の不公正感は弱く、能力主義的価値観へのシフトが強く見られると指摘する。
また都市への流入が激増する農民工(外来人口)問題も不平等・格差を象徴し、都市治安の悪化・不安定化を増大するとの通念がある。しかし実際には都市住民と外来人口の平均収入差はそれほど大きくなく、外来人口の都市生活満足度は高く、彼らが全体的に反政府的な行動に走ることは考えにくいと見る。
もう一つ興味深いのは中間層の分析である。概念自体は多義的だが、その増大が市民社会を形成し政治体制を民主化するとよく言われる。ところが調査では、メディアや地方政府への不信感は強いが中央政府への信頼感は極めて高く、また問題解決のためにデモなどに参加せず、「コネを使う」「お上の意見を聞く」傾向が強い。つまり中国の中間層は、「民主化=体制崩壊」の担い手ではなく、社会安定への指向性が強く保守的でさえあると見ている。
本書の問題提起と結論の関係も面白い。中国は市場経済を導入することで長く堅持してきた社会主義を自己否定した。その行方はどうなるか。これが問題提起である。そして「過去へ進化する社会主義」に向かっていると結論付ける。単なる過去への回帰ではない、進化だとの指摘に、えーっと読みなおしてしまう。しかし向かっているのはどうやら「伝統的な中華国家」である。社会主義は進化しているのか自己否定されたのか。「常識」的理解にチャレンジし、読者に知的刺激を与えてくれる好著である。
◇
そのだ・しげと 61年生まれ。早稲田大教授(中国社会論)。『日本企業アジアへ』。
不平等国家中国―自己否定した社会主義のゆくえ (中公新書 1950)
著者:園田 茂人
出版社:中央公論新社 価格:¥ 777
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807290102.html
*沈黙を破る―元イスラエル軍将兵が語る“占領” [著]土井敏邦
[掲載]2008年7月13日
[評者]南塚信吾(法政大学教授・国際関係史)
■占領地での不正の現実が明らかに
本書は、「占領地」において兵役についていた20歳代の若い元将兵たちが作ったグループ「沈黙を破る」の出した証言集にある発言と、著者のインタビューとからなる。
非武装のパレスチナ人を理由もなく射殺する、少女を撃ち殺す、道路は危険なので壁を破って家から家へと進撃するといった非道、しかも指揮官の明確な指令もなく行われる暴力、これが占領地での現実だという。しかし、そういう占領軍の不正は、将兵自身が認めたがらないし、将兵の親たちも自分の息子たちがそういうことをするとは信じたがらない。パレスチナ社会もそうである。
しかし、理由のない占領と占領地での不正にいたたまれなくなる将兵もいる。このままでは自分は人格的に破滅してしまうと。さらに、こういう不正を認めないイスラエル社会も不健全になっていくと。こういう危機感から、将兵が語り始めたのだ。このグループは2004年に写真展を開き、その後も元将兵への聞き取りを通して、メンバーを増やしている。
沈黙を破る―元イスラエル軍将兵が語る”占領”
著者:土井 敏邦
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807150135.html
*脱出 1940夏・パリ [著]ハンナ・ダイアモンド
[掲載]2008年6月29日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)
■過酷な逃避行を生き生きと描く
1940年6月14日、電撃作戦によりドイツ軍はパリに到達した。思いもかけぬ自国の敗戦を前にしてその直前の数週間に、フランス人560万人以上にベルギー人など180万人を加えた民間人が、フランスの南部をめがけて脱出する。それまでフランスではドイツ兵の残虐さが宣伝されており、恐怖が人々の逃亡を促した。
ドイツ軍の侵攻を阻止するために、橋や道路や鉄道などは破壊された。フランス軍も続々と撤退し、南に向かう道路は兵士と避難民で溢(あふ)れかえった。交通通信網が麻痺(まひ)し寸断された中で、通常の何百倍もの人々の移動が起こる時、そこには怖(おそ)ろしい弱肉強食の世界が出現する。幼児や病人や貧乏人は、過酷な逃避行の中で振り落とされることが多く、ドイツ軍の機銃掃射による犠牲者も含めて、一説によれば10万人の避難民が路上で息を引き取ったという。家族の生き別れも続出した。本書は避難民の日記や体験記を通して、その悲惨な状況を描いたものである。
この秩序の崩壊状況こそが、事実上の降伏である独仏休戦協定の締結をフランスの指導者や国民に受け入れさせた要因だったと、本書は説明する。やがて避難民は帰還したが、生き別れになった家族との再会が果たせない場合もあった。ドイツに捕虜として連行されたフランス軍兵士や、強制収容所送りとなったユダヤ人もあった。
敗戦に伴う逃避行は、フランス人には思い出したくもない記憶として残ったという。だが本書を読んで連想したのは、日本の敗戦後の外地からの引き揚げであり、今日の戦争で生まれた難民たちのことであった。フランスでの国内難民の経験は、普遍的な戦争体験に通じるものがある。
著者は記憶を再現することを通じて、避難民が見通しのつかない中で時々刻々に直面した状況を生き生きと描いてみせた。それには息詰まる ◇
佐藤正和訳、Fleeing Hitler-France 1940/Hanna Diamond 英バース大学フランス歴史学の上級講師。
脱出 1940夏・パリ
著者:ハンナ・ダイアモンド
出版社:朝日新聞出版 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010129.html
*アウシュビッツの沈黙 [編著]花元潔、米田周/ホロコースト [著]芝健介
[掲載]2008年6月29日
[評者]南塚信吾(法政大学教授・国際関係史)
■生命を愚弄した恥ずべき実例を直視
『アウシュビッツの沈黙』は、ホロコースト生還者の「記憶」である。ポーランドで行われた聞き取りを、証言者の言葉のままに記録した画期的なものとなっている。アウシュビッツ強制収容所での虐待・飢餓・大量虐殺についての生々しい「記憶」が語られる。とくに幼い子どもの「ゲルマン化」、ユダヤ人やロマの「人体実験」。そういう生還者もまだ差別されているのだ。語り手には、日本の被爆犠牲への共感もあるのか、率直な告白が胸を打つ。
ところで、このホロコーストの原因や展開などの全貌(ぜんぼう)は意外に知られていない。『ホロコースト』は、ナチスがユダヤ人大量殺戮(さつりく)を行うに至った思想、原因、経緯、そして実態と帰結を、最新の研究成果を踏まえて整理している。『アウシュビッツ』が犠牲者の「下から」の眼(め)だとすれば、これはあえて「上から」の視線で見ている。芝は、ホロコーストは狂った独裁者ヒトラーが命令し実行したという単純なものではないという。
過激な人種主義を基礎に「非アーリア」人追放を掲げたナチスは、政権につくやドイツ国内からのユダヤ人やロマの追放を始め、ポーランド侵攻の後は東欧への移送と「ゲットー化」を進めた。だが、ソ連侵攻以降、大量に抱え込んだ「非アーリア」人を処理できず、初めは現場主導の場当たり的な大量虐殺を行ったが、独ソ戦が膠着(こうちゃく)化すると、絶滅収容所での計画的な大量殺戮をトップにおいて決定した。このような「試行錯誤」の過程で600万人余の「非アーリア」人が殺戮されたのだ。
芝によれば、このホロコーストをめぐっては、長年「なぜ」それが起こったのかが論じられ、その責任主体はヒトラー個人か、ナチ体制の構造そのものかが争われてきている。だが、最近は「どのようにして」それが行われたのか、また一般市民の態度はどうだったのかという関心が高まっているという。
芝は、第2次世界大戦前後のヨーロッパ全体の構造的・文化的共通性の中でこれを考える必要があると言う。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010136.html
*アフリカ 苦悩する大陸 [著]ロバート・ゲスト
[掲載]2008年6月29日
[評者]松本仁一(ジャーナリスト)
■「政府が国民を食い物に」と腐敗を指摘
アフリカはなぜ貧しいのか。
「植民地として搾取を受けてきたため」というのが従来の模範解答だった。しかし著者は断定する。
「アフリカが貧しいのは、政府に問題があるからだ」
政府が無策なだけなら、国民は自力で生きていくことができる。しかしアフリカでは「あまりに多くの政府が国民を食い物にしている」とこの本はいうのである。
政府は、権力者が私腹を肥やすために存在する。官僚はわいろを要求する。警官は国民から金品を奪う――。その実例が次々に登場する。
ジンバブエ。役所の非能率で電話がなかなか引けない。そこである民間人が携帯電話会社を設立した。ところが政府は、民間の電話事業を禁ずる法律をつくる。裁判所がそれを違憲と判断すると、政府は事業を免許制に切り替え、免許を大統領の親族に与えてしまった。
カメルーン。著者はビール輸送のトラックに便乗する。ところが500キロ先の目的地まで4日かかってしまった。なんと47回、検問でとめられたのである。警官は金を渡すまで運転手の免許証を返してくれなかった。
アフリカの多くの政府は国民を支えるどころか、自立しようとする人々を妨害さえしているのである。
国連や世銀などの援助関係者が政府の腐敗を指摘したことはある。しかしそのたびにレイシスト(人種差別主義者)呼ばわりされ、口をつぐんだ。アフリカの政府批判はタブーだった。
しかし最近、タブーを破る発言が相次ぎはじめた。もう黙っているわけにはいかない、という気分。この本もそうした一つである。
著者は英誌「エコノミスト」の元アフリカ特派員。すべての国を調べているわけではないし、順調に国づくりが進むボツワナなどの例もある。だが、同じアフリカ特派員だった私の経験からも、この本の視点は正しいと思う。
アフリカ苦悩する大陸
著者:ロバート・ゲスト
出版社:東洋経済新報社 価格:¥ 2,310
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010124.html
*『「戦争」の心理学…』=グロスマン、クリステンセン著 [毎日]
小西聖子(たかこ)・評 『「戦争」の心理学--人間における戦闘のメカニズム』=D・グロスマン、L・W・クリステンセン著
(二見書房・2520円)
第二次世界大戦の最中にアメリカ軍で兵士の大規模調査が行われた。戦闘直後に行われた調査によると、ドイツまたは日本軍との接近戦に参加した兵士の発砲率は、どの場合でも15%から20%だったという。撃っても当たらないとか、逃げ出したということではなく、8割以上の兵士は、発砲さえしていなかった。敵と至近距離で向かい合ってさえ人は簡単には人を殺せない。そして、二〇世紀になってからの戦争ではつねに、ストレスで心身衰弱の状態になり戦闘できなくなる確率の方が、敵に撃たれて死ぬ確率よりずっと高かった。
唯一の例外はベトナム戦争であると著者は言う。この戦争では発砲したアメリカ兵士の割合は90%に達し、心身の衰弱を経験する確率と敵に殺される確率はほぼ等しくなった。ベトナム戦争では、アメリカ軍は、兵隊が人を殺すことができるように訓練を改良してから、兵士を送り出したからである。
簡単に言えば、それは繰り返しの射撃訓練である。ただし、丸い標的ではだめで、リアルな状況でリアルな人型標的を打つことが重要であった。「シミュレーターの迫真性」が効果をあげたのである。もっとよいのは、当たれば痛みは感じるペイント弾を使って、実戦に近い形で、人を撃つことを繰り返し訓練することだ。繰り返し慣れさせ、考えなくても判断し、対応できる、そういう行動主義的なトレーニングをおこなうと人に対する発砲率は高まることが示された。
ただし、ベトナム戦争では、兵士は発砲できるようになったが、その殺傷による心理的衝撃については何も教えてもらわなかったし、準備も訓練もなかった。彼らは反戦運動のさなかの母国に帰国し、孤立し、多数の帰還兵にPTSD(心的外傷後ストレス障害)が発生した。
ならば、次に考えるべきことは、どうやって落ち着いて殺傷し、恐怖にとらわれることなく生還し、街角の人間を撃ったりすることなく、家族とともに安定した生活を営むことができるのか、ということがポイントになる。
著者グロスマンは、アメリカの陸軍士官学校ウエストポイントの心理学、軍事学の教授で、「殺人学」の専門家、当然軍人である。本書は彼の前著『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫)と一続きになっている。前著はアメリカでは軍事学の教科書として広く採用されているそうだ。そして続編であるこの本は、軍人だけでなく、警察官や消防士など身体的な危機に身を晒(さら)す職業の人たちを読者に想定して書かれている。
この軍隊の中の研究の成果が非戦闘員のPTSDにも応用されるようになり、その後、性暴力被害者などを対象とした治療研究がすすんで科学的にも洗練されたという方が正しい。本家はアメリカ軍である。戦争をしている国が一番予算をつけたい研究は、どう考えてもそっちのほうだ。私はとても複雑な気持ちになった。
毎日新聞 2008年6月1日 東京朝刊
URL:http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20080601ddm015070005000c.html
*0604 『ロシア闇と魂の国家』 亀山郁夫・佐藤優 [読売]
ロシアを「国家」たらしめている「独裁」について、佐藤が現実政治からリアルな見方を示せば、一方の亀山はドストエフスキーの小説を例に、ロシア人の「魂」と「大地」のつながりを論じる。政治と文学をめぐる重厚な議論は、かの国の伝統をほうふつとさせる。
極端から極端へ振れる国民性を理解するカギを、ロシアの歴史に深く根ざした終末思想と宗教的熱狂の中に見て取るなど、ロシアの精神性に深く切り込んだ対話は興味深い。
(2008年6月4日 読売新聞)
出版社:文藝春秋
発行:2008年4月
ISBN:9784166606238
価格:¥788 (本体¥750+税)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/book/column/press/20080603bk0c.htm
*0504 クリエイティブ資本論 新たな経済階級の台頭 [著]リチャード・フロリダ [朝日]
[掲載]2008年05月04日
[評者]橋爪紳也(建築史家、大阪府立大学教授)
■創造力を持つ「階級」が都市を動かす
「クリエイティブ・クラス」と呼ぶべき階層が世界規模で台頭していることを指摘、知識や創造性を究極の資源とする経済と社会の仕組みを新たに構築する必然性を説く。02年に米国でベストセラーとなった都市経済学の話題書がようやく邦訳された。
科学者、技術者、芸術家、音楽家、建築家、作家、デザイナーといった職能、加えてビジネス・教育・医療・法律など専門家が急増している事実が、本書の前提になる。たとえば米国では、高度な知識や創造力を必要とする職能の従事者は、20世紀初頭には労働力の1割に過ぎなかった。しかし21世紀には、全体の3分の1を占めるほどに増加する。
彼らは脱工業化社会への転換期にあって「勝ち組」となり、経済や政治の中枢で活躍している。ただ他人には無関心で、自己中心的な人が少なくないという批判がある。また何よりも自分たちをまとまった集団とは考えてはいない。彼らが社会問題の責務を積極的に担い、唯一、「21世紀社会の指導者」になると確信する著者は、この層を「クリエイティブ・クラス」と命名、「階級」としての覚醒(かくせい)をうながす。
知識や創造性が産業を生むという議論は早くからある。近年も伝統的な職人の技やアートの力で、欧州の歴史都市が再生を遂げた先例が「創造都市」の概念とともに日本に紹介された。地域に潜む文化的な資産を再評価、内発的に活力の向上をはかる方法論は横浜や金沢でも応用された。
しかし本書は、欧州の実践とは一線を画する。とりわけクリエイティブ・クラスのライフスタイルに着目している点が面白い。彼らは自分の能力が生きる職場、より良い生活環境を求めて、転居することをいとわない。結果として彼らが魅力を感じる都市と、そうではない都市とのあいだで経済格差が拡大すると著者は仮説を示す。
この点を実証するべく著者は、技術・才能・寛容性という三つの指標から、都市や国家の創造力のランキングを試みることの必要性を説く。文化の多様性を認めあい、クリエイティビティに対して開かれた地域に、経済発展の可能性があるとみる理屈だ。原著が出版された際、ゲイ・カルチャーを容認するかどうかを指標として用いた点が話題になったが、必ずしも立論の本質ではない。
創造力のある優秀な人材は、住みやすさと活躍の場を求めて居住地を移し、時にはやすやすと国境を越える。本書で提示された議論は、フロリダの著作『クリエイティブ・クラスの世紀』でさらに展開されている。併読することをすすめたい。
もちろんわが国でもクリエイティブ・クラスの台頭があった。しかしその種の現象を「IT長者」「ヒルズ族」などと名づけて、きわめてローカルな世相風俗に矮小(わいしょう)化した感性はいかにも日本的だ。東京を始め日本の各都市も、国際的な都市間競争にあって、クリエイティブ・クラスを誘引する都市基盤の拡充に力を入れる発想が、これまで以上に必要だろう。
クリエイティブ資本論―新たな経済階級の台頭
著者:リチャード・フロリダ
出版社:ダイヤモンド社 価格:¥ 2,940
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805060068.html
*0504 創氏改名 日本の朝鮮支配の中で [著]水野直樹 [朝日]
[掲載]2008年05月04日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)
■同化政策に差異を残したチグハグ
誰でも自分の名前にはこだわりがある。ところが行政当局から突然、半年以内に新しい名前を届け出ろ、今後それを本名にするといわれても、当人は納得しにくいし、知り合いが誰さんなのかも分からなくなり、大混乱に陥るだろう。しかし創氏改名は、それを強行する政策だった。
名前の付け方は、それぞれの国と民族の家族制度によって決められるものだ。韓国・朝鮮人の場合は、夫の姓と妻の姓が違っている。妻は結婚しても、出身の実家の姓を変えないからである。
こうした習慣の朝鮮人に、日本人と同じように夫婦に共通する家の称号である氏を新たに作らせ、それを本名にする政策が「創氏」であった。それは朝鮮の家族制度の力を弱め、日本の「イエ」制度を朝鮮に導入するものだった。ついでに下の名前も、日本人風に変えるのが「改名」である。
本書は、創氏改名の矛盾に満ちた実態を叙述したものである。そこでは創氏は義務の届け出制で、朝鮮総督府をあげて督励し強要されたが、改名は当局の許可制で途中から奨励されなくなった。
そのため多くの朝鮮人は、創氏の届け出はしたが改名はせず、日本人風の氏と朝鮮人風の名を持つ、日本人に似ていながら日本人との違いが目立つ名前になってしまった。朝鮮人の姓に由来する、日本人には見かけない氏も創(つく)られた。それは日本への同化政策でありながら、完全な同化はさせないで、日本人との差異を残すものだった。日本人の中には朝鮮人への優越意識から、朝鮮人を日本人と同じ氏名とすることに反発する動きがあり、これが実施過程で影響したようだ。
著者は創氏改名が、朝鮮社会の家族制度を総督府が力づくで変えられると思い込んだ地点に生まれたと指摘している。でもそれは朝鮮人の反感や面従腹背の態度とともに、一部の日本人の反発も呼んだのである。強権的でありながら、どこか首尾一貫しないチグハグな創氏改名の実情を明らかにすることで、単純に同化政策とばかりはいえない、日本の支配の論理の特徴を考えさせる労作だ。
創氏改名―日本の朝鮮支配の中で (岩波新書 新赤版 1118)
著者:水野 直樹
出版社:岩波書店 価格:¥ 819
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805060055.html
*憲法9条の思想水脈 [著]山室信一 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]四ノ原恒憲(編集委員)
■「英知の結晶」成り立ち追う
参院選での自民党大敗北のひそかな原因の一つが、憲法改正に性急な首相への不安では、と思えてならない。そんな改正論議の中心である憲法9条を支える平和思想の成り立ちを、丁寧に、丁寧に追っている。
戦争が古来、大きな災禍であった以上、洋の東西を問わず、不戦への道を説く思想は、長い歴史を持つ。一挙に国際政治の荒波に投げ出された明治以降の日本にも、東西の不戦思想の影響を受けた中江兆民ら多くの論者が現れる。特に、日清・日露の経験は、その願いを切実なものにした。
ただ、国内外を問わず、現実主義者から「夢想」と遠ざけられたのも確かだ。でも、その「夢想」が無駄であったともいえない。国際連盟、パリ不戦条約、そして国際連合とその夢の一部は形を変え実現してきた。9条の精神は、日本人を含む長い人類の英知の結晶であり、決して「押しつけ」うんぬんで片づけられるほどやわなものではない。
憲法草案に深くかかわった幣原喜重郎・元首相は、述べる。「戦争放棄は正義に基づく正しい道であって日本は今日この大旗を掲げて国際社会の原野を単独で進んで行くのである」。こんな言葉がまぶしすぎる時代は、少し悲しい。
憲法9条の思想水脈
著者:山室 信一
出版社:朝日新聞社出版局 価格:¥ 1,365
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070310.html
*戦争の記憶 忘れたことさえ忘れるまえに(テーマ書評) [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]大上朝美
8月。太平洋戦争が終わって、間もなく62回目の記念日が来る。
「忘れたことさえ忘れてしまうまえに、薄れゆく記憶を取り戻すことをはじめたい」という山口誠著『グアムと日本人』は、日本人でにぎわう「楽園」の成り立ちの歴史を掘り起こす。真珠湾攻撃の直後に日本軍が占領し、「大宮島」と改称したことも日本ではあまり知られないいま、日米激戦の地・タモン湾には日本軍のトーチカが残り、挙式用の「日本人の教会」が立つ。「どちらも眺めが良いポイントを好む」という現地の人の言葉は痛烈だ。
グアムで米軍再上陸の激しい戦闘が行われていたころ、『野火』『俘虜(ふりょ)記』などを後に書く作家・大岡昇平はフィリピン・ミンドロ島に送り込まれた。大岡が70年夏に戦争体験を語り下ろした『戦争』は、小説の張りつめた緊迫感とは異なる趣で、淡々と、ざっくばらんな記述だが、詳細に繰り出す記憶のさまに引き込まれる。
44年夏に陥落したサイパン、グアムから飛び立つB29は、国内に爆弾・焼夷(しょうい)弾の雨を降らせた。『手塚治虫「戦争漫画」傑作選』は、空襲の恐怖や銃後の社会の息苦しさを生々しく核に持つ作品群だ。68年から79年にかけて発表された7編を収める。
乾淑子編著『図説 着物柄にみる戦争』には意表を突かれる。著者自身も2000年冬、インターネットオークションで、日中戦争を背景にした柄の乳児用の着物を初めて見て驚いたと書く。以来、著者が収集した着物を中心に紹介される戦争柄には「兵器」あり「上陸作戦」あり「愛国少年団」あり……。戦後の物不足の時でも着るのははばかられ、しまい込まれて永らえて、いまでは「面白柄」の一つとして人気という。確かに心引かれる面白さなのは、どうしよう。
図説着物柄にみる戦争
出版社:インパクト出版会 価格:¥ 2,310
グアムと日本人―戦争を埋立てた楽園 (岩波新書 新赤版 1083)
著者:山口 誠
出版社:岩波書店 価格:¥ 777
野火 (新潮文庫)
著者:大岡 昇平
出版社:新潮社 価格:¥ 340
俘虜記 (新潮文庫)
著者:大岡 昇平
出版社:新潮社 価格:¥ 660
戦争 (岩波現代文庫 社会 155)
著者:大岡 昇平
出版社:岩波書店 価格:¥ 1,050
手塚治虫「戦争漫画」傑作選 (祥伝社新書 81)
著者:手塚 治虫
出版社:祥伝社 価格:¥ 788
URL:http://book.asahi.com/hondana/TKY200708070340.html
*大地の慟哭―中国民工調査 [著]秦尭禹 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]高原明生(東京大学教授・東アジア政治)
■農村から出稼ぎ、想像を超す苦境に
来年のオリンピックを控えた北京ならずとも、現在、中国の大都市の建設ラッシュはすさまじい。急速に進む中国の都市化、そして「世界の工場」とまで言われるようになった工業化を支えているのは、「民工」と呼ばれる農村からの出稼ぎ労働者だ。
いまや2億人はいると言われる民工は、いわゆる3Kの仕事を受け持ち、仕送りによって農村経済にも大きく貢献する。例えば03年には、それによって四川省の農民の純収入は50%増えたという。
本書は、中国で05年1月に出版され、多くの人に読まれた『中国民工調査』の邦訳である。著者は香港のエコノミスト。中国のいくつかの都市での実地調査と豊富な文献調査を組み合わせ、民工の生活の実態に迫り、それを多面的に描き出した。
一部の民工の実態の厳しさは想像以上だ。給料の遅配欠配は驚くに値しない。劣悪な労働環境による労働災害の頻発と社会保障の欠如、「民工米」と呼ばれる、食用に適さない古い米などを使った粗末な食事、性の抑圧と精神生活の不毛、民工の子供の就学難と学校でのいじめ、そして農村の留守家庭に残された子供への虐待やストレス。民工と農村は都市主導の変革の波に呑(の)み込まれ、血縁を中心とした農村の姻戚(いんせき)文化と社会システムは破壊されたと著者はいう。
中国の指導者は決して無為無策でいるわけではない。差別をなくし、民工に正式労働者と同じ待遇を与えるよう指示を次々と出している。また、女子労働者や熟練工の不足が広東などで深刻化し、賃上げ圧力となっている。
民工の苦難は高度成長に伴う過渡的な問題なのかもしれない。成功している民工だって少なくないはずだ。だが広い中国の場合、過渡期は相当長くならざるをえまい。制度上は差別を廃止しても、豊かな沿海大都市を除き、実態として民工全員に社会福祉を提供することは当面不可能である。差別意識の解消も簡単ではない。表はぴかぴかの摩天楼だが、その裏には長く、濃い影があることを本書は教えてくれる。
◇
田中忠仁ほか訳/チン・ヤオユイ 経済学博士、香港の管理顧問会社マネジャー。
大地の慟哭(どうこく)
著者:秦 尭禹
出版社:PHP研究所 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070290.html
*[[◎平和をつくるための本棚06]] より続く
#contents
最新の記事は [[◎平和をつくるための本棚]] に
- 初めてコメントします。 &br()こちらで紹介されている、土井敏邦さんの『沈黙を破る』がドキュメンタリー映画になりました。 &br()その名もズバリ『沈黙を破る』です。本作は5月2日(土)より東京・ポレポレ東中野にて公開が決定しています。 &br()よろしければ、ぜひご覧下さい。作品詳細はこちらhttp://www.cine.co.jp/chinmoku/ &br() -- にしあきこ (2009-03-28 09:59:48)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*苦難の昭和が示す教訓 [朝日]
[掲載]2008年8月17日
[評者]半藤一利(作家)
■夏の読書特集 新書を読もう!
戦争中、私たちはどんなに新聞に扇動され、集団催眠をかけられたことか。しかし敗戦の日、責任を痛感し白紙で発行した新聞はただ1紙。毎日新聞の西部本社版で、「昨日まで鬼畜米英を唱え、焦土決戦を叫びつづけた紙面を、同じ記者の手によって百八十度の大転換をするような器用な真似(まね)は良心が許さない」という理由によってである。
その、新聞が頬(ほお)かぶりしてきた責任問題を、タブーを破って検証したいい本が出た。朝日新聞「新聞と戦争」取材班の『新聞と戦争』(朝日新聞社)である。潰(つぶ)されるのを覚悟で、勇気をもって戦争反対を書け、そうすれば戦争終結後に朝日は堂々と復活する、といった石原莞爾の話が本文中にある。それに対応しての、いまの新聞人の勇気と覚悟が感得された。
昭和史の中心にあったのは、いうまでもなく昭和天皇である。最近刊の松本健一『畏るべき昭和天皇』(毎日新聞社)は過去の諸書なんかと違い、とにかく昭和史における昭和天皇の存在のいちばん核心のところを深く考察した野心的な論考である。二・二六事件のさいの天皇の畏(おそ)るべきところは、北一輝から軍隊を奪い返したところにある、といったそれこそ恐るべき記述にぶつかり、驚倒させられることしばしばであった。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808190101.html
*大量虐殺の社会史 [編著]松村高夫ら
[掲載]2008年02月24日
[評者]酒井啓子(東京外国語大学教授・中東現代政治)
■虐殺の隠蔽や相対化に対抗するには
歴史家が虐殺の事実を明らかにしようとするとき、二つの障害がある。加害者の国家による史実の隠蔽(いんぺい)と、記憶を重視し実証に懐疑的な歴史学による虐殺の相対化である――。
こう主張する『大量虐殺の社会史』が編まれた動機は、明確だ。近年のポストモダン的歴史学は、歴史的事実を究明不可能とする不可知論に陥ってしまい、国家による虐殺という史実を隠蔽するのに加担しているのではないか。改めて史実の実証分析に力点を戻し、記憶ではなく記録に基づいて虐殺を分析し、比較研究の俎上(そじょう)に載せ、生命の尊厳を守ることに寄与したい。こうした歴史家としての編者の意気込みが伝わってくる編著である。
そこでは、ユダヤ人へのホロコーストやポル・ポトの殺戮、ルワンダ内戦などがあげられているが、朝鮮戦争直後の米軍による韓国避難民攻撃や、クロアチアの対セルビア人虐殺など、知られざる事件にも光を当てる。
出版社:ミネルヴァ書房 価格:¥ 4,725
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200802260140.html
*壊れゆくアメリカ [著]ジェイン・ジェイコブズ
[掲載]2008年8月10日
[評者]柄谷行人(評論家)■集団的記憶喪失が文明を暗黒へと
本書は2006年に亡くなった著者の遺作となったエッセー集である。著者が90歳に近づいて活発に考え、かつ活動していたことを知って、私はあらためて感銘を受けた。本書には格別に新しい考えはない。著者が50年間いい続けてきたことと同じだといってよい。しかし、同じでないのは、50年前と現在である。
現在、多くの人々は昔の都市を覚えていない。たとえば、ロサンゼルスに、かつての東京と同様、路面電車が街中を走っていたといっても、誰も信じないだろう。「モータリゼーション」が都市や都市の生活を根こそぎ破壊したのに、もうそのことに気づくことさえできない。過去を覚えていないからだ。そのような集団的記憶喪失が、各所におこっている。
本書の原題は「暗黒時代が近づいている」という意味であるが、暗黒時代とは、ローマ帝国が滅んだあとのゲルマン社会で、ローマの文化がすぐに忘却されてしまったことを指している。そのような事態が現在おこりつつある、という著者の予感に、私は同意する。それをひきおこしているのは、いうまでもなく、グローバルな資本主義である。
出版社:日経BP社 価格:¥ 1,995
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120141.html
*暴走する資本主義 [著]ロバート・B・ライシュ
[掲載]2008年8月10日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)■消費者・投資家の権力を市民の手に
本書は、クリントン政権で労働長官を務めた政治経済学者である著者が、現在の資本主義を「超資本主義(スーパーキャピタリズム)」と規定した上で、その特質や対応のあり方を包括的に論じるものである。著者の議論の骨子は次のように要約される。(1)第2次大戦が終わった1945年から70年代半ばまで、アメリカの資本主義はある種の黄金時代を享受したが、それは「経済と政治の融合」と総括しうるもので、多くの政府規制や調整、労使交渉のシステム、企業ステーツマンと呼ばれる公的役割を担う経営者等々によって支えられていた。(2)70年代後半からすべてが一変し「超資本主義」へのシフトが始まった。その本質は「消費者と投資家が権力を獲得し、公共の利益を追求する市民が権力を失ってきた」という点に集約される。(3)超資本主義を準備したのは冷戦期の輸送・通信技術などの革新であり、それらがグローバル化、新しい生産様式、規制緩和といった事象と相まって、「安定的な寡占システム」としての民主的資本主義を終焉(しゅうえん)させた。(4)なされるべき対応は何か。鍵は「民主主義」であり、我々の中にある二面性(市民としての自己と、消費者・投資家としての自己)を自覚しつつ、前者をいかに回復していくかにかかっている。
以上が概略だが、一方で、現在の資本主義ないし経済のあり方についての先鋭な分析であり、またアメリカのもっとも「良心的」な部分を代表する書物ともいえる。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120163.html
*「百人斬り競争」と南京事件―史実の解明から歴史対話へ [著]笠原十九司
[掲載]2008年8月10日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)■メディア・国民の喝采で英雄視
「百人斬(ぎ)り競争」とは、南京攻略戦の途上で日本軍の将校2人が、どちらが先に中国兵100人を軍刀で斬り殺すかを競った事件をさしている。南京事件を否定する人たちは、これを報道した新聞記者の創作だったと主張し、2人の将校の遺族は、この事件を改めて紹介した本多勝一らを名誉棄損で訴えた。
06年12月、裁判は原告側の最高裁での敗訴で終わる。確定した判決は「百人斬り競争」について、新聞報道には誇張があったかも知れないが、決してでっち上げではなく、斬殺競争の事実が存在したことは否定できないと認定した。この裁判で被告側を支援して史実を検証したのが著者であり、本書はその裁判での成果をまとめたものだ。
本書によればこの2人の将校に限らず、日本軍将兵が1人で数十人の中国兵を軍刀で斬り殺したという話は、日中戦争期には数多く見られ、将兵の出身地の地方紙上で報道されていた。だがそれは実際には、敗残兵や捕虜など無抵抗の中国人を斬った場合が多いと推測されるという。
衝撃的なのは、その当時こうした斬殺を、将兵の家族を含む地域社会が称賛し、彼らを郷土の英雄扱いしていたことだ。事件を裏で支えていたのは、マスメディアも含む国民の喝采だったことを、本書は明らかにしたのだった。
出版社:大月書店 価格:¥ 2,730
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200808120115.html
*世界を不幸にするアメリカの戦争経済―イラク戦費3兆ドルの衝撃 [著]ジョセフ・E・スティグリッツ、リンダ・ビルムズ
[掲載]2008年7月20日
[評者]久保文明(東京大学教授・アメリカ政治)■「驚くほど高くついた」戦争のコスト
戦争はとてつもなく高くつく。これが本書のメッセージである。イラク戦争開始前、ブッシュ政権関係者は、戦争はすぐに終わり、イラクの石油を売却すれば戦費もごくわずかしかかからないと主張した。「ところが実際には、戦争は生命と財産の両面で、驚くほど高くつくことになった」。本書の概算では、アメリカに課される財政的・経済的コストの総額は約3兆ドルに達する。
戦争の費用に含まれるのは、直接の武器・人件費はいうまでもなく、退役軍人の障害補償や将来の医療費、負傷した退役軍人を介護するために離職を余儀なくされる家族の収入の喪失、石油価格の値上がりによるマクロ経済的損失などである。ちなみに、本書では、日本が被った経済的損失は1010億ドルから3070億ドルの間と推定される。
それだけではない。著者によれば、ブッシュ政権はさまざまな方法でコストを少なくみせようとしてきた。これは国民を欺く行為である。
著者がとくに強く読者に訴えたいことは、アメリカが3兆ドル負担する能力があるかどうかではなく(著者はそれは可能であると言う)、「機会費用」、すなわち「その三兆ドルがあれば何ができただろうか」という問題である。
思うに、経済的コストは、いかなる戦争においても開戦にあたって重要な判断要因である。ただし、戦費が高いからという理由で、開戦の決定は一切行われないということになるであろうか。
アメリカによるアフガニスタンに対する戦争は、その総コストが政権と国民に認識されていたとしても、また事件当時民主党のゴア政権であったとしても、着手されていた可能性が高いと思われる。
超党派の議会予算局はより控えめな推測をしており、石油価格上昇までコストに含める本書には批判も多い。
しかも、本書では9・11テロがアメリカと世界に与えた経済的コストについては触れていない。こちらにも触れた上で議論を進めた方がより公平ではないか。いろいろな意味で読者の独立した思索を促す書である。
◇
楡井浩一訳/Joseph E. Stiglitz 大学教授、Linda J. Bilmes 大学講師。
出版社:徳間書店 価格:¥ 1,785
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807220232.html
*新聞と戦争 [著]朝日新聞「新聞と戦争」取材班
[掲載]2008年7月27日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)■なぜ、薄れたのか「新聞人の自覚」
日本の15年戦争は、マスメディアの協力なしには遂行できなかった。しかしこれまでその戦争責任を追及した研究は、外部の学者や元記者によるものであった。その点で朝日新聞が、自社の戦争協力を検証した「新聞と戦争」シリーズは、画期的な仕事といえるように思う。高齢の新聞社OBを探し出して取材する手法は、新聞社ならではのものであった。07年4月から1年間夕刊に連載されたそれは、日本ジャーナリスト会議の大賞を受賞し、連載をまとめた本書は570ページを超える大著となった。
朝日新聞社が満州事変を契機に戦争支持へ社論を転換させ、戦意昂揚(こうよう)を煽(あお)る紙面作りをしたことは、従来から指摘されていた。その際、緒方竹虎など朝日新聞の首脳部の意図は、軍との協調関係を築きながら、他方で軍への批判や抵抗の芽も残しておこうとするものだったのかも知れない。しかし彼らには、どの地点で踏みとどまるべきか、どうしたら反撃に転じられるかということへの、見通しも勇気も欠けていたように見える。
新聞社の戦争協力は、ずるずると多方面に広がっていった。戦争のニュース映画の製作と各地での上映、女性の組織化と国策協力への動員、文学者とタイアップした前線報道や帰国講演会など、そのいずれもが新聞の購読者の拡大につながるものだった。
さらに進んで朝日新聞では、満蒙開拓青少年義勇軍の募集を後援し、戦争末期には少年兵の志願を勧める少国民総決起大会も開催している。そして新聞社が植民地や満州で、さらには南方占領地などで、新聞を発行し経営の手を広げるのにも、軍との良好な関係は大いに役立ったのである。
新聞人は、戦争協力を当然と考えるナショナリズムに囚(とら)われていた。しかし他方で多くの現場の記者は、戦争の実情を公表できないことに矛盾や違和感を感じていたらしい。公表できないのは、軍や内務省の検閲や圧迫が次第に厳しくなっていったためである。しかし同時に官製報道が一般化して特ダネ競争もなくなり、軍の言いなりに書くことに馴(な)れてしまったという実情もあった。
本書は戦時期の新聞社の問題を、国家や軍との距離感が薄らぐ中で、新聞人が次第に軍と一体化していくことに無自覚になった点に見出(みいだ)しているようだ。従軍記者はしばしばピストルで武装し、朝日の社機と航空部員は海軍に徴用された形で、海軍の便宜を図る見返りに、海軍からガソリンを貰(もら)って前線で写した写真を内地に空輸していた。
その軍との一体化の極端な表れは、戦争末期に朝日新聞の社員と社屋がそのまま軍需産業に使われた場合があったことである。新聞製版上で開発された技術が、軍用機の設計図の拡大複写に転用されたのである。技術開発に携わった東京本社の写真部長が中心になって、「護国第4476工場」と呼ばれた軍需工場が造られた。そこでは新聞人としての職業意識も希薄化していった。ジャーナリストがジャーナリストでなくなっていったことにこそ、その最大の悲劇があったともいえよう。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807290119.html
*不平等国家 中国 [著]園田茂人
[掲載]2008年7月27日
[評者]天児慧(早稲田大学教授・現代アジア論)
中国はこれからの国づくりのカギとして「和諧(わかい)(調和のある)社会」実現を掲げている。それは今日、格差・不平等の問題が極めて深刻であることを意味しているからに他ならない。
本書は、自らが行った多くの社会調査をフルに活用し分析しながら、鋭くかつ説得力のある独自の格差・不平等論を展開している。市場経済の導入が経済発展とともに、格差・不平等社会を生み出した。高学歴化がその不平等な収入を生み出す要因でありながらも、学歴社会に対する中国人の不公正感は弱く、能力主義的価値観へのシフトが強く見られると指摘する。
また都市への流入が激増する農民工(外来人口)問題も不平等・格差を象徴し、都市治安の悪化・不安定化を増大するとの通念がある。しかし実際には都市住民と外来人口の平均収入差はそれほど大きくなく、外来人口の都市生活満足度は高く、彼らが全体的に反政府的な行動に走ることは考えにくいと見る。
もう一つ興味深いのは中間層の分析である。概念自体は多義的だが、その増大が市民社会を形成し政治体制を民主化するとよく言われる。ところが調査では、メディアや地方政府への不信感は強いが中央政府への信頼感は極めて高く、また問題解決のためにデモなどに参加せず、「コネを使う」「お上の意見を聞く」傾向が強い。つまり中国の中間層は、「民主化=体制崩壊」の担い手ではなく、社会安定への指向性が強く保守的でさえあると見ている。
本書の問題提起と結論の関係も面白い。中国は市場経済を導入することで長く堅持してきた社会主義を自己否定した。その行方はどうなるか。これが問題提起である。そして「過去へ進化する社会主義」に向かっていると結論付ける。単なる過去への回帰ではない、進化だとの指摘に、えーっと読みなおしてしまう。しかし向かっているのはどうやら「伝統的な中華国家」である。社会主義は進化しているのか自己否定されたのか。「常識」的理解にチャレンジし、読者に知的刺激を与えてくれる好著である。
◇
そのだ・しげと 61年生まれ。早稲田大教授(中国社会論)。『日本企業アジアへ』。
不平等国家中国―自己否定した社会主義のゆくえ (中公新書 1950)
著者:園田 茂人
出版社:中央公論新社 価格:¥ 777
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807290102.html
*沈黙を破る―元イスラエル軍将兵が語る“占領” [著]土井敏邦
[掲載]2008年7月13日
[評者]南塚信吾(法政大学教授・国際関係史)
■占領地での不正の現実が明らかに
本書は、「占領地」において兵役についていた20歳代の若い元将兵たちが作ったグループ「沈黙を破る」の出した証言集にある発言と、著者のインタビューとからなる。
非武装のパレスチナ人を理由もなく射殺する、少女を撃ち殺す、道路は危険なので壁を破って家から家へと進撃するといった非道、しかも指揮官の明確な指令もなく行われる暴力、これが占領地での現実だという。しかし、そういう占領軍の不正は、将兵自身が認めたがらないし、将兵の親たちも自分の息子たちがそういうことをするとは信じたがらない。パレスチナ社会もそうである。
しかし、理由のない占領と占領地での不正にいたたまれなくなる将兵もいる。このままでは自分は人格的に破滅してしまうと。さらに、こういう不正を認めないイスラエル社会も不健全になっていくと。こういう危機感から、将兵が語り始めたのだ。このグループは2004年に写真展を開き、その後も元将兵への聞き取りを通して、メンバーを増やしている。
沈黙を破る―元イスラエル軍将兵が語る”占領”
著者:土井 敏邦
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807150135.html
*脱出 1940夏・パリ [著]ハンナ・ダイアモンド
[掲載]2008年6月29日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)
■過酷な逃避行を生き生きと描く
1940年6月14日、電撃作戦によりドイツ軍はパリに到達した。思いもかけぬ自国の敗戦を前にしてその直前の数週間に、フランス人560万人以上にベルギー人など180万人を加えた民間人が、フランスの南部をめがけて脱出する。それまでフランスではドイツ兵の残虐さが宣伝されており、恐怖が人々の逃亡を促した。
ドイツ軍の侵攻を阻止するために、橋や道路や鉄道などは破壊された。フランス軍も続々と撤退し、南に向かう道路は兵士と避難民で溢(あふ)れかえった。交通通信網が麻痺(まひ)し寸断された中で、通常の何百倍もの人々の移動が起こる時、そこには怖(おそ)ろしい弱肉強食の世界が出現する。幼児や病人や貧乏人は、過酷な逃避行の中で振り落とされることが多く、ドイツ軍の機銃掃射による犠牲者も含めて、一説によれば10万人の避難民が路上で息を引き取ったという。家族の生き別れも続出した。本書は避難民の日記や体験記を通して、その悲惨な状況を描いたものである。
この秩序の崩壊状況こそが、事実上の降伏である独仏休戦協定の締結をフランスの指導者や国民に受け入れさせた要因だったと、本書は説明する。やがて避難民は帰還したが、生き別れになった家族との再会が果たせない場合もあった。ドイツに捕虜として連行されたフランス軍兵士や、強制収容所送りとなったユダヤ人もあった。
敗戦に伴う逃避行は、フランス人には思い出したくもない記憶として残ったという。だが本書を読んで連想したのは、日本の敗戦後の外地からの引き揚げであり、今日の戦争で生まれた難民たちのことであった。フランスでの国内難民の経験は、普遍的な戦争体験に通じるものがある。
著者は記憶を再現することを通じて、避難民が見通しのつかない中で時々刻々に直面した状況を生き生きと描いてみせた。それには息詰まる ◇
佐藤正和訳、Fleeing Hitler-France 1940/Hanna Diamond 英バース大学フランス歴史学の上級講師。
脱出 1940夏・パリ
著者:ハンナ・ダイアモンド
出版社:朝日新聞出版 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010129.html
*アウシュビッツの沈黙 [編著]花元潔、米田周/ホロコースト [著]芝健介
[掲載]2008年6月29日
[評者]南塚信吾(法政大学教授・国際関係史)
■生命を愚弄した恥ずべき実例を直視
『アウシュビッツの沈黙』は、ホロコースト生還者の「記憶」である。ポーランドで行われた聞き取りを、証言者の言葉のままに記録した画期的なものとなっている。アウシュビッツ強制収容所での虐待・飢餓・大量虐殺についての生々しい「記憶」が語られる。とくに幼い子どもの「ゲルマン化」、ユダヤ人やロマの「人体実験」。そういう生還者もまだ差別されているのだ。語り手には、日本の被爆犠牲への共感もあるのか、率直な告白が胸を打つ。
ところで、このホロコーストの原因や展開などの全貌(ぜんぼう)は意外に知られていない。『ホロコースト』は、ナチスがユダヤ人大量殺戮(さつりく)を行うに至った思想、原因、経緯、そして実態と帰結を、最新の研究成果を踏まえて整理している。『アウシュビッツ』が犠牲者の「下から」の眼(め)だとすれば、これはあえて「上から」の視線で見ている。芝は、ホロコーストは狂った独裁者ヒトラーが命令し実行したという単純なものではないという。
過激な人種主義を基礎に「非アーリア」人追放を掲げたナチスは、政権につくやドイツ国内からのユダヤ人やロマの追放を始め、ポーランド侵攻の後は東欧への移送と「ゲットー化」を進めた。だが、ソ連侵攻以降、大量に抱え込んだ「非アーリア」人を処理できず、初めは現場主導の場当たり的な大量虐殺を行ったが、独ソ戦が膠着(こうちゃく)化すると、絶滅収容所での計画的な大量殺戮をトップにおいて決定した。このような「試行錯誤」の過程で600万人余の「非アーリア」人が殺戮されたのだ。
芝によれば、このホロコーストをめぐっては、長年「なぜ」それが起こったのかが論じられ、その責任主体はヒトラー個人か、ナチ体制の構造そのものかが争われてきている。だが、最近は「どのようにして」それが行われたのか、また一般市民の態度はどうだったのかという関心が高まっているという。
芝は、第2次世界大戦前後のヨーロッパ全体の構造的・文化的共通性の中でこれを考える必要があると言う。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010136.html
*アフリカ 苦悩する大陸 [著]ロバート・ゲスト
[掲載]2008年6月29日
[評者]松本仁一(ジャーナリスト)
■「政府が国民を食い物に」と腐敗を指摘
アフリカはなぜ貧しいのか。
「植民地として搾取を受けてきたため」というのが従来の模範解答だった。しかし著者は断定する。
「アフリカが貧しいのは、政府に問題があるからだ」
政府が無策なだけなら、国民は自力で生きていくことができる。しかしアフリカでは「あまりに多くの政府が国民を食い物にしている」とこの本はいうのである。
政府は、権力者が私腹を肥やすために存在する。官僚はわいろを要求する。警官は国民から金品を奪う――。その実例が次々に登場する。
ジンバブエ。役所の非能率で電話がなかなか引けない。そこである民間人が携帯電話会社を設立した。ところが政府は、民間の電話事業を禁ずる法律をつくる。裁判所がそれを違憲と判断すると、政府は事業を免許制に切り替え、免許を大統領の親族に与えてしまった。
カメルーン。著者はビール輸送のトラックに便乗する。ところが500キロ先の目的地まで4日かかってしまった。なんと47回、検問でとめられたのである。警官は金を渡すまで運転手の免許証を返してくれなかった。
アフリカの多くの政府は国民を支えるどころか、自立しようとする人々を妨害さえしているのである。
国連や世銀などの援助関係者が政府の腐敗を指摘したことはある。しかしそのたびにレイシスト(人種差別主義者)呼ばわりされ、口をつぐんだ。アフリカの政府批判はタブーだった。
しかし最近、タブーを破る発言が相次ぎはじめた。もう黙っているわけにはいかない、という気分。この本もそうした一つである。
著者は英誌「エコノミスト」の元アフリカ特派員。すべての国を調べているわけではないし、順調に国づくりが進むボツワナなどの例もある。だが、同じアフリカ特派員だった私の経験からも、この本の視点は正しいと思う。
アフリカ苦悩する大陸
著者:ロバート・ゲスト
出版社:東洋経済新報社 価格:¥ 2,310
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807010124.html
*『「戦争」の心理学…』=グロスマン、クリステンセン著 [毎日]
小西聖子(たかこ)・評 『「戦争」の心理学--人間における戦闘のメカニズム』=D・グロスマン、L・W・クリステンセン著
(二見書房・2520円)
第二次世界大戦の最中にアメリカ軍で兵士の大規模調査が行われた。戦闘直後に行われた調査によると、ドイツまたは日本軍との接近戦に参加した兵士の発砲率は、どの場合でも15%から20%だったという。撃っても当たらないとか、逃げ出したということではなく、8割以上の兵士は、発砲さえしていなかった。敵と至近距離で向かい合ってさえ人は簡単には人を殺せない。そして、二〇世紀になってからの戦争ではつねに、ストレスで心身衰弱の状態になり戦闘できなくなる確率の方が、敵に撃たれて死ぬ確率よりずっと高かった。
唯一の例外はベトナム戦争であると著者は言う。この戦争では発砲したアメリカ兵士の割合は90%に達し、心身の衰弱を経験する確率と敵に殺される確率はほぼ等しくなった。ベトナム戦争では、アメリカ軍は、兵隊が人を殺すことができるように訓練を改良してから、兵士を送り出したからである。
簡単に言えば、それは繰り返しの射撃訓練である。ただし、丸い標的ではだめで、リアルな状況でリアルな人型標的を打つことが重要であった。「シミュレーターの迫真性」が効果をあげたのである。もっとよいのは、当たれば痛みは感じるペイント弾を使って、実戦に近い形で、人を撃つことを繰り返し訓練することだ。繰り返し慣れさせ、考えなくても判断し、対応できる、そういう行動主義的なトレーニングをおこなうと人に対する発砲率は高まることが示された。
ただし、ベトナム戦争では、兵士は発砲できるようになったが、その殺傷による心理的衝撃については何も教えてもらわなかったし、準備も訓練もなかった。彼らは反戦運動のさなかの母国に帰国し、孤立し、多数の帰還兵にPTSD(心的外傷後ストレス障害)が発生した。
ならば、次に考えるべきことは、どうやって落ち着いて殺傷し、恐怖にとらわれることなく生還し、街角の人間を撃ったりすることなく、家族とともに安定した生活を営むことができるのか、ということがポイントになる。
著者グロスマンは、アメリカの陸軍士官学校ウエストポイントの心理学、軍事学の教授で、「殺人学」の専門家、当然軍人である。本書は彼の前著『戦争における「人殺し」の心理学』(ちくま学芸文庫)と一続きになっている。前著はアメリカでは軍事学の教科書として広く採用されているそうだ。そして続編であるこの本は、軍人だけでなく、警察官や消防士など身体的な危機に身を晒(さら)す職業の人たちを読者に想定して書かれている。
この軍隊の中の研究の成果が非戦闘員のPTSDにも応用されるようになり、その後、性暴力被害者などを対象とした治療研究がすすんで科学的にも洗練されたという方が正しい。本家はアメリカ軍である。戦争をしている国が一番予算をつけたい研究は、どう考えてもそっちのほうだ。私はとても複雑な気持ちになった。
毎日新聞 2008年6月1日 東京朝刊
URL:http://mainichi.jp/enta/book/hondana/news/20080601ddm015070005000c.html
*0604 『ロシア闇と魂の国家』 亀山郁夫・佐藤優 [読売]
ロシアを「国家」たらしめている「独裁」について、佐藤が現実政治からリアルな見方を示せば、一方の亀山はドストエフスキーの小説を例に、ロシア人の「魂」と「大地」のつながりを論じる。政治と文学をめぐる重厚な議論は、かの国の伝統をほうふつとさせる。
極端から極端へ振れる国民性を理解するカギを、ロシアの歴史に深く根ざした終末思想と宗教的熱狂の中に見て取るなど、ロシアの精神性に深く切り込んだ対話は興味深い。
(2008年6月4日 読売新聞)
出版社:文藝春秋
発行:2008年4月
ISBN:9784166606238
価格:¥788 (本体¥750+税)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/book/column/press/20080603bk0c.htm
*0504 クリエイティブ資本論 新たな経済階級の台頭 [著]リチャード・フロリダ [朝日]
[掲載]2008年05月04日
[評者]橋爪紳也(建築史家、大阪府立大学教授)
■創造力を持つ「階級」が都市を動かす
「クリエイティブ・クラス」と呼ぶべき階層が世界規模で台頭していることを指摘、知識や創造性を究極の資源とする経済と社会の仕組みを新たに構築する必然性を説く。02年に米国でベストセラーとなった都市経済学の話題書がようやく邦訳された。
科学者、技術者、芸術家、音楽家、建築家、作家、デザイナーといった職能、加えてビジネス・教育・医療・法律など専門家が急増している事実が、本書の前提になる。たとえば米国では、高度な知識や創造力を必要とする職能の従事者は、20世紀初頭には労働力の1割に過ぎなかった。しかし21世紀には、全体の3分の1を占めるほどに増加する。
彼らは脱工業化社会への転換期にあって「勝ち組」となり、経済や政治の中枢で活躍している。ただ他人には無関心で、自己中心的な人が少なくないという批判がある。また何よりも自分たちをまとまった集団とは考えてはいない。彼らが社会問題の責務を積極的に担い、唯一、「21世紀社会の指導者」になると確信する著者は、この層を「クリエイティブ・クラス」と命名、「階級」としての覚醒(かくせい)をうながす。
知識や創造性が産業を生むという議論は早くからある。近年も伝統的な職人の技やアートの力で、欧州の歴史都市が再生を遂げた先例が「創造都市」の概念とともに日本に紹介された。地域に潜む文化的な資産を再評価、内発的に活力の向上をはかる方法論は横浜や金沢でも応用された。
しかし本書は、欧州の実践とは一線を画する。とりわけクリエイティブ・クラスのライフスタイルに着目している点が面白い。彼らは自分の能力が生きる職場、より良い生活環境を求めて、転居することをいとわない。結果として彼らが魅力を感じる都市と、そうではない都市とのあいだで経済格差が拡大すると著者は仮説を示す。
この点を実証するべく著者は、技術・才能・寛容性という三つの指標から、都市や国家の創造力のランキングを試みることの必要性を説く。文化の多様性を認めあい、クリエイティビティに対して開かれた地域に、経済発展の可能性があるとみる理屈だ。原著が出版された際、ゲイ・カルチャーを容認するかどうかを指標として用いた点が話題になったが、必ずしも立論の本質ではない。
創造力のある優秀な人材は、住みやすさと活躍の場を求めて居住地を移し、時にはやすやすと国境を越える。本書で提示された議論は、フロリダの著作『クリエイティブ・クラスの世紀』でさらに展開されている。併読することをすすめたい。
もちろんわが国でもクリエイティブ・クラスの台頭があった。しかしその種の現象を「IT長者」「ヒルズ族」などと名づけて、きわめてローカルな世相風俗に矮小(わいしょう)化した感性はいかにも日本的だ。東京を始め日本の各都市も、国際的な都市間競争にあって、クリエイティブ・クラスを誘引する都市基盤の拡充に力を入れる発想が、これまで以上に必要だろう。
クリエイティブ資本論―新たな経済階級の台頭
著者:リチャード・フロリダ
出版社:ダイヤモンド社 価格:¥ 2,940
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805060068.html
*0504 創氏改名 日本の朝鮮支配の中で [著]水野直樹 [朝日]
[掲載]2008年05月04日
[評者]赤澤史朗(立命館大学教授・日本近現代史)
■同化政策に差異を残したチグハグ
誰でも自分の名前にはこだわりがある。ところが行政当局から突然、半年以内に新しい名前を届け出ろ、今後それを本名にするといわれても、当人は納得しにくいし、知り合いが誰さんなのかも分からなくなり、大混乱に陥るだろう。しかし創氏改名は、それを強行する政策だった。
名前の付け方は、それぞれの国と民族の家族制度によって決められるものだ。韓国・朝鮮人の場合は、夫の姓と妻の姓が違っている。妻は結婚しても、出身の実家の姓を変えないからである。
こうした習慣の朝鮮人に、日本人と同じように夫婦に共通する家の称号である氏を新たに作らせ、それを本名にする政策が「創氏」であった。それは朝鮮の家族制度の力を弱め、日本の「イエ」制度を朝鮮に導入するものだった。ついでに下の名前も、日本人風に変えるのが「改名」である。
本書は、創氏改名の矛盾に満ちた実態を叙述したものである。そこでは創氏は義務の届け出制で、朝鮮総督府をあげて督励し強要されたが、改名は当局の許可制で途中から奨励されなくなった。
そのため多くの朝鮮人は、創氏の届け出はしたが改名はせず、日本人風の氏と朝鮮人風の名を持つ、日本人に似ていながら日本人との違いが目立つ名前になってしまった。朝鮮人の姓に由来する、日本人には見かけない氏も創(つく)られた。それは日本への同化政策でありながら、完全な同化はさせないで、日本人との差異を残すものだった。日本人の中には朝鮮人への優越意識から、朝鮮人を日本人と同じ氏名とすることに反発する動きがあり、これが実施過程で影響したようだ。
著者は創氏改名が、朝鮮社会の家族制度を総督府が力づくで変えられると思い込んだ地点に生まれたと指摘している。でもそれは朝鮮人の反感や面従腹背の態度とともに、一部の日本人の反発も呼んだのである。強権的でありながら、どこか首尾一貫しないチグハグな創氏改名の実情を明らかにすることで、単純に同化政策とばかりはいえない、日本の支配の論理の特徴を考えさせる労作だ。
創氏改名―日本の朝鮮支配の中で (岩波新書 新赤版 1118)
著者:水野 直樹
出版社:岩波書店 価格:¥ 819
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805060055.html
*憲法9条の思想水脈 [著]山室信一 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]四ノ原恒憲(編集委員)
■「英知の結晶」成り立ち追う
参院選での自民党大敗北のひそかな原因の一つが、憲法改正に性急な首相への不安では、と思えてならない。そんな改正論議の中心である憲法9条を支える平和思想の成り立ちを、丁寧に、丁寧に追っている。
戦争が古来、大きな災禍であった以上、洋の東西を問わず、不戦への道を説く思想は、長い歴史を持つ。一挙に国際政治の荒波に投げ出された明治以降の日本にも、東西の不戦思想の影響を受けた中江兆民ら多くの論者が現れる。特に、日清・日露の経験は、その願いを切実なものにした。
ただ、国内外を問わず、現実主義者から「夢想」と遠ざけられたのも確かだ。でも、その「夢想」が無駄であったともいえない。国際連盟、パリ不戦条約、そして国際連合とその夢の一部は形を変え実現してきた。9条の精神は、日本人を含む長い人類の英知の結晶であり、決して「押しつけ」うんぬんで片づけられるほどやわなものではない。
憲法草案に深くかかわった幣原喜重郎・元首相は、述べる。「戦争放棄は正義に基づく正しい道であって日本は今日この大旗を掲げて国際社会の原野を単独で進んで行くのである」。こんな言葉がまぶしすぎる時代は、少し悲しい。
憲法9条の思想水脈
著者:山室 信一
出版社:朝日新聞社出版局 価格:¥ 1,365
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070310.html
*戦争の記憶 忘れたことさえ忘れるまえに(テーマ書評) [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]大上朝美
8月。太平洋戦争が終わって、間もなく62回目の記念日が来る。
「忘れたことさえ忘れてしまうまえに、薄れゆく記憶を取り戻すことをはじめたい」という山口誠著『グアムと日本人』は、日本人でにぎわう「楽園」の成り立ちの歴史を掘り起こす。真珠湾攻撃の直後に日本軍が占領し、「大宮島」と改称したことも日本ではあまり知られないいま、日米激戦の地・タモン湾には日本軍のトーチカが残り、挙式用の「日本人の教会」が立つ。「どちらも眺めが良いポイントを好む」という現地の人の言葉は痛烈だ。
グアムで米軍再上陸の激しい戦闘が行われていたころ、『野火』『俘虜(ふりょ)記』などを後に書く作家・大岡昇平はフィリピン・ミンドロ島に送り込まれた。大岡が70年夏に戦争体験を語り下ろした『戦争』は、小説の張りつめた緊迫感とは異なる趣で、淡々と、ざっくばらんな記述だが、詳細に繰り出す記憶のさまに引き込まれる。
44年夏に陥落したサイパン、グアムから飛び立つB29は、国内に爆弾・焼夷(しょうい)弾の雨を降らせた。『手塚治虫「戦争漫画」傑作選』は、空襲の恐怖や銃後の社会の息苦しさを生々しく核に持つ作品群だ。68年から79年にかけて発表された7編を収める。
乾淑子編著『図説 着物柄にみる戦争』には意表を突かれる。著者自身も2000年冬、インターネットオークションで、日中戦争を背景にした柄の乳児用の着物を初めて見て驚いたと書く。以来、著者が収集した着物を中心に紹介される戦争柄には「兵器」あり「上陸作戦」あり「愛国少年団」あり……。戦後の物不足の時でも着るのははばかられ、しまい込まれて永らえて、いまでは「面白柄」の一つとして人気という。確かに心引かれる面白さなのは、どうしよう。
図説着物柄にみる戦争
出版社:インパクト出版会 価格:¥ 2,310
グアムと日本人―戦争を埋立てた楽園 (岩波新書 新赤版 1083)
著者:山口 誠
出版社:岩波書店 価格:¥ 777
野火 (新潮文庫)
著者:大岡 昇平
出版社:新潮社 価格:¥ 340
俘虜記 (新潮文庫)
著者:大岡 昇平
出版社:新潮社 価格:¥ 660
戦争 (岩波現代文庫 社会 155)
著者:大岡 昇平
出版社:岩波書店 価格:¥ 1,050
手塚治虫「戦争漫画」傑作選 (祥伝社新書 81)
著者:手塚 治虫
出版社:祥伝社 価格:¥ 788
URL:http://book.asahi.com/hondana/TKY200708070340.html
*大地の慟哭―中国民工調査 [著]秦尭禹 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]高原明生(東京大学教授・東アジア政治)
■農村から出稼ぎ、想像を超す苦境に
来年のオリンピックを控えた北京ならずとも、現在、中国の大都市の建設ラッシュはすさまじい。急速に進む中国の都市化、そして「世界の工場」とまで言われるようになった工業化を支えているのは、「民工」と呼ばれる農村からの出稼ぎ労働者だ。
いまや2億人はいると言われる民工は、いわゆる3Kの仕事を受け持ち、仕送りによって農村経済にも大きく貢献する。例えば03年には、それによって四川省の農民の純収入は50%増えたという。
本書は、中国で05年1月に出版され、多くの人に読まれた『中国民工調査』の邦訳である。著者は香港のエコノミスト。中国のいくつかの都市での実地調査と豊富な文献調査を組み合わせ、民工の生活の実態に迫り、それを多面的に描き出した。
一部の民工の実態の厳しさは想像以上だ。給料の遅配欠配は驚くに値しない。劣悪な労働環境による労働災害の頻発と社会保障の欠如、「民工米」と呼ばれる、食用に適さない古い米などを使った粗末な食事、性の抑圧と精神生活の不毛、民工の子供の就学難と学校でのいじめ、そして農村の留守家庭に残された子供への虐待やストレス。民工と農村は都市主導の変革の波に呑(の)み込まれ、血縁を中心とした農村の姻戚(いんせき)文化と社会システムは破壊されたと著者はいう。
中国の指導者は決して無為無策でいるわけではない。差別をなくし、民工に正式労働者と同じ待遇を与えるよう指示を次々と出している。また、女子労働者や熟練工の不足が広東などで深刻化し、賃上げ圧力となっている。
民工の苦難は高度成長に伴う過渡的な問題なのかもしれない。成功している民工だって少なくないはずだ。だが広い中国の場合、過渡期は相当長くならざるをえまい。制度上は差別を廃止しても、豊かな沿海大都市を除き、実態として民工全員に社会福祉を提供することは当面不可能である。差別意識の解消も簡単ではない。表はぴかぴかの摩天楼だが、その裏には長く、濃い影があることを本書は教えてくれる。
◇
田中忠仁ほか訳/チン・ヤオユイ 経済学博士、香港の管理顧問会社マネジャー。
大地の慟哭(どうこく)
著者:秦 尭禹
出版社:PHP研究所 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070290.html
*[[◎平和をつくるための本棚06]] より続く
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: