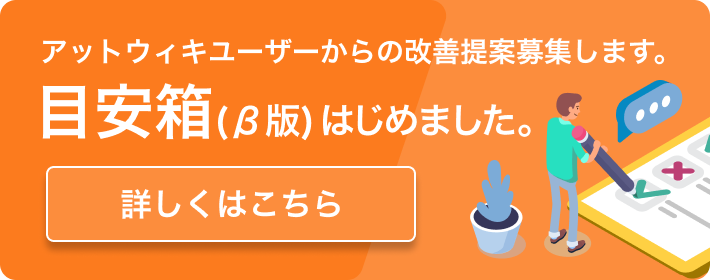新生人工言語論
高級語の命名法
最終更新:
lideldmiir
-
view
(注)後述の新生人工言語とは文化を定めた言語程度の意味です。
千前後の基本語や、もう少し多い日常生活語を作り終えると、次は高級語に入ります。これは数が多くて大変です。
ここでは高級語の命名法について述べますが、機械類より広域性の高い自然物に特化して説明しています。
ここでは高級語の命名法について述べますが、機械類より広域性の高い自然物に特化して説明しています。
ここで述べたいのは形態論ではありません。形態論に関しては先にさらっと述べます。
形態論的にみれば高級語は合成語が便利でしょう。辞書が引きやすいし、1語で1つの概念を表わせるからです。
フランス語の場合、連語で高級語を表わすことが多いので辞書が引きづらいです。しかも何語で1つの概念か分かりづらいので、見づらいです。
形態論的にみれば高級語は合成語が便利でしょう。辞書が引きやすいし、1語で1つの概念を表わせるからです。
フランス語の場合、連語で高級語を表わすことが多いので辞書が引きづらいです。しかも何語で1つの概念か分かりづらいので、見づらいです。
フランス語には高級語だけでなく、基本語にもこの性質が生きています。
たとえば蹴るという概念について。蹴るに当たる語がないわけではないのですが、donner un coup de pied(足の一撃を与える)ということがあります。
kickやpunchというレベルで言い分けるのではなく、coup(一撃)という上位概念を使うことによる言い分けです。この性質がフランス語では高級語にも及びます。
ドイツ語のように長大な語にはなりませんが、スペーシングと前置詞が入った分、結果的に更に長くなります。
たとえば蹴るという概念について。蹴るに当たる語がないわけではないのですが、donner un coup de pied(足の一撃を与える)ということがあります。
kickやpunchというレベルで言い分けるのではなく、coup(一撃)という上位概念を使うことによる言い分けです。この性質がフランス語では高級語にも及びます。
ドイツ語のように長大な語にはなりませんが、スペーシングと前置詞が入った分、結果的に更に長くなります。
基本語の例をもうひとつ挙げると、蛾はドイツ語ではNachtfalterですが、フランス語ではpapillon de nuitです。結果としてフランス語のほうが長くなっているのが見て取れます。
フランス語批判をしたいのではありません。人工言語で高級語を作るときは合成語を推奨すると言っています。
フランス語批判をしたいのではありません。人工言語で高級語を作るときは合成語を推奨すると言っています。
合成語にも欠点はあります。合成語の要素間の関係が掴みにくいことです。
たとえば「前掛け」の先行要素「前」は前半身という場所を指しますが、「涎掛け」の「涎」は場所でなく防ぐ対象を指します。
しかしこの程度なら常識で判断できますから、一々混乱しません。
たとえば「前掛け」の先行要素「前」は前半身という場所を指しますが、「涎掛け」の「涎」は場所でなく防ぐ対象を指します。
しかしこの程度なら常識で判断できますから、一々混乱しません。
合成語は要素間の関係が掴みにくいのが欠点ですが、関係を掴みやすくするために前置詞に相当するものを接辞化すると、今度は語形が長くなります。
あっちを立てればこっちが立たずですが、要素間の関係は慣例として学習者に覚えさせることにしたほうが語形が短く、実用時に便利です。さて、形態論はこのくらいにしましょう。
あっちを立てればこっちが立たずですが、要素間の関係は慣例として学習者に覚えさせることにしたほうが語形が短く、実用時に便利です。さて、形態論はこのくらいにしましょう。
人工文化がどの程度の科学力を持っているかによって、高級語の内容は変わります。
科学が発達した文化なら当然、それを表わす語が必要になります。
人工文化の場合、その文化の科学史から作らねば適切な命名ができません。しかし個人や小団体で科学的な命名法を多岐に渡って作るのは不可能です。
科学が発達した文化なら当然、それを表わす語が必要になります。
人工文化の場合、その文化の科学史から作らねば適切な命名ができません。しかし個人や小団体で科学的な命名法を多岐に渡って作るのは不可能です。
作ろうとしても完成する前に寿命が尽きますし、科学の成長に追いつけません。
2005年から科学の語を全て作ったとしましょう。たとえば2100年に作業が完成するかもしれませんが、完成したのは2005年までの内容で、作業中の95年分の進歩に付いていっていません。
こちらが作るより遥かに多くの人数が造語を繰り返しているので、追いつくことさえ無理でしょう。
2005年から科学の語を全て作ったとしましょう。たとえば2100年に作業が完成するかもしれませんが、完成したのは2005年までの内容で、作業中の95年分の進歩に付いていっていません。
こちらが作るより遥かに多くの人数が造語を繰り返しているので、追いつくことさえ無理でしょう。
また、ゼロから自分たちで現在の地球の科学力を越えた文化を創るのも事実上不可能です。
SFチックないい加減な設定なら可能でしょうが、細かい専門用語を専門知識に則って作る人員と時間はありません。
SFチックないい加減な設定なら可能でしょうが、細かい専門用語を専門知識に則って作る人員と時間はありません。
そこで結論としては、ある程度現在の地球の科学力に頼って、限られた範囲を命名するしかありません。
まぁ、実際問題、そのような高級語は作ったところでまず使うことがありませんから実用に支障はないでしょう。
語を作るのはその分野が必要になったときでいいでしょう。必要になったら作るというのは言語の基本的性質にも合致します。
まぁ、実際問題、そのような高級語は作ったところでまず使うことがありませんから実用に支障はないでしょう。
語を作るのはその分野が必要になったときでいいでしょう。必要になったら作るというのは言語の基本的性質にも合致します。
極端な話、科学の乏しい文化を作り上げれば科学の語彙は要らないのですが、それだと現代の先進国では表わせない物が多くなってしまい、困ります。
日常で科学が介在しているものは多いです。家電やPCや薬など、枚挙に暇がありません。
日常で科学が介在しているものは多いです。家電やPCや薬など、枚挙に暇がありません。
一方、仮に科学の語彙を狭めたとしても、依然として変わらないのは自然物の語彙です。
動植物など、その風土に存在するものは科学力に関係なく命名せねばなりません。ところがこれがかなり多いです。
ここからは普及型も考慮して人工言語全般で自然物の命名法について考えていきましょう。
動植物など、その風土に存在するものは科学力に関係なく命名せねばなりません。ところがこれがかなり多いです。
ここからは普及型も考慮して人工言語全般で自然物の命名法について考えていきましょう。
自然物を命名する際、人工言語一般の立場に立つと、できるだけ広範囲の動植物を公平に命名したいです。
牛を重宝する文化に焦点を合わせてしまうと、牛ばかり細かく分類されて不公平です。そこで、なるべく人工言語としては公平に行きたいものです。
となると思い当たるのは自然科学です。国際的な自然科学の分類にしたがって命名できれば、少なくともどこかの言語の分類に合わせるよりは広範囲で公平といえます。
牛を重宝する文化に焦点を合わせてしまうと、牛ばかり細かく分類されて不公平です。そこで、なるべく人工言語としては公平に行きたいものです。
となると思い当たるのは自然科学です。国際的な自然科学の分類にしたがって命名できれば、少なくともどこかの言語の分類に合わせるよりは広範囲で公平といえます。
かといって自然科学はある対象が日常的か否かなど気に掛けてくれませんので、リンゴのような卑近なものにも長大な名を付けます。
そこで、基本語については自言語のやり方で動植物の名を決めましょう。
後験語なら参考言語から語を拝借し、新生人工言語なら文化に沿って動植物を分類し、命名しましょう。
それが終わって初めて滅多に出てこない自然物、つまり高級語を命名し、その際に自然科学を利用しましょう。
そこで、基本語については自言語のやり方で動植物の名を決めましょう。
後験語なら参考言語から語を拝借し、新生人工言語なら文化に沿って動植物を分類し、命名しましょう。
それが終わって初めて滅多に出てこない自然物、つまり高級語を命名し、その際に自然科学を利用しましょう。
自然科学は分類が民間分類より遥かに細かいので、緻密な命名が可能です。ただし学名をそのまま訳すと語形が長くなるので、邦名を付けるが如くできるだけ簡素なものにしましょう。
また、学名を単に簡素に訳すのでも構いませんが、調査の上で自文化に基づいた命名をするのも良いでしょう。
たとえばダチョウは最大の鳥なので「大きい鳥」を語源にするのもいいでしょう。(もちろん、他の命名でも一向に構いません)
また、学名を単に簡素に訳すのでも構いませんが、調査の上で自文化に基づいた命名をするのも良いでしょう。
たとえばダチョウは最大の鳥なので「大きい鳥」を語源にするのもいいでしょう。(もちろん、他の命名でも一向に構いません)
こうしていけば当面必要になるレベルの自然物を命名することができます。
これで自然物の高級語は大丈夫? いえ、実は自然科学による分類は万能ではありません。
以前私はリンゴなど卑近な単語以外について科学的な命名をしましたが、以下の3つの点で戸惑いました。
これで自然物の高級語は大丈夫? いえ、実は自然科学による分類は万能ではありません。
以前私はリンゴなど卑近な単語以外について科学的な命名をしましたが、以下の3つの点で戸惑いました。
1つは科学を参考にすると、科学の変化によって一度決めたものが変わってしまうということ。
ある学説を境に、ある動植物の分類や信じられていた性質が変わってしまうということがありますが、地球の科学に合わせていると一度作った語を変えねばなりません。
変えないと間違いがそのまま残ります。最近の例だと「冥王星」とかね……。
ある学説を境に、ある動植物の分類や信じられていた性質が変わってしまうということがありますが、地球の科学に合わせていると一度作った語を変えねばなりません。
変えないと間違いがそのまま残ります。最近の例だと「冥王星」とかね……。
2つは、科学の歴史のせいで変な分類になった動植物の命名です。
ホタルイカはホタルイカモドキ科です。ホタルイカの方が下位なのに、歴史的にホタルイカが早くから馴染まれていたからだそうです。
我々から見れば奇妙なこの科学的命名に対し、人工言語が一々付き合うのは不自然な気がします。
もう科学的な答えを知っている私たちが上位であるホタルイカモドキにモドキと命名するのは不自然です。
ホタルイカはホタルイカモドキ科です。ホタルイカの方が下位なのに、歴史的にホタルイカが早くから馴染まれていたからだそうです。
我々から見れば奇妙なこの科学的命名に対し、人工言語が一々付き合うのは不自然な気がします。
もう科学的な答えを知っている私たちが上位であるホタルイカモドキにモドキと命名するのは不自然です。
しかし、これらは世界と調和する普及型にとっては瑣末な問題でしょう。
問題は3つ目です。自然科学的による命名は、日本語の動植物命名などより遥かに細やかな定義を可能にします。非常に便利です。
しかしながら、科学分類よりもむしろ民間分類の方が細かく、しかも定着しているものがあるのです。
問題は3つ目です。自然科学的による命名は、日本語の動植物命名などより遥かに細やかな定義を可能にします。非常に便利です。
しかしながら、科学分類よりもむしろ民間分類の方が細かく、しかも定着しているものがあるのです。
たとえば鷲と鷹は科学的には同じタカ科で、大きさでぼんやり区別しています。そのせいで専門家でもまとめてワシタカ科などと呼んでいた経緯もあるそうです。科学的には鷹匠は鷲匠でもいいのですね。ちょっと不思議な気がします。
しかし、日本語は鷲と鷹の区別を持っています。日本語だけならいいのですが、どうも日本語に特殊な区分ではないようです。
しかし、日本語は鷲と鷹の区別を持っています。日本語だけならいいのですが、どうも日本語に特殊な区分ではないようです。
英:eagle hawk
独:der Adler der Falke(含ハヤブサ)
仏:l'aigle le faucon(むしろハヤブサ)
エス:aglo falko
芬:kotka haukka
中:jiu4 ying1
独:der Adler der Falke(含ハヤブサ)
仏:l'aigle le faucon(むしろハヤブサ)
エス:aglo falko
芬:kotka haukka
中:jiu4 ying1
つまり、自然科学では却って分類できないか、控えめに言っても分類しづらい概念があるということです。
そうなると自然科学を絶対視して自言語に鷲と鷹の区別を設けないか、そうでなくば、いくつかの自然言語を調査して、多くの言語で区別されている概念は特別に自言語でも区別するかのどちらかを選ぶことになります。
そうなると自然科学を絶対視して自言語に鷲と鷹の区別を設けないか、そうでなくば、いくつかの自然言語を調査して、多くの言語で区別されている概念は特別に自言語でも区別するかのどちらかを選ぶことになります。
多くの自然言語に存在している鷲と鷹の区別を科学の名の下に切り捨てて良いのでしょうか?
別に私たちは科学分類表を作っているのではありません。あくまで言葉を作っているのです。
その意味では科学に逆らって鷲と鷹を別の語として立てたほうが自然でしょう。
別に私たちは科学分類表を作っているのではありません。あくまで言葉を作っているのです。
その意味では科学に逆らって鷲と鷹を別の語として立てたほうが自然でしょう。
鷲と鷹は卑近な語なのでいいのですが、もっと込み入った語になると更に困惑するでしょう。
自然科学を利用した命名は確かに強力ですが、万能ではないということを覚えておいてください。
自然科学を利用した命名は確かに強力ですが、万能ではないということを覚えておいてください。
人工文化を持つタイプの新生人工言語は自文化に沿って命名するので鷲と鷹の区別が科学にあろうとなかろうとどうでもいいのですが、普及型の場合、鷲と鷹は国際的な科学で解決できない問題なので、戸惑うことでしょう。
そのような場合、メジャーな自然言語を調査し、多数決で決めるのが実践的です。つまり、科学で掬いきれなかった零れを自然言語で補完しようということです。
そのような場合、メジャーな自然言語を調査し、多数決で決めるのが実践的です。つまり、科学で掬いきれなかった零れを自然言語で補完しようということです。