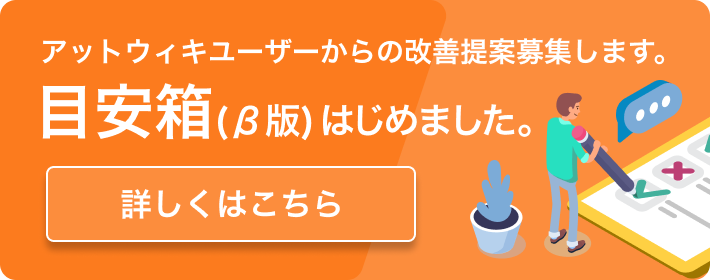「シナリオイメージ1-1」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「シナリオイメージ1-1」(2008/11/07 (金) 10:36:43) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*シナリオイメージ1-1
怖いほどの赤。
すべてを飲み込まんとするような、大きく赤い夕日がそこにはあった。
このような時間を昔の人は逢魔ヶ刻と称したらしい。
異界と現世が混じり合い、人外のものがあらわれるという。
すべてが紅に染まり、いつも見慣れた景色さえも違う場所のようだ。
このような景色を見せられると、あながち絵空事ではないのかもしれないと思ってしまう。
もしそんな存在が現実にあるのならば、逢ってみたいものだ。
この退屈な日々が終わるのならば……。
そんな期待もむなしく、何事もなく俺が住むアパートへとたどり着いてしまった。
階段をあがる俺の足が鉄の響きを奏でる。
まるで俺の存在だけがここにいるかのように、やけにあたりに響く。
それともすでに俺は異界に紛れてしまったのだろうか?
「そんなわけないか……」
階段をあがれば錆びたドアの俺の住処が待っているだけだ。
「すぅ……すぅ……」
「……?」
聞き慣れない音に違和感を覚える。この階には俺以外の住人はいないはずだ。
火事で半焼したアパート。それゆえ俺でも借りられる手頃な家賃になっている。
階段から階の様子をのぞき込む。
「だれだ……?」
俺の部屋の前で、女の子が心地よさそうな寝息を立てて眠っていた。
白く長い髪。この肌寒い季節にまとっているのは薄い布地のみ。
異界の者という言葉がぴったりだった。
夕焼けのせいか、その顔や手がやけに赤くみえる。
現実から切り取られた世界がそこにはあった。
俺は夢でも見ているのだろうか。その顔をただ見つめる以外、俺にはなにもできなくなっていた。
なんの臭いだ?(赤く反転)
やけに鼻につく臭いが俺を現実に引き戻す。
「これは……血?」
鼓動が高鳴る。女の子の顔や手にびっしりとついていたのは、間違いなく血だった。
「おい、大丈夫か!?」
女の子の体をゆする。眠たそうに薄目を開け……また閉じてしまった。
「すぅ……すぅ……」
小さな寝息を立てながら、まるで安全な場所だとでもいうように無防備にその体をさらしている。
「呼吸は……安定してるな。傷は右手だけか」
顔の方は手でこすりでもしたのだろう。これならば俺でも応急処置はできそうだ。
とりあえず、この寒空の下に置いておくわけにもいかないだろう。
女の子をそっと抱え、部屋の中にいれることにする。
「なんだ?」
部屋の扉には血で意味不明の絵が描かれていた。この子が描いたのだろうか?
興味はひかれたが、今は女の子の手当が先決だ。
女の子を敷きっぱなしだった布団に寝かせ、ホコリまみれの救急箱を取り出す。
消毒液にひたした脱脂綿を傷口にあてがう。しみたのか女の子が顔をしかめる。
「たいしたことはなさそうだな」
どうやら薄皮を切っただけのようだ。出血の量ほど傷は深くなかった。
傷薬を塗ったガーゼを包帯で固定し、手当を終えることにする。
となると怪我で倒れたというわけではなさそうだが、未だまったく起きる様子がない。
見たこともない白い髪。この子は本当に現世の者なのだろうか?
「警察に連絡するにしても、この子が起きてからか……」
幸せそうな寝顔をしたままのこの子を、俺はもっと見ていたいだけなのかもしれない。
「……ん?」
気がつけばあたりはすっかり暗闇に包まれていた。
目覚まし時計の時刻は6時をまわっている。どうやらしばらくうとうとしてしまっていたらしい。
女の子は……もぬけの空だった。寝かしていたはずの布団にはその姿はどこにもなかった。
「夢……だったのか?」
あまりにも現実離れした出来事。俺の妄想が見せていただけなのかもしれない。
眠った頭を起こそうと頭をふり、電気をつけようと起き上がろうとする……やけに右腕が重い。
右腕を見れば街灯の明かりに照らし出され、白く輝くその髪がそこにあった。
「すぅ……すぅ……」
いつの間に移動していたのか、女の子が俺の腕をがっちりと抱え込んでいた。
その感じたことのない、柔らかなぬくもりに何だか気恥ずかしくなってくる。
「おい、いい加減起きてくれよ……」
半分起きていたのか、先ほどとは違いうっすらとその目を開ける。
「……っ」
思わずその目を見て息を飲んだ。
兎のそれとも違う、血のように赤い目がそこにはあった。
「んー……?」
ぼうっとした表情で俺の顔をみつめる。
警戒心というものがないのであろうか、見知らぬ部屋にいるというのに動じている様子がまったくない。
「で、お前は一体だれなんだ?」
ぎゅ~
かわいらしい返事が返ってきた。
「腹へったのか?」
俺の顔と自分のおなかを見比べ、こくりと返事する。
「わかった。今つくるから食べ終わったら答えてくれよ」
まだ夕飯には少し早いが、どうせ俺も飯にしようと思っていたところだ。準備をしようと腰をあげる……右手が重い。
「飯食いたいなら、放してくれないと作れないんだが」
俺の右手と自分のお腹を交互にさすったりしながら、なにやら悩んでいるようだ。
しかし空腹には負けたのか、俺の腕はやっと解放される。
「すぐ作るから、テレビでもみて待っててくれ」
「……?」
俺のいった意味がわからなかったのか、小首をかしげて俺の方を見上げている。
とりあえずニュース番組を付け、リモコンをその手にもたせてやる。
見たい番組がないのか、しきりにボタンを押しながらころころと番組をかえている。
しばらくするとそれにも飽きたのか、ふとその手が止まる。
「また市街で女学生の失踪事件が発生しました。目撃証言もなく……」
俺の見知った風景が映し出される。その景色はこの街だった。
「少女を狙った誘拐事件か……えげつないな」
この女の子も、もしかしたらその犯人に狙われたのだろうか。
昨日までは他人事だったのだが、この子の傷をみるとなにやらその犯人にむかっ腹がたってくる。
「さてと、できたぞ」
ミートソースの臭いにつられたのか、女の子がぱたぱたとかけよってくる。
勢いあまったのか激しく俺に追突する。
「うおっと! お、落ち着け。食べ物は走って逃げたりしないぞ」
おもわず取り落としそうになった皿をなんとかバランスをとり、テーブルの上にのせる。
女の子はちょこんと座布団にすわり、いまかいまかと待ち受けているようだ。
「さあ、たべていいぞ」
フォークをさしだしてやる。しかし、いっこうにそれをつかむ様子がない。
「あーん……」
「ちょっと待て……まさかフォークの使い方も知らないのか?」
えさを待つヒナ鳥のようにあーんと口をあけたまま静止している。
「……?」
一向に口にはいってこないことに疑問を感じたのか、俺のほうを不思議そうな顔でみている。
「わ、わかった。たべさせてやるから。一体どこのお姫様だよ……」
フォークでパスタをからめ、その口にいれてやる。その口に収まると、もぐもぐと小さな口を一生懸命動かしている。
ミートソースの味が気に入ったのか、あーんと何度も催促してくる。
一皿では足りなかったのか結局俺の分の皿まで催促され、ずっと世話をさせられるはめになった。
「すぅ……すぅ……」
食べたら食べたで、ソースを口のまわりにつけながらすでにお姫様は夢の中だ。
「おーい、起きてくれ……まったく」
口のまわりのソースを拭きながら、何者なのだろうと頭をめぐらせる。
眠っている間に身元がわかるものがないか探ってみたが、財布はおろかなに一つ持っていなかった。
とりあえず本人が自分の口で話してくれないことには、何もわかりそうになかった。
テーブルの下で横になっている体を引きずり出し、布団に寝かしつかせてやる。
この様子だとちょっとやそっとでは起きそうにない。
「結局晩飯食べ損ねたし、寝ている間になにか買ってくるか……」
また催促されても困るし、少し多めに買ってきておくべきだろう。
*シナリオイメージ1-1
怖いほどの赤。
すべてを飲み込まんとするような、大きく赤い夕日がそこにはあった。
このような時間を昔の人は逢魔ヶ刻と称したらしい。
異界と現世が混じり合い、人外のものがあらわれるという。
すべてが紅に染まり、いつも見慣れた景色さえも違う場所のようだ。
このような景色を見せられると、あながち絵空事ではないのかもしれないと思ってしまう。
もしそんな存在が現実にあるのならば、逢ってみたいものだ。
この退屈な日々が終わるのならば……。
そんな期待もむなしく、何事もなく俺が住むアパートへとたどり着いてしまった。
階段をあがる俺の足が鉄の響きを奏でる。
まるで俺の存在だけがここにいるかのように、やけにあたりに響く。
それともすでに俺は異界に紛れてしまったのだろうか?
「そんなわけないか……」
階段をあがれば錆びたドアの俺の住処が待っているだけだ。
「すぅ……すぅ……」
「……?」
聞き慣れない音に違和感を覚える。この階には俺以外の住人はいないはずだ。
火事で半焼したアパート。それゆえ俺でも借りられる手頃な家賃になっている。
階段から階の様子をのぞき込む。
「だれだ……?」
俺の部屋の前で、女の子が心地よさそうな寝息を立てて眠っていた。
白く長い髪。この肌寒い季節にまとっているのは薄い布地のみ。
異界の者という言葉がぴったりだった。
夕焼けのせいか、その顔や手がやけに赤くみえる。
現実から切り取られた世界がそこにはあった。
俺は夢でも見ているのだろうか。その顔をただ見つめる以外、俺にはなにもできなくなっていた。
なんの臭いだ?(赤く反転)
やけに鼻につく臭いが俺を現実に引き戻す。
「これは……血?」
鼓動が高鳴る。女の子の顔や手にびっしりとついていたのは、間違いなく血だった。
「おい、大丈夫か!?」
女の子の体をゆする。眠たそうに薄目を開け……また閉じてしまった。
「すぅ……すぅ……」
小さな寝息を立てながら、まるで安全な場所だとでもいうように無防備にその体をさらしている。
「呼吸は……安定してるな。傷は右手だけか」
顔の方は手でこすりでもしたのだろう。これならば俺でも応急処置はできそうだ。
とりあえず、この寒空の下に置いておくわけにもいかないだろう。
女の子をそっと抱え、部屋の中にいれることにする。
「なんだ?」
部屋の扉には血で意味不明の絵が描かれていた。この子が描いたのだろうか?
興味はひかれたが、今は女の子の手当が先決だ。
女の子を敷きっぱなしだった布団に寝かせ、ホコリまみれの救急箱を取り出す。
消毒液にひたした脱脂綿を傷口にあてがう。しみたのか女の子が顔をしかめる。
「たいしたことはなさそうだな」
どうやら薄皮を切っただけのようだ。出血の量ほど傷は深くなかった。
傷薬を塗ったガーゼを包帯で固定し、手当を終えることにする。
となると怪我で倒れたというわけではなさそうだが、未だまったく起きる様子がない。
見たこともない白い髪。この子は本当に現世の者なのだろうか?
「警察に連絡するにしても、この子が起きてからか……」
幸せそうな寝顔をしたままのこの子を、俺はもっと見ていたいだけなのかもしれない。
「……ん?」
気がつけばあたりはすっかり暗闇に包まれていた。
目覚まし時計の時刻は6時をまわっている。どうやらしばらくうとうとしてしまっていたらしい。
女の子は……もぬけの空だった。寝かしていたはずの布団にはその姿はどこにもなかった。
「夢……だったのか?」
あまりにも現実離れした出来事。俺の妄想が見せていただけなのかもしれない。
眠った頭を起こそうと頭をふり、電気をつけようと起き上がろうとする……やけに右腕が重い。
右腕を見れば街灯の明かりに照らし出され、白く輝くその髪がそこにあった。
「すぅ……すぅ……」
いつの間に移動していたのか、女の子が俺の腕をがっちりと抱え込んでいた。
その感じたことのない、柔らかなぬくもりに何だか気恥ずかしくなってくる。
「おい、いい加減起きてくれよ……」
半分起きていたのか、先ほどとは違いうっすらとその目を開ける。
「……っ」
思わずその目を見て息を飲んだ。
兎のそれとも違う、血のように赤い目がそこにはあった。
「んー……?」
ぼうっとした表情で俺の顔をみつめる。
警戒心というものがないのであろうか、見知らぬ部屋にいるというのに動じている様子がまったくない。
「で、お前は一体だれなんだ?」
ぎゅ~
かわいらしい返事が返ってきた。
「腹へったのか?」
俺の顔と自分のおなかを見比べ、こくりと返事する。
「わかった。今つくるから食べ終わったら答えてくれよ」
まだ夕飯には少し早いが、どうせ俺も飯にしようと思っていたところだ。準備をしようと腰をあげる……右手が重い。
「飯食いたいなら、放してくれないと作れないんだが」
俺の右手と自分のお腹を交互にさすったりしながら、なにやら悩んでいるようだ。
しかし空腹には負けたのか、俺の腕はやっと解放される。
「すぐ作るから、テレビでもみて待っててくれ」
「……?」
俺のいった意味がわからなかったのか、小首をかしげて俺の方を見上げている。
とりあえずニュース番組を付け、リモコンをその手にもたせてやる。
見たい番組がないのか、しきりにボタンを押しながらころころと番組をかえている。
しばらくするとそれにも飽きたのか、ふとその手が止まる。
「また市街で女学生の失踪事件が発生しました。目撃証言もなく……」
俺の見知った風景が映し出される。その景色はこの街だった。
「少女を狙った誘拐事件か……えげつないな」
この女の子も、もしかしたらその犯人に狙われたのだろうか。
昨日までは他人事だったのだが、この子の傷をみるとなにやらその犯人にむかっ腹がたってくる。
「さてと、できたぞ」
ミートソースの臭いにつられたのか、女の子がぱたぱたとかけよってくる。
勢いあまったのか激しく俺に追突する。
「うおっと! お、落ち着け。食べ物は走って逃げたりしないぞ」
おもわず取り落としそうになった皿をなんとかバランスをとり、テーブルの上にのせる。
女の子はちょこんと座布団にすわり、いまかいまかと待ち受けているようだ。
「さあ、たべていいぞ」
フォークをさしだしてやる。しかし、いっこうにそれをつかむ様子がない。
「あーん……」
「ちょっと待て……まさかフォークの使い方も知らないのか?」
えさを待つヒナ鳥のようにあーんと口をあけたまま静止している。
「……?」
一向に口にはいってこないことに疑問を感じたのか、俺のほうを不思議そうな顔でみている。
「わ、わかった。たべさせてやるから。一体どこのお姫様だよ……」
フォークでパスタをからめ、その口にいれてやる。その口に収まると、もぐもぐと小さな口を一生懸命動かしている。
ミートソースの味が気に入ったのか、あーんと何度も催促してくる。
一皿では足りなかったのか結局俺の分の皿まで催促され、ずっと世話をさせられるはめになった。
「すぅ……すぅ……」
食べたら食べたで、ソースを口のまわりにつけながらすでにお姫様は夢の中だ。
「おーい、起きてくれ……まったく」
口のまわりのソースを拭きながら、何者なのだろうと頭をめぐらせる。
眠っている間に身元がわかるものがないか探ってみたが、財布はおろかなに一つ持っていなかった。
とりあえず本人が自分の口で話してくれないことには、何もわかりそうになかった。
テーブルの下で横になっている体を引きずり出し、布団に寝かしつかせてやる。
この様子だとちょっとやそっとでは起きそうにない。
「結局晩飯食べ損ねたし、寝ている間になにか買ってくるか……」
また催促されても困るし、少し多めに買ってきておくべきだろう。
→[[続く>シナリオイメージ1-2]]
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: