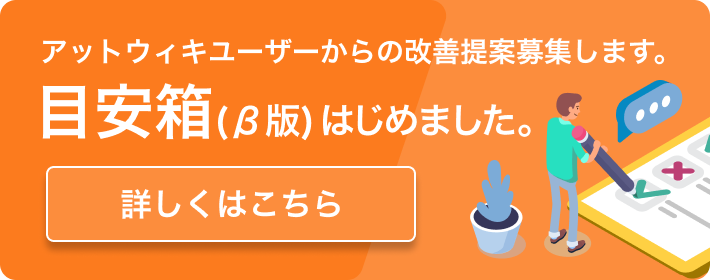+ R e l i a n c e +
『俺らがであったその理由』
最終更新:
aizeet
『俺らが出会った、その理由 Alzeet side』
目を開けて最初に入ってきたのは、昨日の天気からは想像も付かないような透通った日差しだった。
目が覚めた後、何も考えず天井を見つめていた。
「・・・この部屋にも、しばらく帰ってこれねェな・・・」
軽く呟いて、ぼーっとしていると、部屋を出てすぐの階段の下から、母の声が飛び込んできた。
「アル!すぐ出発するの?しっかり朝御飯は食べて行きなさいね!」
「ああ・・・すぐ降りるよ・・・。」
その場で返事したものの。結局、しばらくそのまま天井を見つめていた。
階段を下りるとき、風邪でも引いたのか、なんとなく寒気がした。おそらく、昨日の祖父との手合わせが原因だろう。天候が悪く、3日間雨が降り続き、ずっと稽古が出来ないことに業を煮やした祖父は、雨のなか稽古をすると言い出した。今日出発すると一ヶ月ほど前から決めていて、稽古をつけるチャンスを逃したらもう出来ないからだろう。一度言い出したら止めないのは、俺の家系の男代々の特徴だ。それを知っている俺は、反論もせず祖父とともに暴風雨の吹き荒れる庭へと飛び出した。
稽古の後、俺はすぐに疲れて寝てしまった。そのせいで寝冷えしたのだろう。この祖父、高齢だと言うのにやたら体力があり腕も立つ。酒が人並以上に好きなので、心配した母と祖母に進められ医師の診断を受けたときには、200歳まで生きるだろうと言われて帰ってきた。
結局、この家を出るまで、3本先取の手合わせで祖父には一度も勝つことが出来なかった。肩を抱きながらふと、階段の窓を見ると、畑で祖父が元気に農作業をしているのが見え、少し唖然とした。後に祖母から聞いた話では、朝4時におきて半には仕事を始めていたという。
医者の200歳まで生きるというのはあながち冗談ではないのではないかと俺は思う。
階段から降りると、テーブルの上には俺の分の食事しかなく、その隣には祖母が座っていた。
家族はもう済ませてしまったのだろう。
超が付くほどの早起きの祖父のせいで、我が家の朝は早い。
朝食を作らなければならない母も早起きしなければならないわけで、嫁いできた当時はかなり辛かったと聞く。しかし、人間の適応能力というものは凄まじく、今は苦も無く、下手すれば祖父より早く起きるほどだ。
が、どうも俺は早起きと縁が無いらしく、いまだに朝早く起きることができない。
最初は祖父に6時には起きろとガミガミ言われていたが、3ヶ月くらいで言うのも疲れたらしく、とうとう諦めた。おかげで寝るのが比較的早めなのも幸いして、平均睡眠時間は十時間弱、クマとは無縁の生活をしている。
椅子に座って食事を始めると、祖母は微笑みながら俺を見ていた。
しばらくは見ているだけだったが、しばらくすると静かに話しかけてきた。
「あんなに小さかったアルも、独り立ちする日になってしまったんだねェ・・・。寂しくなるよ、この家も。」
俺はいったん手を止めて、祖母の方へ向いた。
「そんな、一人減るだけじゃないか・・・。心配しないでよ。手紙も書くし、落ち着いたら顔見せに来るから。」
「そうかい。・・・気をつけるんだよ。」
一言そういうと、また静かに俺を見ている。見守ってくれる。其処に居るだけで空気が和み、安心する。祖母は、そういう人だ。
食事を食べ終わると、俺は食器を流し台へ持って行き、ささっと洗ってしまった。
「それじゃぁ、そろそろ準備してくるよ。」
そう祖母に告げて、俺は階段を上がっていった。窓の外では、まだ畑を耕す祖父が見える。
バックパックに必要な物を詰め終えた後には、家具以外、ほとんど何も無くなった。
地図、服、買った向こうの家の権利書、コンパス、食料、写真。何もなくなった部屋は自分の部屋では無いような味気なく感じてしまい、なんとなく切なかった。毎日見てきた天井と、部屋のにおいだけは変わらず俺の部屋だと言うことを証明していた。
玄関を出て、庭に出ると、庭のベンチに祖父が座っていた。俺が近づくと、足元においてあった長い2本の棒状のものを投げてくる。
「俺が使っていたものだ。このあいだ村の鍛冶屋に鍛えなおしてもらった。やるから、持ってけ。」
唐突で慌てる俺を尻目に、足元へ落ちる2本。
一本は大鎌、もう一本は長槍だった。このあたりの田舎では剣術など武術などがあまり盛んではなかった。
そのため剣や槍よりも、農業で使う鎌が発展し、大鎌や手鎌の武術が発展したのだと言う。長槍は、がぁらに居た時に買ったそうだ。
「ありがと。大切に使うよ。」
そういって拾い上げたとき、ふと疑問が浮かんだ。
「あのさ、これ、入れ物とかねぇの?」
「そんなもん、そのまま担いで行けばいいだろ。」
「あの、その鍛冶屋に頼んで、せめて刃を被うような物だけでも・・・。」
「あいつにそんな器用な真似ができるか。」
一蹴された。
こんな物騒な物2つも持って歩いていたら、どんな目で見られるかは火を見るよりも明らかだ。しかし、こんなものが入る入れ物はあるはずが無く、成すすべなく呆然と立ち尽くすだけだった。
最後に遂に家の門を出る時には、両親祖父母が並んで見送ってくれた。
母は案の定泣いており、父は少し心配そうだったが、すぐ大丈夫だろうと言う顔をして、「頑張れよ」と言ってくれた。祖母はいつもどおりどこか落ち着く微笑を浮かべ。祖父はと言うと、意外にも涙目になっていた。門をくぐった後、もう一度だけ振り返り、後はもう、振り返らなかった。
結局どうすることも出来ず、槍と鎌はそのまま担いでいくことになった。村の中ならまだ良い。村のほとんどの人は顔見知りだし、祖父が冒険者だったことも知っている。
祖母が良く話しているから、俺が村を出ることも知っているだろう。
村の人は色々声をかけてくれたし、祖父の性格も知っているから、事情も理解してくれたようだった。
しかし、送りに来てくれた幼馴染や友人には、
「うわ!アル、お前危ない奴か?」
と、からかわれた。思えば友人達とからかいあったのはこれが最後だったかもしれない。
後に、家族との手紙で、彼らも変わりなく暮らしていると知った。
村を出る前に、会っておきたい人が居たけれど、家には居なかったし、村の中を歩いてみても見つからなかった。会えるまで出発を延ばそうかとも思ったけれど、船に乗ることもある。仕方なく俺は、村を発った。
問題は村の外だ。こんな田舎では、明らかにこんな物騒な物を持って歩いたら、明らかに危ない奴だと思われる。仕方なく、槍は先の部分を布で巻いて隠し、鎌は幸い刃が取り外せたので、何重にも布を巻いてバックパックに括り付けた。今日滞在する予定の村は幾分か大きい村だったので、武具屋、もしくは鞄屋でカバーを作ってもらうことにした。
滞在した村に鍛冶屋があったので、刃の保護ケースを作ってもらった。
その後何日かかけて定期船を乗り継いで、やっとのことでがぁらへの定期船が出ている街まで辿り着いた。
最後に通った村からこの街までの距離がやたら長く、結局野宿しなければならなくなってしまった。
野宿で一泊し、次の日の正午近くに、この街へと辿り着いた。街に着くとまず、定期船の出発時間の確認と乗船の手続きを済ませてしまおうと、発着所へ向かう。
確認してみると、次の出発は明日の午前中だった。今日はここで一泊しなければならない。
とりあえず宿を、と考えたそのときだった。
あの日の風邪が完治していなかったらしい。急に寒気を感じ、くしゃみを一つ。そのせいで、手の力が緩み、2本の棒がするりと滑り抜けた。
「ぅわ痛てッ!」
その直後、大きな声が耳を劈いた。
前に居た人の膝裏の辺りに2本が思いっきりぶつかってしまったようだ。
軽めとはいうものの、質量、長さの有る2本の棒が膝裏にぶつかったら、結構な痛みだろう。
「うわった、悪い、大丈夫か?」
振り返った男は、銀色で綺麗に伸びた長髪。
少し潤んでる瞳は藍色。
「ったく・・・気をつけてくれよな・・・。」
軽く首を唸りながら去っていた男。
その男こそ、ソレスト=シルファリオスだった。
街へ戻った俺は、宿に入った後、疲れでそのまま寝てしまった。次に目を覚ました時には、もうかなり日は暮れていた。取った宿は食事が付いていなかったので、食事のついでに必要な物を買いに出かけた。外に出ると、昼とは打って変わって冷たい風が西へ向かって走り抜けていった。
夕食はラザニアとキール。久々に食った保存食以外の飯に軽く感動を覚えつつも、勘定を払って店を出ると、相変わらず風は肌に冷たかった。少し街を見て歩こうかと思い、歩を進める。
しばらくすると、一つの少し汚れたテントが見えた。街中でテントと言うのも珍しいものだ、と思いながら見ていると、入り口が開いて、人影が現れる。昼間に有った男だと気付くと、あ、と思わず声が出る。昼のことを咎められるかと思った俺は、少しギョッとしたが、向こうは昼のことなど覚えてないように言った。
「俺の顔になんかついてるのか?それとも、何かようかい?」
ハッとして俺は返事を返した。
「あ、……ああ、街中にテントなんて珍しいな、と思ってさ。宿屋とか、泊まらないのか?」
少しおどおどした様子で俺は尋ねた。
「俺は放浪者だからねぇ…。金は出来るだけ倹約したいしな。」
そういうと、俺と反対方向へ行ってしまった。しばらくシルファリオスの背中を見ていた後、街で買い物をして宿に戻った。
次の日の朝、宿屋のチェックアウトを済ませると、まっすぐに俺は港へ向かった。出航まではまだ時間があったが、俺は余裕を持って到着しないと落ち着かない癖があるので、早めに手続きをして港で本を読んでいた。
出航が近くなった頃、俺は一番乗りで船に乗り込んだ。ガキくさいと言われても反論できないが、俺はなぜか一番にこだわる事がたびたびある。まぁ、向上心が強いとでもしておこう。
そんな時、船の中でまたあの男に会った。
「・・・よぅ、よく会うな。」
「ああ。なにかの縁かねぇ。」
シルファリオスは隣に座り、しばらく俺たちは話をした。生い立ち、職業、なんかを暇つぶし程度に教えあったりした。
「・・・なぁ、アンタは何故がぁらに行こうとしてるんだい?」
何気なく、俺はシルファリオスに聞いた。
「特に、理由なんかねぇよ。…俺は放浪者だからな。」
己は、祖父が居た場所を見たくてがぁらを目指した。
…しかしこの男は、がぁらを目指しているわけでない。奴にとってがぁらは、俺ががぁらに向かうために通りすぎた街、その程度のものでしかないのだ。
なんとなく、そんな無限大にも思えるような生き方に憧れを抱き、シルファリオスと言う男になんとなくを好意感じた。
「………そうか。それじゃあ、向こうでも会うことがあるかも知れねぇし、そのときはよろしくな。」
結局俺たちはがぁらに着くまで、ほとんど行動を共にした。
祖父が過ごした世界。これから起こる出来事。未知なる景色。次第に近づいてくる地平線に、俺の胸は湧き返る。
共に過ごし、共に歩み、別れ。ステアが頭の上に乗るのは、もう少し、後のお話。