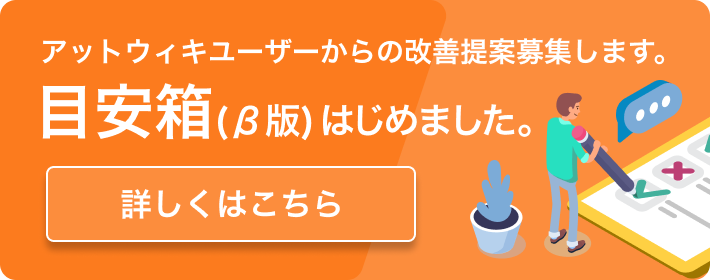新生人工言語論
グローバル社会の人工言語
最終更新:
lideldmiir
-
view
地球のグローバル化に伴い、それまでは殆ど西洋に封印されていた人工言語の概念は20世紀には世界各地に普及していた。日本にも20世紀にエスペラントは既に持ち込まれていた。世界3大宗教と人工言語の割合の分布の違いは明白である。アラブ圏にいけばイスラム教徒が多く、西欧ではキリスト教徒が多い。地域ごとに比率が異なる。しかし人工言語はそうでない。概ねどこへ行こうがエスペラントのシェアが最も高い。人工言語の割合はむしろコンピュータのOSに近い。ウィンドウズが大概最大のシェアを占めるように、エスペラントが群を抜いている。日本でもそれは同じで、エスペラントが最も多くのシェアを占める。書店で購入できる書籍を比べてみてもインターネットの日本語サイトの件数を比べてみても明らかである。
グローバル化に伴い西洋から人工言語が伝来し、日本では人工言語といえばエスペラントという公式が生まれるに至った。これは今日でも変わらないが、作成者の側では21世紀に入って大きな変化が訪れた。 20世紀末にパソコンが普及したことにより、ネットも徐々に普及していく。 21世紀にかけてネットの加入者は爆発的に増え、常時接続が普及し、大容量ブロードバンドが普及した。人工言語が最も社会に歓迎されたのは17世紀の普遍言語時代であるが、この時代でも人工言語で儲けたり飯を食うのは極めて難しかった。いわんや現代は英語が国際語として機能している。ネットによって世界は更に狭くなり、英語はデジタルを通して更に普及している。
この社会的背景でいま人工言語が持つ機能とは何であるか。暗号型は軍隊などが使う本格的なものとしては望めない。およそ人工言語を資料ひとつ残さず複数人に丸暗記させるのは不可能である。ただ、個人或いは団体がちょっとした秘密の書字として使う程度なら機能するだろう。また、排他的な共通の言語を使うことにより使用者間に連帯感が生まれることがあるため、符牒型の言語も機能するだろう。ゴドウィンの月世界のような演出型の人工言語も現代では小説や他のメディアの中に頻出している。トールキンの『指輪物語』に出てくるエルフ語や、『スタートレック』のクリンゴン語などがそうである。
今までの人工言語史とその成果を見ると、人工言語の機能としてこれからも生き残るのは「暗号型」「符牒型」「演出型」の3点であると考えられる。暗号と符牒は似たところがあるので、要するに大きくまとめれば「秘密の言語」と「空想の言語」の2点である。
尚、普及型はこの4世紀の間もっぱら扱われてきたものだったが、普遍言語ないし国際語として普及したものはいまのところ無い。最も有望視されるのはエスペラントである。しかし、ネットや交通によって英語が世界中に浸透していく中、乗り遅れずシェアを維持或いは増やすには、地道な普及運動と利用者にとって有益と思われる情報を発信するより他はない。
さて、現代のネット社会は作成者が言語を作成する段階にも影響を与えた。ザメンホフがそうであったように、今までは人工言語を発表するにはしばしば多額の費用をかけて自費出版するしかなかった。人工言語は上述のように金には変わらないためである。その経済的敷居の高さゆえ、人工言語を作ることはできても発表することはままならなかった。発表がままならず、他の人工言語についての書籍も手に入りにくい時代では容易に人工言語を作ることはできない。手に入る資料がエスペラントばかりであればこの改良品を作ることが念頭に浮かび、別の型を作る契機にはなかなかならない。
しかしその敷居をネットが急落させた。人工言語をネット接続費用程度の小額で発表できるようになった。人工言語がネットで公開されればそれは他の作成者の資料になるため、他の作成者にとって更に人工言語作成の敷居は下がる。こうして人工言語の作成については17世紀の普遍言語時代と同じくらい爆発的に増えることとなった。
だが容易に発表できるということは18世紀のように前時代の焼き増しを行った粗い言語の出現も意味する。自費出版という大きな自腹を切る場合、原稿の隅々まで考察して見直してから出版するだろう。しかし気軽に行えるネット言語の場合そうとはかぎらない。精度を高め、多額の出費も厭わない言語が自費出版を踏み切る。だが今はその必要性もないのでいわば考察の甘い覚悟の弱い言語が頻出することになる。 18世紀に見られたような焼き増し現象が将に21世紀に返り咲いている。言語や語学が好きという好事家が容易に言語を作成し発表できるというのは一長一短である。
人工言語の今後についてだが、公開が容易であることと作成のための資料が集めやすくなったことから、ネット言語の氾濫が予想される。それは玉石混交で、精度の高いものもあれば即興的なものもある。
言語を作る行為は大変なもので、言語学や語学に留まらず、ウィルキンズの計画のように博学的知識まで必要とする。更に今まで見てきたように、人工言語は当時の科学力を反映している。これからの人工言語は2次曲線を描いて昇華した20世紀の科学を反映する。既にウィルキンズの時代で人が一生かけても作りきれないほど多かった分類や概念を、どう新概念の増えた現代人が行うというのか。現代の学術用語が利用しているラテン語を機械的に写し取る方法を取らない限り語彙を作りきることはできない(厳密には語彙は開かれた体系なので終わりはない)。
尤も科学技術の単語は必要になった際に作ればよいわけだから語彙の問題は置くことができる。しかしそれでも言語を作ることは容易いことではない。玉石の石のほうは恐らく作者がすぐに飽きて捨て去ってしまうだろう。また人工言語が乱立する中で学習者は殆ど見込めないだろう。結局多くの言語が公開から数年も経たぬうちに消えるか更新されない亡霊として残るだろう。そしてその間にもまた新しいものができるという連鎖を繰り返すだろう。
普及型の言語すなわち国際語や国際補助語は歴史も現状も顧みず無謀にも作られるであろう。だが普及は成功せず、学習者も極めて少ないというのが考えられる実情である。小数の協力者との限られたコミュニティの中でその国際語は存在し、暫くもすれば自然と符牒型やコミュニティの暗号型に変わっていくことだろう。
また、ネット言語が乱立すればそれをまとめたリンク集やポータルサイトが出現するし、自言語の紹介ではなく人工言語そのものを論じたものも現われるだろう。これは中世・近世において紙で行われていたことをデジタルにしただけのものであるから発想としては斬新ではない。ただ、ポータルサイトの類は紙よりネットのリンクのほうが遥かに便利であるため、その有効性はかつてのものより高いと考えられる。
自然言語の総数が減少の一途を辿るのに人工言語が増加の一途を辿るというのは興味深い視点である。ただ、増えていく人工言語が自己のレーゾンデートルを持たぬ限り、
そして、そのレーゾンデートルが上記3点の人工言語の有効な機能に当てはまらないかぎり、その灯火は短いものだと思われる。