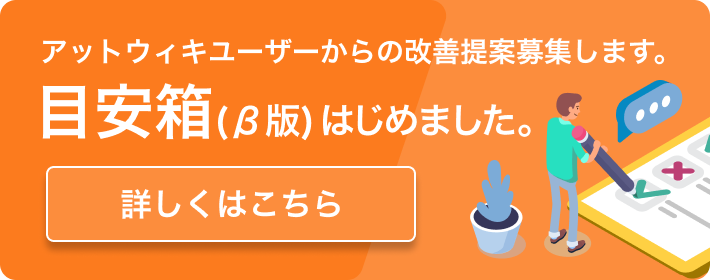dunpoo @Wiki
◎歴史の本棚
最終更新:
dunpoo
-
view
原始の神社をもとめて [著]岡谷公二 [朝日]
[掲載]2009年10月11日
巨岩や山を神体とし樹木に囲まれた聖なる空間には、不可視なものを重んじ人工物を忌避する心性がみられる。異なる歴史的経緯をたどったものの神社の祖形と通じる場として、沖縄の御嶽(うたき)、韓国・済州島の堂(タン)を訪ねて、日本の信仰の原点を探る。
巨岩や山を神体とし樹木に囲まれた聖なる空間には、不可視なものを重んじ人工物を忌避する心性がみられる。異なる歴史的経緯をたどったものの神社の祖形と通じる場として、沖縄の御嶽(うたき)、韓国・済州島の堂(タン)を訪ねて、日本の信仰の原点を探る。
シベリア抑留 [著]栗原俊雄 [朝日]
[掲載]2009年10月11日
酷寒中での重労働や飢え、収容所内での旧軍秩序への反発から始まった「民主化運動」のもたらした反目、帰国後に直面した世間の冷たい反応。国策により渡った満州で身柄を拘束された人たちへの補償はいまだなされない。膨大な手記が発表されたにもかかわらず、歴史的意味の解明も終わらない悲劇の全体像に迫る。
酷寒中での重労働や飢え、収容所内での旧軍秩序への反発から始まった「民主化運動」のもたらした反目、帰国後に直面した世間の冷たい反応。国策により渡った満州で身柄を拘束された人たちへの補償はいまだなされない。膨大な手記が発表されたにもかかわらず、歴史的意味の解明も終わらない悲劇の全体像に迫る。
1968 (上・下) [著]小熊英二 [朝日]
[掲載]2009年10月4日
[評者]天児慧(早稲田大学教授・現代アジア論)
全国の大学を席巻した学生の叛乱(はんらん)は何だったのか、そして何を残したのか。一世代下の著者があの叛乱を真剣に問うている。そしてそれを一過性の現象ではなく総体として描こうと全力で取り組んでいる。評者は団塊世代で原点は1968年にある。しかしこれまでほとんどそれを語らなかった、語れなかった。理由の一つは、閉じた目に浮かぶ全共闘運動の“原風景”と、成田三里塚、新宿騒乱、安田講堂、よど号ハイジャック、連合赤軍などと続くメディアによって象徴化されていく事件、いわゆる「全共闘運動」との違和感が大きく、またそれをよしとする「全共闘ナルシスト」への不快感があったからである。
[評者]天児慧(早稲田大学教授・現代アジア論)
全国の大学を席巻した学生の叛乱(はんらん)は何だったのか、そして何を残したのか。一世代下の著者があの叛乱を真剣に問うている。そしてそれを一過性の現象ではなく総体として描こうと全力で取り組んでいる。評者は団塊世代で原点は1968年にある。しかしこれまでほとんどそれを語らなかった、語れなかった。理由の一つは、閉じた目に浮かぶ全共闘運動の“原風景”と、成田三里塚、新宿騒乱、安田講堂、よど号ハイジャック、連合赤軍などと続くメディアによって象徴化されていく事件、いわゆる「全共闘運動」との違和感が大きく、またそれをよしとする「全共闘ナルシスト」への不快感があったからである。
しかし「語れない」もう一つの理由は、本書でも触れているが、あの運動は言葉も思想も行動もほとんど中途半端であり、結局はばらばらに私化し内面化してしまったからである。告発していたはずの社会に少なくとも表面的には無抵抗に埋没してしまった。ある番組で田原総一朗が「団塊世代の無責任さがその後の日本をダメにしたんだ!」と批判していた。それは多分「運動の中途半端さ」にかかわってくる。上と下の世代から挟まれ、われわれは、“あの時代”にもう一度向き合わざるを得ない。
本書は、膨大な資料を収集し、戦後の左翼運動史から早慶、日大、東大など各大学闘争、高校闘争、ベ平連、リブなどほぼすべての運動を丹念に再現し、同時に様々な活動家たちの内面に入り込んでいる。評者の原風景の中心には、一般学生、教師も含めた人々の、それ以前も、以後にも経験しなかった自己、大学、社会を根元から問う異様な熱気があった。著者風にいえば「加害者であり被害者である自己」のもがき、生のリアリティーを欠く「現代的不幸」を背負う若者の異議申し立てがあった。上巻の表紙の写真は評者と同じ大学の後輩ノンポリ学生。あどけなさを残す「ヘルメットの女の子」の参加が叛乱のある側面を象徴している。著者は、戦後民主主義に育てられ、その欺瞞(ぎまん)に憤り、高度成長が生み出す物質的な欲望充足に奔走する「大人社会」への反感、あるいは発展途上国としての幼少期と先進国としての青年期を生きた団塊世代のギャップこそが叛乱の「原動力」だと指摘する。
しかし全共闘運動がなぜ党派を超え巨大なうねりになったのか。そこにはある種の「感性の共有」があった。評者も含め多くの無党派、一般学生は党派にかかわることを躊躇(ためら)った。しかし『青春の墓標』で自殺に至るまでの闘いと人間としての苦悩を綴(つづ)った活動家・奥浩平や羽田闘争で轢死(れきし)した京大生・山崎博昭の生きざまは多くの共感を引き起こしたと著者は語る。悲惨な「死」の選択を余儀なくされた活動家の数は少なくない。だが結局「死」を選択しなかった者は、「沈黙」を選択せざるをえない。時代の流れに合わせ「沈黙」を続けることは、感性の摩耗と背中合わせになる。摩耗してもしなくても、中途半端な生きざまに映る。その意味で田原の批判は当たっている。
あれから40年が過ぎた。あの運動が何を生みだしたのか。著者はその後、団塊世代が「大衆消費文化の作り手として活躍している」ことに触れている。しかし全体としてどう見たらいいのか。本書では最後に、「私には何もないの」という序文の少女の言葉に戻っているが、今日ようやく見え始めてきた部分もある。あの時、大学を捨て今なお借金に追われながら有機による「興農」を続けている人たちがいる。安田講堂、早大学館に立てこもり数々の逮捕歴を持つ親友は、地方の精神科病院に勤め医療事務の改革に後の歳月を費やした。ある仲間は人間をはぐくむ教育を求め私塾を続けている。「アジア」にこだわってきた評者の源もまたあの日々にある。農業、医療、教育、アジアなど今日、成長主義、欧米主義のパラダイム転換が真剣に問われている。別の視点から見直すなら“1968年”はある意味でその「転換の原点」になるのかもしれない。著者の「時代をつかむ感性」に敬服しながら、改めてそう思ったのは評者の読み過ぎだろうか。
◇
おぐま・えいじ 62年生まれ。慶応大学教員。著書に『インド日記』『〈民主〉と〈愛国〉』『〈癒し〉のナショナリズム』『市民と武装』『日本という国』、共編書に『在日一世の記憶』など。
吉本隆明の時代 [著]すが秀実 [朝日]
[掲載]2009年3月1日
[評者]柄谷行人(評論家)
本書は「吉本隆明論」というよりも、その「時代」、特に1960年の前後10年ほどの時期を扱った歴史書というべきものである。なぜそれが吉本論として語られるのか。この時代が、吉本隆明という批評家がヘゲモニーを確立していった時期だからである。
[評者]柄谷行人(評論家)
本書は「吉本隆明論」というよりも、その「時代」、特に1960年の前後10年ほどの時期を扱った歴史書というべきものである。なぜそれが吉本論として語られるのか。この時代が、吉本隆明という批評家がヘゲモニーを確立していった時期だからである。
それ以前には、さまざまなタイプの知識人がいて、吉本はその中の一人にすぎなかった。そのような知識人らがそれぞれの課題と動機をもって一堂に会したのが、1960年安保闘争という舞台であった。しかし、この過程で、吉本は他の者を残らず駆逐してしまった。それ以前と以後では思想の風景が一変してしまったのである。なぜこんなことがありえたのか。
この問題に関して、著者は二つの参照例をもってきた。一つは、安保闘争をフランスのドレフュス事件との類推で見ることである。そこから、その頃の日本になぜ自由浮動的な「革命的」知識人が出現したのかを照明する。もう一つは吉本隆明を、戦後フランスの知的世界に君臨した哲学者サルトルとの類推で見ることである。なぜサルトルは知識人として別格の地位を得たのか。その理由の一つは、彼が小説家であり、けっして大学の教授にならなかったことだ。つまり、彼は「呪われた詩人」という系譜に属していたのである。
吉本隆明も同様であった。彼はむしろ、「呪われた」負の部分を栄光へと逆転することによって、勝利したのである。しかし、著者は吉本隆明の「勝利」にも、勝者によって作られた歴史にも関心をもっていない。実際、吉本が勝者であるとはいえない。彼に覇権を与えた高度資本主義経済が、彼自身を呑(の)みこんでしまったからだ。それを対象化するには、吉本が消去してしまった諸視点が必要である。
著者はその鍵を、吉本隆明の罵倒(ばとう)の下に消されていった敗者(花田清輝・武井昭夫・丸山真男など)に見いだそうとしている。これらの考察は新鮮で啓発的である。本書は“1960年”だけでなく、戦後日本史に関する通念を根本的に変える、スリリングな歴史書である。