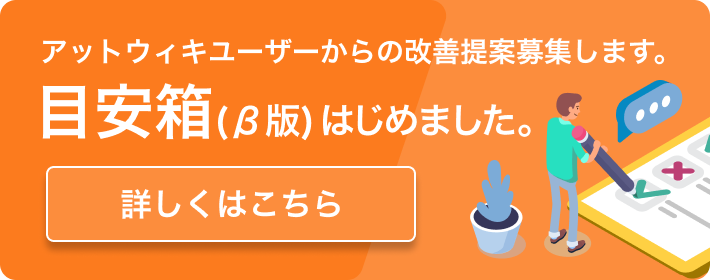dunpoo @Wiki
◎市民の政策局の本棚
最終更新:
dunpoo
-
view
格差・秩序不安と教育 [著]広田照幸 [朝日]
[掲載]2009年10月11日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大副学長・教育社会学)
1990年代以降、教育政策が迷走を繰り返して日本的教育システムが崩れたことに多くの人々は気づいている。けれども、変化の断片をつなぎあわせて変化の底流を明快に描いた著作は少ない。20編以上の硬軟多様な論考からなる本書は、この大主題に一貫して取り組んだ力作である。分析対象は現代だが、教育の歴史社会学を本業とする著者の歴史眼を随所に感じる。
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大副学長・教育社会学)
1990年代以降、教育政策が迷走を繰り返して日本的教育システムが崩れたことに多くの人々は気づいている。けれども、変化の断片をつなぎあわせて変化の底流を明快に描いた著作は少ない。20編以上の硬軟多様な論考からなる本書は、この大主題に一貫して取り組んだ力作である。分析対象は現代だが、教育の歴史社会学を本業とする著者の歴史眼を随所に感じる。
70年代までの保守対革新という二極対立時代以後、教育政治は複雑化して非常にわかりにくくなった。それを著者は三極対立図式を軸にわかりやすく説明する。三極モデルを構成するのは、(1)規制による質保障を志向し日本型教育モデルを維持しようとする族議員・文科省(2)市場原理による質保障を志向した新自由主義的改革派(3)現場の自律性を重視する政治的リベラル・社民勢力の三者。90年代には新自由主義的な改革論者が、保守グループを押しのけヘゲモニー(覇権)を握る。文科省はいろいろな部分で負け、規制改革グループが主張する競争と評価などを重視する改革案が実行に移された。そしていま、「小さな政府」路線による行財政改革に大転換が生じ、新自由主義者は政治の主舞台から退場しつつある。
教育はどこへ行くのか。新政権にマニフェストは存在するけれども、目指すべき社会像を伴った将来ビジョンが明確なわけではない。根拠なき新自由主義が歴史の必然ではなく選択の結果であったとすれば、私たちは別の未来の可能性を構想することができるはずだと著者は説く。そのとき、不透明な未来社会においてきちんとした政治的判断を下せる市民を育てていくところに教育と教育学の使命があると著者は主張する。
50年代以降教育学の主流研究者たちは野党的な政治的ポジションに隔離されてきた。それは、制度構築や政策提言につながるような、実証的分析能力を教育学が持つことを妨げた。こう分析する本書は、教育学自省の、そして希望の書でもある。政権交代は、著者の表舞台での出番を増やすだろう。オピニオンリーダーの登場である。
◇
ひろた・てるゆき 59年生まれ。日本大学教授。『陸軍将校の教育社会史』など。
学力と階層―教育の綻(ほころ)びをどう修正するか [著]苅谷剛彦[掲載]2009年2月8日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)

学力低下論が席巻していた01年、著者は『階層化日本と教育危機』を出版して衝撃を与えた。「だれの学力が低下しているのか」を実証的に明らかにし、社会の階層化と不平等化という文脈に教育を位置づける挑戦だった。学力低下から教育格差へ。その後人々の教育問題へのまなざしに生じた変化は、著者によって問題がとらえ直され、再定義された結果だといっても過言ではない。

学力低下論が席巻していた01年、著者は『階層化日本と教育危機』を出版して衝撃を与えた。「だれの学力が低下しているのか」を実証的に明らかにし、社会の階層化と不平等化という文脈に教育を位置づける挑戦だった。学力低下から教育格差へ。その後人々の教育問題へのまなざしに生じた変化は、著者によって問題がとらえ直され、再定義された結果だといっても過言ではない。
この本は前著の続編であり、主に03年以降に著者が折々の教育問題を分析した論考を集めたものである。タイトルは『学力と階層』だが、狭い意味での学力格差が主題ではない。いまや獲得された知識のストック(学力)ではなく、知識獲得のためのスキルや学習能力が重視される「学習資本主義社会」の時代が到来した。著者の関心は、学習意欲や態度を含む「学習資本」の階層間格差にあり、その形成にかかわる教育費の配分や教員の勤務実態にまでスコープは広がる。
著者の分析は看過することのできない知見を次々に明らかにしていく。出身階層によって子どもの努力(学習時間)には差があり、しかもその差は近年拡大している。もはや努力主義(「がんばれば誰でも……」)は結果の平等をもたらすことのないイデオロギーに過ぎない。自己責任が強調され、個人の失敗が努力の欠如によって説明されるようになれば、階層間格差を隠蔽(いんぺい)することになる。
義務教育費国庫負担制度の変更にも容赦なく批判を浴びせる。この制度は結局、国の負担率を2分の1から3分の1へと引き下げてその分を地方に回すことで政治的決着を見た。少子化によって地方の財政負担は将来減少するという「常識」が国の負担率を減ずる有力な根拠だったが、著者の分析は正反対の結果を示す。子どもの数は減っても教育費は減らないどころか、教師の大量退職などにより増える。しかも財政力の弱い地方ほど多額の教育費を要する。どの地域でも義務教育の条件は変わらないというスタートラインの平等は崩れ、教育機会の不均等化が進むことになる。
出版社:朝日新聞出版 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902100138.html
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902100138.html
失われた場を探して [著]メアリー・C・ブリントン[掲載]2009年2月22日
[評者]苅部直(東京大学教授・日本政治思想史)
日本でバブル経済が崩壊した、1990年代に学校教育をおえた世代が、なかなか正規雇用の職にありつけない。この、いわゆるロストジェネレーション問題は、外からはどう見えるのだろうか。
日本でバブル経済が崩壊した、1990年代に学校教育をおえた世代が、なかなか正規雇用の職にありつけない。この、いわゆるロストジェネレーション問題は、外からはどう見えるのだろうか。
アメリカの社会学者が、丹念な調査を行ってまとめた本である。そこから浮かびあがるのは、むしろ、高度成長期から80年代までの日本社会を支えていた、特殊なしくみにほかならない。
学校という「場」から、会社という「場」へ。年齢に応じて「場」の間を、順序どおりに移動するのが人生の標準型とされる。高校での就職斡旋(あっせん)や企業の終身雇用といった制度が、その「あたりまえ」さを保証していた。
しかし90年代には、産業の中心が製造業からサービス業や小売・卸売業へと移り、他方で高卒者の正規社員としての採用が減った。その結果、学力水準の高くない高校を出た若者が、会社の「場」に安住する道は狭まってしまう。ニートやフリーターの増加の原因を、本書はここに見る。
この変化をうけとめ、若者が、学校に必ずしも頼らず、自分で職を選ぶための感覚を磨くこと。そして周りの社会がそれを助けること。「場」の喪失がもたらした不透明さを語りながら、そこに新たな希望を、著者は見いだそうとする。
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,995
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902240078.html
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,995
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902240078.html
社会的排除―参加の欠如・不確かな帰属 [著]岩田正美[掲載]2009年3月8日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
グローバリゼーションと脱工業化という新しい経済社会状況に移行する中で、古い福祉国家の諸制度が対応できない新しい社会問題が登場してきた。「社会的排除」概念の価値は、セーフティーネットからこぼれ落ちてしまう人々が出現する過程を説明し、問題を解決する方策を「社会的包摂」として明らかにしようとするところにある。
グローバリゼーションと脱工業化という新しい経済社会状況に移行する中で、古い福祉国家の諸制度が対応できない新しい社会問題が登場してきた。「社会的排除」概念の価値は、セーフティーネットからこぼれ落ちてしまう人々が出現する過程を説明し、問題を解決する方策を「社会的包摂」として明らかにしようとするところにある。
フランス生まれのこの言葉は、いまやEU加盟国における社会政策上のキーコンセプトに育ったが、その意味は単純ではない。著者は、この概念の特徴をたくみに整理した上で、路上ホームレスとネットカフェホームレスを例に、日本社会のリアリティーに切り込む“社会的排除”の力を示してみせる。日本ではまだ実証的研究は多いとはいえないが、ホームレス以外にも障害者、女性、外国人移住者、いじめや虐待など、多様な社会問題の考察が可能である。
ホームレスの事例研究は日本での社会的排除の形成に二つの形があることを教える。ひとつは、いったんは社会のメーンストリームに組み込まれた人々が、そこから一気に引きはがされるタイプ。失業、離婚と借金、病気など多様な要因が複合的に絡んで、一気に定点を奪う。ふたつめは、メーンストリームに組み込まれたことはなく、途切れ途切れの不安定就労のように、そもそも社会への参加が「中途半端な接合」に過ぎなかったタイプ。いずれも、20世紀日本で作られた社会保険や生活保護制度の網から漏れてしまっている。
いまや海外では、社会的排除概念を使った社会問題の分析が、20世紀型福祉国家の所得保障システムから飛び出て、新しい福祉政策を生み始めているという。グローバリゼーションの中で日本だけが何もしないで社会の亀裂を回避できる保証はどこにもない。社会はその内部から社会に参加できない人々を作り出している。
社会的包摂をめぐる議論の行き着く先は必ずしも鮮明ではない。しかし社会的排除概念の有効性を主張する本書のメッセージは、コンパクトで平明ながら力強い。
出版社:有斐閣 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200903100136.html
出版社:有斐閣 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200903100136.html
アンデルセン、福祉を語る [著]G・エスピン-アンデルセン[掲載]2009年2月15日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
本書は、福祉国家に関する比較研究の第一人者が、フランスの一般読者向けに書いた書物の翻訳である。そう記すと既知の話題の再論かと想像してしまうが、本書の議論は以下のような刺激的な問題提起を多く含んでいる。
本書は、福祉国家に関する比較研究の第一人者が、フランスの一般読者向けに書いた書物の翻訳である。そう記すと既知の話題の再論かと想像してしまうが、本書の議論は以下のような刺激的な問題提起を多く含んでいる。
第一に親から子どもへの「社会的相続」というテーマ。子どもの認知能力の基盤は小学校に入る前の段階でかなり決定されることが近年の研究で明らかになっており、それには経済的要因にも増して家庭環境の「文化」的要素(たとえば家にある本の冊数)が大きいという。こうした点から保育施設の質的充実など、北欧に代表される早い時期からの公的対応が、子どもにとっての「文化資本」の不平等を是正し、かつ社会全体の生産性を高める投資としても有効と著者は論じる。
第二に「死は民主的でない」という指摘。たとえばフランスでは男性の管理職は工場労働者よりも5年以上長生きするので、結果として高所得層が年金や医療、介護などの給付のより大きな受給者となる。つまり「平等」のための制度がかえって格差を増幅させているわけで、著者は代案として平均寿命に応じた累進課税などを提起する。
第三に「効率性」と「平等」の関係についての掘り下げ。たとえばデンマークの公的社会保障支出はアメリカのそれよりずっと大きいが、保育や医療に関する私的な支出も含めると両者の違いはほとんどなくなる。ならば市場より政府による対応のほうが、平等のみならず効率性の観点からもすぐれているのではないか。これら以外にも、現在の福祉国家に関する鋭角的な指摘が随所にあふれていて興味深い。
一方、“投資としての社会保障”という視点の重要性を確認したうえでなお、著者の議論の持つある種の「生産主義」的な傾向には疑問も残る。現在の先進諸国における慢性的失業の背景には構造的な生産過剰があり、雇用拡大という方向には限界があるのではないか。労働時間削減やワークシェア、賃労働の相対化といったテーマに関する著者の議論も聞きたいと思う。
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902170092.html
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200902170092.html