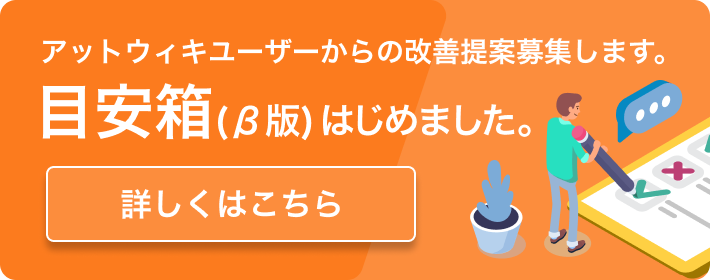「◎生き方・考え方の本棚」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「◎生き方・考え方の本棚」(2012/03/03 (土) 12:24:51) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[◎生き方・考え方の本棚09Ⅱ]] へ
[[◎生き方・考え方の本棚10]] へ
#contents
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*竹内薫『竹内流の「書く・話す」知的アウトプット術』(2009.5 実務教育出版)[談風子]
竹内はサイエンス・ライターで100册もの著作があるというが、科学モノを読まない僕は知らなかった。(ただし最近話題になった『99.9%は仮説』という書名は知っている。)いけてない書名だし、サブタイトルに「プロフェッショナルは、こうやっている!」とあるのもなんか読む方が気恥ずかしいが、この本に惹かれたのは、タイトルに「話す」というのも入っているからだ。僕は、これから書く方だけでなく、講演や放送でも仕事が来るようにしたいと思っているだけに、「書く」と「話す」についてプロが伝授してくれるなら、と手にとった次第。
で、役に立ったかというと、「話す」に関しては、全く失望。「笑いをとれ」とか「つかみが大事」とか「客の反応を見よ」とか「リハーサルが大事」とか、当たり前で抽象的なアドバイスばかりで、あげくは「大事なのは、表面的な出来不出来より、しゃべる中身」ときたもんだ。
「書く」方に関してもたいした方法論はないが、筆一本で立つのは、かなりたいへん、二足のわらじが無難、という教えはありがたく拝聴した。「奥さんが許してくれたときが作家としての自立の時期だ」という鈴木光司の言葉は胸にしみる。
そのほか、ものを調べる具体的な方法でいくつか参考になることがあった。漢和辞典は大修館の「現代漢和辞典」がアイウエオ順で引けていいとか、英和辞典は「リーダーズ英和」だとか。英語のwikipediaはかなり使える、とか。あと、英会話は、廉価なCD教材を半年間繰り返し全部暗誦してしまえば一丁上がりだとか。これは早速実践してみよう。
(お勧め度 ★★)
#amazon(4788907593)
*日本浄土 [著]藤原新也
[掲載]2008年10月5日
[評者]久田恵(ノンフィクション作家)
■多くの生死を見つめ、なお旅の途上
70年代に若者だった世代にとって、第一作『インド放浪』を引っさげて登場してきた藤原新也は、衝撃だった。
熱に浮かされていた政治の季節が過ぎ去り、社会の管理化が推し進められようとしていた時代。どこにも行けない若者が、社会のあちこちで吹き溜(だ)まっていた。
その世代の一人だった私は、藤原新也の写真に釘(くぎ)付けになった。インドの聖地ベレナスの火葬の光景。夕日に染まった河を流れる遺体。その遺体を長い嘴(くちばし)で突く烏(からす)。
冒頭、著者は記していた。
「歩むごとに、ぼく自身と、ぼく自身の習って来た世界の虚偽が見えた」
彼はこの書によって多くの若者を旅に向かわせた。私はどこにも行けなかったけれど、ここではないどこかへ旅立たなければ、なにも分からないのだと思った。
80年代、『東京漂流』で、また衝撃を受けた。アジア13年の旅の後、著者は自分の目に映じた日本社会をしたたかに撃った。この本には、某誌連載を降板することになった写真が収められていた。インド放浪の折に撮られた野犬が屍(しかばね)を食らう写真だ。
「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」
添えられたコピーに社会が震撼(しんかん)した。
藤原新也は凄(すご)すぎた。唯一無比のアナーキーな社会派。尊敬を通りこし、畏敬(いけい)の念を抱かせた。
それから、25年。
本著、『日本浄土』に私は3度目の衝撃を受けた。気がついたら、遠くにいたはずの著者が傍らにいるではないか。
そして、美しいのである。文章も写真も。やさしくて深い味わいがある。
ここには、多くのものを見てきた人の静かなまなざしがある。頭の先で考えたことではなく、旅をしながら、生身の人々の生死を見つめてきた人の言葉がある。
世界を巡った長い放浪の果ての著者にとって、彼の人生でもっとも目立たない、思い出探しの島巡り、海巡りの旅だと言うこの本に、今、出会えて良かったな、と思う。
著者は、旅をしながら、「今日、佳景に出会うことは大海に針を拾うがごとくますます至難になりつつある」と語っている。
が、その一方で、歩行の速度の中では、「風景の中に息をひそめるように呼吸をしている微細な命が見え隠れする」とも言う。
事実、読者は、一葉のコスモスの写真を回路に、彼の放つ言葉の翼に乗って、記憶という行き着くことが果たせないほどの遠くまで旅立つことができるのだという思いに打たれるにちがいない。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200810070100.html
&amazon(4487802148)
*0601 ニッポンには対話がない [著]北川達夫・平田オリザ [朝日]
[掲載]2008年06月01日
15歳の国際基準学力世界一のフィンランドで教材を作る元外交官と、劇作家の大阪大教授が教育現場をふまえて対談した。フィンランドでは「心とか、考えというものは全員違うのがあたりまえ」。価値観の押しつけの危険性に、日本人は無防備だと指摘。自分の経験を絶対視しない、衝突後に妥協点を探るなど、意見の相違を恐れず対話を尽くすためのヒントがあふれている。多様化が進み、国際化・多文化化する社会では、「ダメなものはダメ」が、一番ダメなのだ。
出版社:三省堂 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200806030083.html
&amazon(4385363714)
*0504 調べる技術・書く技術 [著]野村進 [朝日]
[掲載]2008年05月04日
ノンフィクションを書くためのテーマ選び、資料集めに始まって実際の執筆まで、基本から助言する。事前にできるだけ調べる、人と会うときは絶対に遅刻しないなど、実は特別な近道はない。織り込まれた著者の体験が、参考になる。ノンフィクション取材にとどまらず、勉学や仕事にも役立ちそう。
調べる技術・書く技術 (講談社現代新書 1940) (講談社現代新書 1940)
著者:野村 進
出版社:講談社 価格:¥ 777
URL:http://book.asahi.com/paperback/TKY200805060113.html
&amazon(4062879409)
*0819 ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く [著]リサ・ランドール [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]渡辺政隆(サイエンスライター)
■現代宇宙物理学の最先端からの報告
最新の宇宙論に触れるたびに抱くのは、宇宙に果てはあるのか、広大無辺な宇宙における人間の存在とはいったい何なのかといった、考えれば考えるほど頭がぼうっとしてきそうな問いである。素人に納得できる解答が出されないまま、理論宇宙物理学の新しい学説が送り出されている。
今回の新機軸は、われわれはブレーンと呼ばれる膜のようなものの上で暮らしているのかもしれないと説く「ワープした余剰次元」理論。それと、その理論の提唱者にして本書の著者が、アインシュタインやホーキングといった、まさに異次元の住人を思わせる天才ではなく、才色兼備の物理学者という点。
では、その余剰次元とは何か。われわれが認識する世界は、縦・横・高さという3つの次元でできている。それに時間も入れた4次元の世界ならば、まあまあ常識で理解できる。しかし実際にはこれに、歪(ゆが)んだ(ワープした)第5の次元が存在するというのが余剰次元理論である。いや、こんな説明ではわからなくて当然。そもそも600ページにもおよぶ本書の内容を数行で要約できるはずがない。
本書の半分あまりはアインシュタインから超ひも理論までの理論物理学史のおさらいに当てられている。かつてニュートンは、自分が他よりも遠くを見通せたのは、巨人たち(偉大な先人たち)の肩の上に乗っていたからだと語ったという。研究が進み知識が増えつのるに伴い、先端科学を理解するための素養も増大する。踏み越えるべき巨人の数も増すというわけだ。おまけに次元数まで増えてしまった!
そこで本書の冒頭では高次の次元という考え方が、芸術家の遠近法になぞらえて説明されている。また、歴史のおさらいは、著者自らが提唱する最新理論が登場した必然性を踏まえている点で斬新である。新しい難解な理論が生み出される現場を垣間見られるエピソードも楽しい。難点があるとしたら、当事者が語る歴史特有の、細部へのこだわりだろうか。ともあれ、異次元宇宙にワープするには格好の1冊である。
◇
Warped Passages/向山信治監訳・塩原通緒訳/Lisa Randall 理論物理学者。米ハーバード大教授。
ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く
著者:リサ・ランドール
出版社:日本放送出版協会 価格:¥ 3,045
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210244.html
&amazon(4140812397)
*すべての終わりの始まり [著]キャロル・エムシュウィラー [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]巽孝之(慶應大学教授・アメリカ文学)
■心地よく常識ゆさぶる破壊の力
半世紀ものキャリアを誇るアメリカ女性作家キャロル・エムシュウィラーは、すでに生ける伝説である。ジェイン・オースティンとともにフランツ・カフカを愛する彼女は、長短編問わず多数の傑作を書き継ぎ、ネビュラ賞やディック賞、世界幻想文学大賞など華麗な受賞歴を重ねてきた。必ずしも大向こう受けしそうもないその作風を称賛したのは、フェミニズムとSFの双方の視点より「他者(エイリアン)」の意義を知り尽くした、『ゲド戦記』で著名なアーシュラ・K・ル=グウィンや、その好敵手たる男装作家ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアといった猛者たちだった。
日本独自の編集になる本書が揃(そろ)えた19の短編も、雰囲気こそ奇妙とか不思議とか不条理と評されるかもしれないが、語り手の巧みな叙述から、他者そのものの驚くべき深みや多様性をえぐりだし、わたしたちの日常を塗り替えていく手つきは、まさに文学的名匠というしかない。
表題作では離婚歴のある女性が、地球強奪の第一歩として猫の大虐殺を企(たくら)む異星人と結んだ共犯関係を告白し、「見下ろせば」ではヘビと猫を丸呑(の)みする鳥が「聖なる〈三〉」を体現する神として語り、「おばあちゃん」では孫娘が、人命救助に命を賭け天候や環境まで変えてしまうスーパーウーマンの武勇伝を回想し、「育ての母」では養母が、言葉や歌を教え込み愛情深く育んだ人間ならざる「あの子」との別れを惜しみ、「ジョーンズ夫人」では独身姉妹が、ふとしたことから遺伝子工学の産物らしき異形の老人を迎え入れ、新たな家族像を構築していくさまが綴(つづ)られる。
だがいちばんスリリングなのはむしろ、ごくあたりまえの人間たちが扱われる時だろう。「セックスおよび/またはモリソン氏」の語り手は、そもそも男女という二つの性を自明と思うこと自体が間違っているのかもしれない、「私たちの中にきっと『ほかの者』がいるはずだ」と確信する。
わたしたちの常識を心地よくもゆさぶる、これは小さくても破壊力満点の贈り物だ。
◇
The Start of the End of It All/畔柳和代訳/Carol Emshwiller 21年、米・ミシガン州生まれ。作家。
すべての終わりの始まり
著者:キャロル・エムシュウィラー
出版社:国書刊行会 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070307.html
*トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつなぐ [著]小林傳司
[掲載]2007年07月29日
[評者]山下範久(立命館大学准教授・歴史社会学)
■誰がどう「想定」し、責任を負うのか
本書を読んでいる最中に新潟県中越沖地震が起き、柏崎刈羽原発で火災、次いで微量の放射能漏れが報じられた。M6.8、震度6強という規模の地震は、設計の想定を超えていたそうであるから、原発の損傷はある意味では必然だったともいえる。
しかしこの「想定」とは、いったい誰の想定なのか。その「想定」の責任は誰が負うべきなのか。これらの問いがまさに本書のテーマである。
著者は言う。特定の状況を仮定したときに、どれくらいの確率でどのような帰結が生ずるかということについてならば、専門家の意見はおおむね一致する。しかしその特定の状況が起こる確率に対して、その帰結として生ずる事態への事前(および事後)の対処にかかる費用をどう評価するのかについては、専門家の意見の一致は崩れる。この設計ならこの震度までは耐えられるということについては、確実な判断ができるとしても、そもそもどのレベルの耐震性が社会的に要請されているのかの判断にまで、専門家に確実さの責任を負わせるには無理があるのだ。
著者が強調するのは、社会が科学技術をどのように受け入れるか、そのデザインを専門家まかせにしておける時代は終わったということである。逆にいえば、科学技術を受け入れる社会的な責任を、より広くかつ直接的に市民が共有すべきだということだ。
もちろん、専門家と非専門家のあいだの溝は掛け声だけでは埋まらない。なにか制度的な工夫が必要だ。本書はそのひとつとしてコンセンサス会議の手法を紹介している。公募で選ばれた市民パネルが、専門家との対話および市民パネル間の対話を通じて、技術の導入に関する意見をまとめ、行政に働きかける。それによって万人が合意する完璧(かんぺき)な「想定」が保証されるわけではないが、専門家は、非専門家との対話から、より社会的に適切な「想定」をなしうるし、非専門家もその「想定」についての責任を当事者として共有することになる。
「責任者」のつるし上げを繰り返すだけでは、問題は悪化の一途なのである。」
◇
こばやし・ただし 54年生まれ。大阪大教授。『誰が科学技術について考えるのか』
トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつなぐ
著者:小林 傳司
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200707310278.html
*となりの神さま [著]ペ・ソ/エトランジェのフランス史 [著]渡辺和行 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]酒井啓子(東京外国語大学教授・中東現代政治)
■オモロイ友達として共存する道問う
藤原新也が26年前に出版した『全東洋街道』が衝撃的だったのは、日本の外に旅して、アジア、中東の異文化に等身大でぶつかり、異国の強烈で生々しい日常を写真でわれわれに伝えてくれたからだ。
ペ・ソは、同じ異国のビビッドな生の営みを日本のなかに見つけて、紹介していく。群馬県のプレハブ建てのイスラーム教モスク、東京下町のマンションの一角にカラフルに飾り立てられたシク教寺院、九十九里浜で祈る韓国のシャーマン。これほどまでに多くの宗教、信仰ネットワークが日本国内で息吹(いぶ)いていたのかと、評者にも驚きだった。
外国人が増えるにつれ、日本に流入する異文化、見知らぬ宗教は、往々にして違和感と胡散(うさん)臭さをもって語られる。治安問題に結びつけたり、景観を問題にしたり、とにかく怪しい、という先入観が前面に出る。「異文化を理解しなければ」と考えても、頭のなかだけの優等生的回答になりがちだ。
しかし、『となりの神さま』がこうした異文化認識と決定的に違うのは、すでに共存に視点を定めているところだ。その映像、筆致は、徹底して温かい。ワシ、こんなヘンテコでオモロイ知り合いがたくさんおるんやで、的な、友達自慢みたいな本だ。筆者自身、異国からきた人々の生活の多様さに共振し、楽しんでいる。自分もまたディアスポラ(離散の民)だという意識が、相手と同じ目線を生んでいるのだろう。
外国人とは誰か、という問いは、国民とは誰か、との問いでもある。人々が王様への忠誠によって「臣民」とされていたとき、あるいは人々が信仰に応じて「信徒」とされていたときには、誰がその共同体の構成員かは、わかりやすかった。だが王様がいなくなり、宗教が統治と切り離された現代の国民国家では、国民とはいかに規定されるのか。
その問題に最初にぶつかったのが、革命後のフランスである。フランス革命を支持すれば外国人もフランス人になれるのか。フランス人の子としてフランスに生まれなければフランス人ではないのか。いったん国籍を得た外国人は、子孫もフランス人なのか。
先般フランス大統領となったサルコジ氏は、内相時代、北アフリカ出身の移民第二世代の若者を「社会のくず」と呼んで、物議をかもした。フランス国籍を持っていても、移民出身者は常に異邦人として社会から排斥される。特に近年のイスラーム運動のグローバルな台頭で、「イスラーム嫌い」が西欧全般に蔓延(まんえん)しつつある。
『エトランジェのフランス史』は、外国人受け入れを巡るフランスの対応を軸に、国民とは何か、を問う。歴史的に、労働力としての外国人受け入れの必要性から、同化・共存を謳(うた)いつつ、しばしば激しい外国人排斥を繰り返してきたフランス。今後、日本も同じような試行錯誤を強いられるのだろうか?
でもそこに「となりの神さま」を、オモロイ友達自慢として楽しむ包容力があれば、日本での異文化共存には、西欧と違う等身大の共生の道が、開けているのかもしれない。
◇
▽『となり――』/ペ・ソ 56年生まれ。フォトジャーナリスト。▽『エトランジェ――』/わたなべ・かずゆき 52年生まれ。奈良女子大学教授。
となりの神さま
著者:裴 昭
出版社:扶桑社 価格:¥ 1,470
エトランジェのフランス史―国民・移民・外国人
著者:渡辺 和行
出版社:山川出版社 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070273.html
[[◎生き方・考え方の本棚09Ⅱ]] へ
[[◎生き方・考え方の本棚10]] へ
#contents
- 逝ってよし(*´ω`)★ http://ktjg.net -- 俺だ (2012-03-03 12:24:51)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*竹内薫『竹内流の「書く・話す」知的アウトプット術』(2009.5 実務教育出版)[談風子]
竹内はサイエンス・ライターで100册もの著作があるというが、科学モノを読まない僕は知らなかった。(ただし最近話題になった『99.9%は仮説』という書名は知っている。)いけてない書名だし、サブタイトルに「プロフェッショナルは、こうやっている!」とあるのもなんか読む方が気恥ずかしいが、この本に惹かれたのは、タイトルに「話す」というのも入っているからだ。僕は、これから書く方だけでなく、講演や放送でも仕事が来るようにしたいと思っているだけに、「書く」と「話す」についてプロが伝授してくれるなら、と手にとった次第。
で、役に立ったかというと、「話す」に関しては、全く失望。「笑いをとれ」とか「つかみが大事」とか「客の反応を見よ」とか「リハーサルが大事」とか、当たり前で抽象的なアドバイスばかりで、あげくは「大事なのは、表面的な出来不出来より、しゃべる中身」ときたもんだ。
「書く」方に関してもたいした方法論はないが、筆一本で立つのは、かなりたいへん、二足のわらじが無難、という教えはありがたく拝聴した。「奥さんが許してくれたときが作家としての自立の時期だ」という鈴木光司の言葉は胸にしみる。
そのほか、ものを調べる具体的な方法でいくつか参考になることがあった。漢和辞典は大修館の「現代漢和辞典」がアイウエオ順で引けていいとか、英和辞典は「リーダーズ英和」だとか。英語のwikipediaはかなり使える、とか。あと、英会話は、廉価なCD教材を半年間繰り返し全部暗誦してしまえば一丁上がりだとか。これは早速実践してみよう。
(お勧め度 ★★)
#amazon(4788907593)
*日本浄土 [著]藤原新也
[掲載]2008年10月5日
[評者]久田恵(ノンフィクション作家)
■多くの生死を見つめ、なお旅の途上
70年代に若者だった世代にとって、第一作『インド放浪』を引っさげて登場してきた藤原新也は、衝撃だった。
熱に浮かされていた政治の季節が過ぎ去り、社会の管理化が推し進められようとしていた時代。どこにも行けない若者が、社会のあちこちで吹き溜(だ)まっていた。
その世代の一人だった私は、藤原新也の写真に釘(くぎ)付けになった。インドの聖地ベレナスの火葬の光景。夕日に染まった河を流れる遺体。その遺体を長い嘴(くちばし)で突く烏(からす)。
冒頭、著者は記していた。
「歩むごとに、ぼく自身と、ぼく自身の習って来た世界の虚偽が見えた」
彼はこの書によって多くの若者を旅に向かわせた。私はどこにも行けなかったけれど、ここではないどこかへ旅立たなければ、なにも分からないのだと思った。
80年代、『東京漂流』で、また衝撃を受けた。アジア13年の旅の後、著者は自分の目に映じた日本社会をしたたかに撃った。この本には、某誌連載を降板することになった写真が収められていた。インド放浪の折に撮られた野犬が屍(しかばね)を食らう写真だ。
「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」
添えられたコピーに社会が震撼(しんかん)した。
藤原新也は凄(すご)すぎた。唯一無比のアナーキーな社会派。尊敬を通りこし、畏敬(いけい)の念を抱かせた。
それから、25年。
本著、『日本浄土』に私は3度目の衝撃を受けた。気がついたら、遠くにいたはずの著者が傍らにいるではないか。
そして、美しいのである。文章も写真も。やさしくて深い味わいがある。
ここには、多くのものを見てきた人の静かなまなざしがある。頭の先で考えたことではなく、旅をしながら、生身の人々の生死を見つめてきた人の言葉がある。
世界を巡った長い放浪の果ての著者にとって、彼の人生でもっとも目立たない、思い出探しの島巡り、海巡りの旅だと言うこの本に、今、出会えて良かったな、と思う。
著者は、旅をしながら、「今日、佳景に出会うことは大海に針を拾うがごとくますます至難になりつつある」と語っている。
が、その一方で、歩行の速度の中では、「風景の中に息をひそめるように呼吸をしている微細な命が見え隠れする」とも言う。
事実、読者は、一葉のコスモスの写真を回路に、彼の放つ言葉の翼に乗って、記憶という行き着くことが果たせないほどの遠くまで旅立つことができるのだという思いに打たれるにちがいない。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200810070100.html
&amazon(4487802148)
*0601 ニッポンには対話がない [著]北川達夫・平田オリザ [朝日]
[掲載]2008年06月01日
15歳の国際基準学力世界一のフィンランドで教材を作る元外交官と、劇作家の大阪大教授が教育現場をふまえて対談した。フィンランドでは「心とか、考えというものは全員違うのがあたりまえ」。価値観の押しつけの危険性に、日本人は無防備だと指摘。自分の経験を絶対視しない、衝突後に妥協点を探るなど、意見の相違を恐れず対話を尽くすためのヒントがあふれている。多様化が進み、国際化・多文化化する社会では、「ダメなものはダメ」が、一番ダメなのだ。
出版社:三省堂 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200806030083.html
&amazon(4385363714)
*0504 調べる技術・書く技術 [著]野村進 [朝日]
[掲載]2008年05月04日
ノンフィクションを書くためのテーマ選び、資料集めに始まって実際の執筆まで、基本から助言する。事前にできるだけ調べる、人と会うときは絶対に遅刻しないなど、実は特別な近道はない。織り込まれた著者の体験が、参考になる。ノンフィクション取材にとどまらず、勉学や仕事にも役立ちそう。
調べる技術・書く技術 (講談社現代新書 1940) (講談社現代新書 1940)
著者:野村 進
出版社:講談社 価格:¥ 777
URL:http://book.asahi.com/paperback/TKY200805060113.html
&amazon(4062879409)
*0819 ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く [著]リサ・ランドール [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]渡辺政隆(サイエンスライター)
■現代宇宙物理学の最先端からの報告
最新の宇宙論に触れるたびに抱くのは、宇宙に果てはあるのか、広大無辺な宇宙における人間の存在とはいったい何なのかといった、考えれば考えるほど頭がぼうっとしてきそうな問いである。素人に納得できる解答が出されないまま、理論宇宙物理学の新しい学説が送り出されている。
今回の新機軸は、われわれはブレーンと呼ばれる膜のようなものの上で暮らしているのかもしれないと説く「ワープした余剰次元」理論。それと、その理論の提唱者にして本書の著者が、アインシュタインやホーキングといった、まさに異次元の住人を思わせる天才ではなく、才色兼備の物理学者という点。
では、その余剰次元とは何か。われわれが認識する世界は、縦・横・高さという3つの次元でできている。それに時間も入れた4次元の世界ならば、まあまあ常識で理解できる。しかし実際にはこれに、歪(ゆが)んだ(ワープした)第5の次元が存在するというのが余剰次元理論である。いや、こんな説明ではわからなくて当然。そもそも600ページにもおよぶ本書の内容を数行で要約できるはずがない。
本書の半分あまりはアインシュタインから超ひも理論までの理論物理学史のおさらいに当てられている。かつてニュートンは、自分が他よりも遠くを見通せたのは、巨人たち(偉大な先人たち)の肩の上に乗っていたからだと語ったという。研究が進み知識が増えつのるに伴い、先端科学を理解するための素養も増大する。踏み越えるべき巨人の数も増すというわけだ。おまけに次元数まで増えてしまった!
そこで本書の冒頭では高次の次元という考え方が、芸術家の遠近法になぞらえて説明されている。また、歴史のおさらいは、著者自らが提唱する最新理論が登場した必然性を踏まえている点で斬新である。新しい難解な理論が生み出される現場を垣間見られるエピソードも楽しい。難点があるとしたら、当事者が語る歴史特有の、細部へのこだわりだろうか。ともあれ、異次元宇宙にワープするには格好の1冊である。
◇
Warped Passages/向山信治監訳・塩原通緒訳/Lisa Randall 理論物理学者。米ハーバード大教授。
ワープする宇宙―5次元時空の謎を解く
著者:リサ・ランドール
出版社:日本放送出版協会 価格:¥ 3,045
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210244.html
&amazon(4140812397)
*すべての終わりの始まり [著]キャロル・エムシュウィラー [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]巽孝之(慶應大学教授・アメリカ文学)
■心地よく常識ゆさぶる破壊の力
半世紀ものキャリアを誇るアメリカ女性作家キャロル・エムシュウィラーは、すでに生ける伝説である。ジェイン・オースティンとともにフランツ・カフカを愛する彼女は、長短編問わず多数の傑作を書き継ぎ、ネビュラ賞やディック賞、世界幻想文学大賞など華麗な受賞歴を重ねてきた。必ずしも大向こう受けしそうもないその作風を称賛したのは、フェミニズムとSFの双方の視点より「他者(エイリアン)」の意義を知り尽くした、『ゲド戦記』で著名なアーシュラ・K・ル=グウィンや、その好敵手たる男装作家ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアといった猛者たちだった。
日本独自の編集になる本書が揃(そろ)えた19の短編も、雰囲気こそ奇妙とか不思議とか不条理と評されるかもしれないが、語り手の巧みな叙述から、他者そのものの驚くべき深みや多様性をえぐりだし、わたしたちの日常を塗り替えていく手つきは、まさに文学的名匠というしかない。
表題作では離婚歴のある女性が、地球強奪の第一歩として猫の大虐殺を企(たくら)む異星人と結んだ共犯関係を告白し、「見下ろせば」ではヘビと猫を丸呑(の)みする鳥が「聖なる〈三〉」を体現する神として語り、「おばあちゃん」では孫娘が、人命救助に命を賭け天候や環境まで変えてしまうスーパーウーマンの武勇伝を回想し、「育ての母」では養母が、言葉や歌を教え込み愛情深く育んだ人間ならざる「あの子」との別れを惜しみ、「ジョーンズ夫人」では独身姉妹が、ふとしたことから遺伝子工学の産物らしき異形の老人を迎え入れ、新たな家族像を構築していくさまが綴(つづ)られる。
だがいちばんスリリングなのはむしろ、ごくあたりまえの人間たちが扱われる時だろう。「セックスおよび/またはモリソン氏」の語り手は、そもそも男女という二つの性を自明と思うこと自体が間違っているのかもしれない、「私たちの中にきっと『ほかの者』がいるはずだ」と確信する。
わたしたちの常識を心地よくもゆさぶる、これは小さくても破壊力満点の贈り物だ。
◇
The Start of the End of It All/畔柳和代訳/Carol Emshwiller 21年、米・ミシガン州生まれ。作家。
すべての終わりの始まり
著者:キャロル・エムシュウィラー
出版社:国書刊行会 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070307.html
*トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつなぐ [著]小林傳司
[掲載]2007年07月29日
[評者]山下範久(立命館大学准教授・歴史社会学)
■誰がどう「想定」し、責任を負うのか
本書を読んでいる最中に新潟県中越沖地震が起き、柏崎刈羽原発で火災、次いで微量の放射能漏れが報じられた。M6.8、震度6強という規模の地震は、設計の想定を超えていたそうであるから、原発の損傷はある意味では必然だったともいえる。
しかしこの「想定」とは、いったい誰の想定なのか。その「想定」の責任は誰が負うべきなのか。これらの問いがまさに本書のテーマである。
著者は言う。特定の状況を仮定したときに、どれくらいの確率でどのような帰結が生ずるかということについてならば、専門家の意見はおおむね一致する。しかしその特定の状況が起こる確率に対して、その帰結として生ずる事態への事前(および事後)の対処にかかる費用をどう評価するのかについては、専門家の意見の一致は崩れる。この設計ならこの震度までは耐えられるということについては、確実な判断ができるとしても、そもそもどのレベルの耐震性が社会的に要請されているのかの判断にまで、専門家に確実さの責任を負わせるには無理があるのだ。
著者が強調するのは、社会が科学技術をどのように受け入れるか、そのデザインを専門家まかせにしておける時代は終わったということである。逆にいえば、科学技術を受け入れる社会的な責任を、より広くかつ直接的に市民が共有すべきだということだ。
もちろん、専門家と非専門家のあいだの溝は掛け声だけでは埋まらない。なにか制度的な工夫が必要だ。本書はそのひとつとしてコンセンサス会議の手法を紹介している。公募で選ばれた市民パネルが、専門家との対話および市民パネル間の対話を通じて、技術の導入に関する意見をまとめ、行政に働きかける。それによって万人が合意する完璧(かんぺき)な「想定」が保証されるわけではないが、専門家は、非専門家との対話から、より社会的に適切な「想定」をなしうるし、非専門家もその「想定」についての責任を当事者として共有することになる。
「責任者」のつるし上げを繰り返すだけでは、問題は悪化の一途なのである。」
◇
こばやし・ただし 54年生まれ。大阪大教授。『誰が科学技術について考えるのか』
トランス・サイエンスの時代―科学技術と社会をつなぐ
著者:小林 傳司
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 1,890
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200707310278.html
*となりの神さま [著]ペ・ソ/エトランジェのフランス史 [著]渡辺和行 [朝日]
[掲載]2007年08月05日
[評者]酒井啓子(東京外国語大学教授・中東現代政治)
■オモロイ友達として共存する道問う
藤原新也が26年前に出版した『全東洋街道』が衝撃的だったのは、日本の外に旅して、アジア、中東の異文化に等身大でぶつかり、異国の強烈で生々しい日常を写真でわれわれに伝えてくれたからだ。
ペ・ソは、同じ異国のビビッドな生の営みを日本のなかに見つけて、紹介していく。群馬県のプレハブ建てのイスラーム教モスク、東京下町のマンションの一角にカラフルに飾り立てられたシク教寺院、九十九里浜で祈る韓国のシャーマン。これほどまでに多くの宗教、信仰ネットワークが日本国内で息吹(いぶ)いていたのかと、評者にも驚きだった。
外国人が増えるにつれ、日本に流入する異文化、見知らぬ宗教は、往々にして違和感と胡散(うさん)臭さをもって語られる。治安問題に結びつけたり、景観を問題にしたり、とにかく怪しい、という先入観が前面に出る。「異文化を理解しなければ」と考えても、頭のなかだけの優等生的回答になりがちだ。
しかし、『となりの神さま』がこうした異文化認識と決定的に違うのは、すでに共存に視点を定めているところだ。その映像、筆致は、徹底して温かい。ワシ、こんなヘンテコでオモロイ知り合いがたくさんおるんやで、的な、友達自慢みたいな本だ。筆者自身、異国からきた人々の生活の多様さに共振し、楽しんでいる。自分もまたディアスポラ(離散の民)だという意識が、相手と同じ目線を生んでいるのだろう。
外国人とは誰か、という問いは、国民とは誰か、との問いでもある。人々が王様への忠誠によって「臣民」とされていたとき、あるいは人々が信仰に応じて「信徒」とされていたときには、誰がその共同体の構成員かは、わかりやすかった。だが王様がいなくなり、宗教が統治と切り離された現代の国民国家では、国民とはいかに規定されるのか。
その問題に最初にぶつかったのが、革命後のフランスである。フランス革命を支持すれば外国人もフランス人になれるのか。フランス人の子としてフランスに生まれなければフランス人ではないのか。いったん国籍を得た外国人は、子孫もフランス人なのか。
先般フランス大統領となったサルコジ氏は、内相時代、北アフリカ出身の移民第二世代の若者を「社会のくず」と呼んで、物議をかもした。フランス国籍を持っていても、移民出身者は常に異邦人として社会から排斥される。特に近年のイスラーム運動のグローバルな台頭で、「イスラーム嫌い」が西欧全般に蔓延(まんえん)しつつある。
『エトランジェのフランス史』は、外国人受け入れを巡るフランスの対応を軸に、国民とは何か、を問う。歴史的に、労働力としての外国人受け入れの必要性から、同化・共存を謳(うた)いつつ、しばしば激しい外国人排斥を繰り返してきたフランス。今後、日本も同じような試行錯誤を強いられるのだろうか?
でもそこに「となりの神さま」を、オモロイ友達自慢として楽しむ包容力があれば、日本での異文化共存には、西欧と違う等身大の共生の道が、開けているのかもしれない。
◇
▽『となり――』/ペ・ソ 56年生まれ。フォトジャーナリスト。▽『エトランジェ――』/わたなべ・かずゆき 52年生まれ。奈良女子大学教授。
となりの神さま
著者:裴 昭
出版社:扶桑社 価格:¥ 1,470
エトランジェのフランス史―国民・移民・外国人
著者:渡辺 和行
出版社:山川出版社 価格:¥ 1,575
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708070273.html
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: