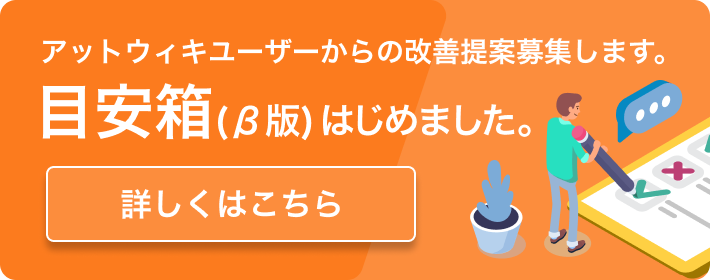「◎市民の政策局の本棚07・08」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「◎市民の政策局の本棚07・08」(2009/06/07 (日) 12:01:51) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
[[◎市民の政策局の本棚]]
#contents
- ホテル行く前に外で2発イカせてもらいますた! http://ston.mlstarn.com/2441402 -- てれれん (2009-06-02 20:17:05)
- セフしさまさまだなwマジ天国www &br() &br()http://sersai%2ecom/hosakimenma/28457778 -- 大日にょ来 (2009-06-06 00:10:46)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*新しい貧困―労働、消費主義、ニュープア [著]ジグムント・バウマン
[掲載]2008年9月28日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
■貧困の根本原因を掘り下げる貴重な試み
本書の議論の骨子は以下のようなものだ。(1)「労働倫理」というものが近代社会において生まれたが、それは産業化時代の工場労働に典型的なもので、労働は貧困撲滅のための万能薬とされた。(2)時代はやがて「生産社会」から「消費社会」へと移行したが、それは欲望の無限の拡大を駆動因とする社会であり、消費者の審美的な選択が支配的となる。そこでは労働も「面白く」自己実現的な少数の労働と、「退屈」でルーチン的な大多数の労働に二極化する。さらに20世紀末以降、失業が長期化する中で「余剰」労働者という言い方が一般的となる。(3)もともと資本主義はその余剰を植民地の開発によって解決しようとしてきたが、今や「私たちの地球は満杯である」。したがって、問題はむしろローカルなレベルで解決されなければならない。(4)何がなされるべきか。手がかりは賃労働中心の考え方からの脱却であり、「基本所得」(労働と無関係に一定の所得を保障する制度)や「職人の倫理」の復権、「経済成長」への態度変更などが柱となるが、それは私たちの価値観の根本的な転換を伴うものである。
(要約)
出版社:青土社 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200809300097.html
*民主主義への憎悪 [著]ジャック・ランシエール
[掲載]2008年9月21日
[評者]柄谷行人(評論家)
■とるにたらない者による統治を
一般に、民主主義というと、代表制(議会制)と同義だと考えられている。しかし、モンテスキューは代表制と民主主義を峻別(しゅんべつ)した。代表制とは貴族政あるいは寡頭政の一種であり、選挙によって選ばれた有能なエリートが支配する体制である。一方、民主主義の本質は、アテネにおいてそうであったように、くじ引きにある。デモクラシーとは、デモス(民衆)が、すなわち、「とるにたらない」(誰でもよい)者が統治する体制なのである。
民主主義の問題をプラトンにさかのぼって根本的に問い直す著者は、民主主義を積極的に肯定する。といっても、民主主義は制度ではないし、合意を形成する手段でもない。それは、これまで公的な領域から排除され、「言葉をもたない」とされてきた者らが、「不合意」を唱え、異議を申し立てる出来事を意味する。そこにこそ、「とるにたらない者」による統治、つまり、デモクラシーが存在するのである。(趣意)
出版社:インスクリプト 価格:¥ 2,940
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200809230080.html
*教育立国フィンランド流 教師の育て方 [著]増田ユリヤ
[掲載]2008年10月5日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
■社会のデザインと教育プランが一致
80年代までの教育界では「アメリカでは……」がはやり、彼(か)の地の大学入試制度やバラ色の学校生活を輸入する教育改革の提案が相次いだ。皮肉にもその後、当のアメリカで日本をモデルとする教育改革が進んで、アメリカ「ではの守(かみ)」たちは退場した。
いま教育界の注目はフィンランドに集まる。経済協力開発機構の学習到達度調査で、連続世界一の学力を示したためである。日本はこの調査で、順位をやや下げた。学力低下不安とゆとり教育批判の中で、日本の教育界は成功の秘訣(ひけつ)を求めて尋常ならざる関心をフィンランドに向けた。
著者は05年から5回にわたってフィンランドを訪問し、30カ所にのぼる教育機関を取材した。「どんなにスゴい教育が行われているのか」と意気込んで見たのだが、結論は「何を見ても、どんな話を聞いても、ただ単にまっとうなことを実行しているのみ」。
とはいえ、フィンランドと日本の教育風景は相当に異なる。フィンランド教育を語るためには「すべての子どもに平等な教育を」「現場への信頼」「質の高い教員の養成」という三つのキーワードで足りる。日本の教育も、理念的にはそう違わない。異なるのは、理念を実現するための仕組みが実際に存在し機能しているかどうかだ。理解の遅い子どもを早い段階で手助けし落ちこぼれを未然に防ぐ体制、子どもたちの心の問題にチームでていねいに対処する仕組み――それらが至極当然のように、質の高い教師たちによって実際に機能している様子に、驚きを禁じ得ない。
なぜそれが可能か。著者は言う。「社会のデザインと教育プランが見事なほどに一致」している。どういう社会を作りたいのか、そのために教育はどうあるべきかが国レベルから現場レベルまで一貫している。こう看破する著者に導かれて、私たちは、「なぜ社会と学校現場の間でネジレが生じ、まっとうなことをそのまま実行できないのか」という核心的な問いにたどり着く。答えるのは容易ではないが、「ではの守」たちによる類書をはるかに凌駕(りょうが)する洞察といってよい。
◇
ますだ・ゆりや 64年生まれ。教育ジャーナリスト。『「新」学校百景』など。
出版社:岩波書店 価格:¥ 1,680
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200810070092.html
*どうする国有林 [著]笠原義人、香田徹也、塩谷弘康
[掲載]2008年7月13日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
■森林の公共性とは何かを問い直す
土地所有というテーマはある意味で日本社会の核心にある問題だが、それは国土の約7割を占める森林、そしてその森林の3割を占める国有林についてもあてはまる。
本書はそうした国有林が、2006年の行革推進法を受け独立行政法人化の方向で検討が進められている状況を踏まえ、単純な民営化推進論に疑義を呈しつつ、これからの国有林のあり方について包括的な議論を展開するものである。環境問題への関心が高まる中、「森」についての書物は数多く出されているが、森林の「所有」のあり方や「政策」を正面から議論するものは少なく、その点からも貴重な内容だ。
本書の前半では国有林をめぐる戦後の政策展開が概観される。戦後復興期から高度成長期にかけて、広葉樹林を針葉樹林に転換する拡大造林の方針のもと、成長量をはるかに超える伐採を続けた結果、森林資源が枯渇して赤字経営に転落した第1期。「改善計画」が開始されたものの実質は事業縮小にほかならず、累積債務が膨れ上がり事実上の破産宣告に至った第2期。「抜本的改革」が唱えられつつなお理念が定まらぬまま現在に至る第3期。こうした政策展開を検証した上で、後半では今後の国有林のあり方に関する四つの基本理念((1)持続性原則(2)地域原則(3)公共性原則(4)公開・参加原則)が提示されるとともに、「国有林基本法」の制定など具体的な提言が行われる。
かさはら・よしと 宇都宮大名誉教授。東京林業研究会国有林部会会員が執筆。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807150127.html
*0518 政局から政策へ―日本政治の成熟と転換 [著]飯尾潤 [朝日]
[掲載]2008年05月18日
[評者]久保文明(東京大学教授・アメリカ政治)
はたして日本の政治はよくなったのか。難しい問いである。よくなったと言い切るには勇気がいる。しかし、それが本書の基本的な立場である。最近二十数年間の日本政治を振り返り、選挙制度改革や内閣機能の強化などの「政治改革」の流れを肯定的に評価する。
著者によると、わが国の政治は議院内閣制ならぬ官僚内閣制によって統治されており、55年体制も「経済自立人」ではなく「行政依存人」のための政治体制であった。内閣の主体は官僚制を内実とする各省庁にあり、政策運営の第一義的担い手は各省庁であった。中選挙区制の下、政権交代なき政党政治において、政治は「政局」を中心に展開され「政策」は付け足しであった。
ところが、小選挙区制の導入およびその他の改革によって、選挙区での投票によって首相を選ぶ方向に有権者の意識が変わり、日本の政治は大きく変わり始めた。その画期となったのが05年の郵政解散である。有権者と首相が直結し、それによって大きく政治が動いた。小泉内閣の下、官僚内閣制から議院内閣制本来の姿に変貌(へんぼう)し、政治といえば政局という常識が崩れた。政策は官僚に任せる政治から、政局を起こすにも政策、それも個別政策ではなく、一定の(例えば経済自立人的)価値観に立脚した政策体系の提示が必要になった。これが著者の主張である。
しかし、アメリカの(やや行き過ぎとも思われる)固定化した政党対立と比較すると、わが国の政党は指導者も含めて、政策体系を支える基本的価値観の次元で無原則的な揺れが大きく、改革の政党が突如行政依存人の政党になる(あるいはその逆)。政党が提示する政策体系と有権者との安定した結びつきがまだ弱いのではないか。とりわけ政党には原則、信念、一貫性を重視する姿勢が弱い。このあたりが、日本政治の質をさらに高めていくための次なる課題では、とも思われる。
良質の政治評論は少ない。その中にあって本書は近年のわが国政治の軌跡を骨太に理解するのに格好の書である。
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805200145.html
*0525 子どもの貧困―子ども時代のしあわせ平等のために [編]浅井春夫、松本伊智朗、湯澤直美 [朝日]
[掲載]2008年05月25日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
この論文集が扱っているのは、掛け値なしに重要で目を背けることのできない主題である。著者らによれば、未婚の子を含む世帯の貧困率は約15%、とくにひとり親世帯で高く、また1990年代後半から増加している。
執筆陣には、児童福祉研究者のほか、児童養護施設や婦人保護施設など、福祉の実践者が名を連ねる。現場からの報告は、保育料滞納問題、虐待のハイリスク要因としての貧困等を取り上げており、貧困に起因する諸問題の広がりをあらためて痛感させる。
私自身、近年、教育格差に関心を有するため、この本の企図を貴重だと思う。現代社会は業績に応じて富が配分されることを正当だと認める社会である。競争の結果として富の不平等が生まれるのは当然の帰結に過ぎない。にもかかわらずなぜ、子どもの貧困は、注視されねばならないのか。だれにでも機会が開かれた競争という業績主義社会を支える「公正」の前提が、子どもの貧困の存在によって容易に突き崩されてしまうからだ。子どもの貧困は、富の格差が子世代へと再生産され、人生のスタートラインにおいて機会がけっして平等に開かれているわけではないことを端的に示すからである。
この本の読者は、貧困という現実を生きることを、自己責任からではなく余儀なくされた子どもたちの存在を目の当たりにし、彼らを生み続ける社会構造に対して怒りを共有するだろう。「貧困は見ようとしないと見えない」。それを見せてくれる点に本書の最大の貢献がある。
だが問題は、その次の問いにある。なにをなすべきか。
前政権は再チャレンジ可能な社会の建設を目標に掲げたが、焦眉(しょうび)の急は再チャレンジ以前にある。編者のひとり浅井春夫は、いまの社会福祉政策が子どもの貧困を克服する方向ではなく貧困児童の排除政策の色彩を強めていることを憂う。とくに重要なのは、表面上の機会均等ではなく実効的な機会の均等を保障するために、貧困層を手厚く支援する「積極的格差」原則の提案である。政策転換を期待したい。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805270138.html
*0525 ワークライフシナジー―生活と仕事の〈相互作用〉が変える企業社会 [著]大沢真知子
[掲載]2008年05月25日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
本書は、前著『ワークライフバランス社会へ』での著者の議論を一歩進める形で、なぜ「ワークライフバランス」が日本においてなかなか定着しないかの要因を探るとともに、浸透のための対応策を具体例とともに提示し、これらを通じて「ワークライフシナジー(仕事と生活の相互作用・相乗効果)」という新たな考え方を提案するものだ。
本書が打ち出している特徴的な視点として以下の三つがある。第一に、「労働時間が短い国のほうが労働生産性が高い」という論点を積極的に示していること。第二に、かといって「ワークライフバランスは“生産性向上に寄与するから”重要だ」という議論に終わるのではなく、「足るを知る」ことといった、人々の価値観そのものの転換について論を展開していること。第三に、「ワークライフバランスはストレスマネジメント」という指摘に示されるように、労働あるいは働き方とストレスの関係という、これまで日本で十分に論じられてこなかった視点を重視していること(私は日本人の最大の健康阻害要因は労働のあり方にあると考えている)。全体を通じ、著者自身の個人的な経験も多く盛り込まれていて読みやすい。
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,310
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805270133.html
*0602 『“食の安全"はどこまで信用できるのか』 [読売]
河岸宏和
出版社:アスキー・メディアワークス
発行:2008年3月
ISBN:9784756151353
価格:¥760 (本体¥724+税)
食品表示が義務づけられているコンビニ弁当はかなり安全、国産だからといって安心とはいえない――。食肉処理場や総菜工場の現場で長年品質管理に携わってきたベテランが、業界では当たり前だが、消費者は知らない“食”のカラクリを解き明かす。(アスキー新書、724円)
(2008年6月2日 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/book/paperback/20080602bk0f.htm
*0601 加害者は変われるか?―DVと虐待をみつめながら [著]信田さよ子 [朝日]
[掲載]2008年06月01日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待にかかわる援助者は、最近すっかり被害者支援、ケアへと力点を移した。被害者に集中し、加害者を敵視するだけの現場の視線の中で、著者はそれでよいのかと考える。臨床事例と事例から作られた架空の挿話が、加害者とは誰か、彼らは変われるか、被害者はなにを望んでいるのかを問う。
加害者の多くは、虐待とDVの被害経験者、目撃者である。大人になった彼らにとって、妻は自分の思い通りになりどんな自分も受け入れてくれる「母」(であるべき)なのだ。加害者を敵視するだけの問題構成は、そうした理解を妨げ適切な対処方策から目をそらせてしまう。彼らは特殊ではなくどこにでもいる。
著者には、虐待やDVの根を個人の心理に求めるのではなく、夫と妻、親と子の間の非対称的な権力関係の中に位置づける社会学的発想が見える。心理学界ではやや異端かもしれないが、私には常套(じょうとう)手段にとらわれずに真の被害者支援を追求する、勇敢な実践家に思えた。
出版社:文藝春秋
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200806030088.html
*経済再生の条件―失敗から何を学ぶか [著]塩谷隆英 [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]高橋伸彰(立命館大学教授・日本経済論)
■元次官が痛感する政策「戦略」の重要性
01年1月の省庁再編に伴い、かつての経済白書は「経済財政白書」と名前が変わった。名前だけではなく、時の政権に媚(こ)びない中立的なかつての白書の分析も、当時の竹中平蔵大臣の言葉によれば「経済財政諮問会議の審議のサポート」に変容した。
変わり果てた白書を見て66年に経済企画庁に入庁し、事務次官を経て99年に退官した著者は「昔の白書を懐かしく思う」という。しかし、ノスタルジーから覚めた著者は心機一転、バブル発生以降の失敗の教訓を「公共政策に携わった者の責務」として「後進に伝え」ようと試みる。失敗の本質は「戦略性の欠如」にあった。高度成長に継ぐ目標を定められないまま、整合性を欠いた政策運営が続けられたのだ。実際、プラザ合意後の円高不況や貿易摩擦への対応を優先し、資産価格の高騰を放置した失敗がバブルを招き、その退治に固執した過度な引き締め策が、銀行のバランスシートに与える影響を看過した失敗の顛末(てんまつ)が90年代の「大停滞」だった。
30年以上に及ぶ政策現場での経験から著者が学んだのは、不況に陥れば長期の目標を棚上げしても景気対策に集中し、好況に転じれば目先の利益よりも長期の目標を追求するという、政策「戦略」の重要性である。その判断を間違えば、97年後半以降の不況の際に財政支出を惜しみ、虎の子の財政構造改革法の効力を成立後1年余りで失った旧大蔵省の轍(てつ)を踏む恐れがある。同様に、一見「勇ましい」小泉改革の行方も、格差を放置すれば必ずしも安泰ではない。「見えざる神の手」に日本の未来をゆだねる改革に批判的な著者は、「改革なくして成長なし」の帰結が「効率一辺倒・弱肉強食の格差社会」に見えるという。
本書には多くの政治家や官僚が実名で登場し、景気判断や政策調整をめぐる議論や交渉の様子が臨場感溢(あふ)れる形で再現される。そこで著者が示すのは、どんなに優れた人間でも間違うということだ。過去の失敗を責めても歴史は変わらない。しかし、失敗から学ばなければ同じ失敗が繰り返されるのである。
◇
しおや・たかふさ 41年生まれ。経済企画事務次官、NIRA理事長など歴任。
経済再生の条件―失敗から何を学ぶか
著者:塩谷 隆英
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,100
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210264.html
*0729 「トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ」 小林傳司著 NTT出版
著者が強調するのは、社会が科学技術をどのように受け入れるか、そのデザインを専門家まかせにしておける時代は終わったということである。([朝日]書評(2007/07/29 by山下範久
*民営化で誰が得をするのか [著]石井陽一/市場原理とアメリカ医療 [著]石川義弘 [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]小林良彰(慶應大学教授・政治学)
■理念なき「改革」はどこに向かうのか
先の参院選で自民党が大敗した。小泉改革で進められた新自由主義改革が現実のものとなった結果、地域間格差や個人間格差に伴う不公平感が生じたことが、大敗の一因としてあげられる。そもそも、小泉元首相を支持していた者は多かったが、改革の中身をどこまで理解して支持していたのだろうか。
『民営化で誰が得をするのか』は、期せずしてタイムリーな出版となった。著者は、海外移住事業団での駐在経験も持つ神奈川大名誉教授。海外情勢に詳しい目で、日本の旧三公社(国鉄・電電・専売)や、道路公団・郵政の民営化を、米国や欧州・ラテンアメリカ・アジア各国と比較し検証した。
まず世界の民営化を、動機に基づいて五つのタイプに分け、日本における民営化の多くが「政治的配慮」によって行われ、「民営化そのものは目的ではなく、労働問題、政治問題であった」と批判する。旧三公社のうち、国労・動労や全電通という強力な労働組合があった国鉄と電電公社の解体は、総評の崩壊と社会党の没落を招く。一方、専売公社の労組は穏健であったため、日本たばこ産業(JT)は分割されずに済んだと指摘する。
小泉改革における道路と郵政の民営化については、なぜ民営化なのか理念がはっきりとせぬままに構造改革という美辞麗句にくるまれ、あたかも逆らえない世界の潮流かのような思いこみの中、既成事実として民営化が進行しつつあると手厳しい。
経済面の効果も疑問視する。民営化収入で国の債務を償却したり増税を免れたりした国もあるなか、日本の場合は巨額な政府債務の前に焼け石に水でしかなかった。また、郵便料金は変わらず、JRも私鉄と比べて運賃が特段、安いわけではない。こちらも競争原理導入で効果が上がっているとは言い難い。
民営化では、医療も聖域ではない。例えば、大学の独立法人化や国立病院の民間移転など、わが国でも米国流の市場原理が徐々に導入され始めている。『市場原理とアメリカ医療』は、ハーバード大助教授などを経て横浜市立大教授である著者が、日米の大学で医療に携わってきた経験を背景に、米国の医療制度の現状と問題点を詳細に紹介した。
国民健康保険制度がある日本と異なり、米国では自動車など他の保険と同様に医療保険が民営化されており、高額保険の加入者は高水準の医療を受けられる。医師も技術に見合った報酬を受け取ることができ、医療水準が他国に比べて高い。しかしその半面、安い保険の加入者は低水準の医療に甘んじ、国民の2割を占める無保険者は症状がひどくなってから救急救命センターに駆け込むか州立病院の慈善クリニックなどへ行くしかない。
結局、市場原理から得るものもあるが、隣の芝生が緑に見えるが如(ごと)く、何でも民営化しさえすればいいというものではないというのが、両書の著者達(たち)の主張である。財政再建のためなのか、それとも所得再分配のためなのかという民営化の理念を明確にした上で、日本の実情に合わせた公平な実施策を考える段階に来ているのではないか。
◇
いしい・よういち 30年生まれ/いしかわ・よしひろ 59年生まれ。
民営化で誰が得をするのか―国際比較で考える
著者:石井 陽一
出版社:平凡社 価格:¥ 735
市場原理とアメリカ医療―日本の医療改革の未来形
著者:石川 義弘
出版社:医学通信社 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210170.html
*[[◎市民の政策局の本棚06]] より続く
[[◎市民の政策局の本棚]]
#contents
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40) ↑ご自由にコメントをお書き下さい。
*新しい貧困―労働、消費主義、ニュープア [著]ジグムント・バウマン
[掲載]2008年9月28日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
■貧困の根本原因を掘り下げる貴重な試み
本書の議論の骨子は以下のようなものだ。(1)「労働倫理」というものが近代社会において生まれたが、それは産業化時代の工場労働に典型的なもので、労働は貧困撲滅のための万能薬とされた。(2)時代はやがて「生産社会」から「消費社会」へと移行したが、それは欲望の無限の拡大を駆動因とする社会であり、消費者の審美的な選択が支配的となる。そこでは労働も「面白く」自己実現的な少数の労働と、「退屈」でルーチン的な大多数の労働に二極化する。さらに20世紀末以降、失業が長期化する中で「余剰」労働者という言い方が一般的となる。(3)もともと資本主義はその余剰を植民地の開発によって解決しようとしてきたが、今や「私たちの地球は満杯である」。したがって、問題はむしろローカルなレベルで解決されなければならない。(4)何がなされるべきか。手がかりは賃労働中心の考え方からの脱却であり、「基本所得」(労働と無関係に一定の所得を保障する制度)や「職人の倫理」の復権、「経済成長」への態度変更などが柱となるが、それは私たちの価値観の根本的な転換を伴うものである。
(要約)
出版社:青土社 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200809300097.html
*民主主義への憎悪 [著]ジャック・ランシエール
[掲載]2008年9月21日
[評者]柄谷行人(評論家)
■とるにたらない者による統治を
一般に、民主主義というと、代表制(議会制)と同義だと考えられている。しかし、モンテスキューは代表制と民主主義を峻別(しゅんべつ)した。代表制とは貴族政あるいは寡頭政の一種であり、選挙によって選ばれた有能なエリートが支配する体制である。一方、民主主義の本質は、アテネにおいてそうであったように、くじ引きにある。デモクラシーとは、デモス(民衆)が、すなわち、「とるにたらない」(誰でもよい)者が統治する体制なのである。
民主主義の問題をプラトンにさかのぼって根本的に問い直す著者は、民主主義を積極的に肯定する。といっても、民主主義は制度ではないし、合意を形成する手段でもない。それは、これまで公的な領域から排除され、「言葉をもたない」とされてきた者らが、「不合意」を唱え、異議を申し立てる出来事を意味する。そこにこそ、「とるにたらない者」による統治、つまり、デモクラシーが存在するのである。(趣意)
出版社:インスクリプト 価格:¥ 2,940
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200809230080.html
*教育立国フィンランド流 教師の育て方 [著]増田ユリヤ
[掲載]2008年10月5日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
■社会のデザインと教育プランが一致
80年代までの教育界では「アメリカでは……」がはやり、彼(か)の地の大学入試制度やバラ色の学校生活を輸入する教育改革の提案が相次いだ。皮肉にもその後、当のアメリカで日本をモデルとする教育改革が進んで、アメリカ「ではの守(かみ)」たちは退場した。
いま教育界の注目はフィンランドに集まる。経済協力開発機構の学習到達度調査で、連続世界一の学力を示したためである。日本はこの調査で、順位をやや下げた。学力低下不安とゆとり教育批判の中で、日本の教育界は成功の秘訣(ひけつ)を求めて尋常ならざる関心をフィンランドに向けた。
著者は05年から5回にわたってフィンランドを訪問し、30カ所にのぼる教育機関を取材した。「どんなにスゴい教育が行われているのか」と意気込んで見たのだが、結論は「何を見ても、どんな話を聞いても、ただ単にまっとうなことを実行しているのみ」。
とはいえ、フィンランドと日本の教育風景は相当に異なる。フィンランド教育を語るためには「すべての子どもに平等な教育を」「現場への信頼」「質の高い教員の養成」という三つのキーワードで足りる。日本の教育も、理念的にはそう違わない。異なるのは、理念を実現するための仕組みが実際に存在し機能しているかどうかだ。理解の遅い子どもを早い段階で手助けし落ちこぼれを未然に防ぐ体制、子どもたちの心の問題にチームでていねいに対処する仕組み――それらが至極当然のように、質の高い教師たちによって実際に機能している様子に、驚きを禁じ得ない。
なぜそれが可能か。著者は言う。「社会のデザインと教育プランが見事なほどに一致」している。どういう社会を作りたいのか、そのために教育はどうあるべきかが国レベルから現場レベルまで一貫している。こう看破する著者に導かれて、私たちは、「なぜ社会と学校現場の間でネジレが生じ、まっとうなことをそのまま実行できないのか」という核心的な問いにたどり着く。答えるのは容易ではないが、「ではの守」たちによる類書をはるかに凌駕(りょうが)する洞察といってよい。
◇
ますだ・ゆりや 64年生まれ。教育ジャーナリスト。『「新」学校百景』など。
出版社:岩波書店 価格:¥ 1,680
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200810070092.html
*どうする国有林 [著]笠原義人、香田徹也、塩谷弘康
[掲載]2008年7月13日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
■森林の公共性とは何かを問い直す
土地所有というテーマはある意味で日本社会の核心にある問題だが、それは国土の約7割を占める森林、そしてその森林の3割を占める国有林についてもあてはまる。
本書はそうした国有林が、2006年の行革推進法を受け独立行政法人化の方向で検討が進められている状況を踏まえ、単純な民営化推進論に疑義を呈しつつ、これからの国有林のあり方について包括的な議論を展開するものである。環境問題への関心が高まる中、「森」についての書物は数多く出されているが、森林の「所有」のあり方や「政策」を正面から議論するものは少なく、その点からも貴重な内容だ。
本書の前半では国有林をめぐる戦後の政策展開が概観される。戦後復興期から高度成長期にかけて、広葉樹林を針葉樹林に転換する拡大造林の方針のもと、成長量をはるかに超える伐採を続けた結果、森林資源が枯渇して赤字経営に転落した第1期。「改善計画」が開始されたものの実質は事業縮小にほかならず、累積債務が膨れ上がり事実上の破産宣告に至った第2期。「抜本的改革」が唱えられつつなお理念が定まらぬまま現在に至る第3期。こうした政策展開を検証した上で、後半では今後の国有林のあり方に関する四つの基本理念((1)持続性原則(2)地域原則(3)公共性原則(4)公開・参加原則)が提示されるとともに、「国有林基本法」の制定など具体的な提言が行われる。
かさはら・よしと 宇都宮大名誉教授。東京林業研究会国有林部会会員が執筆。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200807150127.html
*0518 政局から政策へ―日本政治の成熟と転換 [著]飯尾潤 [朝日]
[掲載]2008年05月18日
[評者]久保文明(東京大学教授・アメリカ政治)
はたして日本の政治はよくなったのか。難しい問いである。よくなったと言い切るには勇気がいる。しかし、それが本書の基本的な立場である。最近二十数年間の日本政治を振り返り、選挙制度改革や内閣機能の強化などの「政治改革」の流れを肯定的に評価する。
著者によると、わが国の政治は議院内閣制ならぬ官僚内閣制によって統治されており、55年体制も「経済自立人」ではなく「行政依存人」のための政治体制であった。内閣の主体は官僚制を内実とする各省庁にあり、政策運営の第一義的担い手は各省庁であった。中選挙区制の下、政権交代なき政党政治において、政治は「政局」を中心に展開され「政策」は付け足しであった。
ところが、小選挙区制の導入およびその他の改革によって、選挙区での投票によって首相を選ぶ方向に有権者の意識が変わり、日本の政治は大きく変わり始めた。その画期となったのが05年の郵政解散である。有権者と首相が直結し、それによって大きく政治が動いた。小泉内閣の下、官僚内閣制から議院内閣制本来の姿に変貌(へんぼう)し、政治といえば政局という常識が崩れた。政策は官僚に任せる政治から、政局を起こすにも政策、それも個別政策ではなく、一定の(例えば経済自立人的)価値観に立脚した政策体系の提示が必要になった。これが著者の主張である。
しかし、アメリカの(やや行き過ぎとも思われる)固定化した政党対立と比較すると、わが国の政党は指導者も含めて、政策体系を支える基本的価値観の次元で無原則的な揺れが大きく、改革の政党が突如行政依存人の政党になる(あるいはその逆)。政党が提示する政策体系と有権者との安定した結びつきがまだ弱いのではないか。とりわけ政党には原則、信念、一貫性を重視する姿勢が弱い。このあたりが、日本政治の質をさらに高めていくための次なる課題では、とも思われる。
良質の政治評論は少ない。その中にあって本書は近年のわが国政治の軌跡を骨太に理解するのに格好の書である。
出版社:エヌティティ出版 価格:¥ 2,415
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805200145.html
*0525 子どもの貧困―子ども時代のしあわせ平等のために [編]浅井春夫、松本伊智朗、湯澤直美 [朝日]
[掲載]2008年05月25日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
この論文集が扱っているのは、掛け値なしに重要で目を背けることのできない主題である。著者らによれば、未婚の子を含む世帯の貧困率は約15%、とくにひとり親世帯で高く、また1990年代後半から増加している。
執筆陣には、児童福祉研究者のほか、児童養護施設や婦人保護施設など、福祉の実践者が名を連ねる。現場からの報告は、保育料滞納問題、虐待のハイリスク要因としての貧困等を取り上げており、貧困に起因する諸問題の広がりをあらためて痛感させる。
私自身、近年、教育格差に関心を有するため、この本の企図を貴重だと思う。現代社会は業績に応じて富が配分されることを正当だと認める社会である。競争の結果として富の不平等が生まれるのは当然の帰結に過ぎない。にもかかわらずなぜ、子どもの貧困は、注視されねばならないのか。だれにでも機会が開かれた競争という業績主義社会を支える「公正」の前提が、子どもの貧困の存在によって容易に突き崩されてしまうからだ。子どもの貧困は、富の格差が子世代へと再生産され、人生のスタートラインにおいて機会がけっして平等に開かれているわけではないことを端的に示すからである。
この本の読者は、貧困という現実を生きることを、自己責任からではなく余儀なくされた子どもたちの存在を目の当たりにし、彼らを生み続ける社会構造に対して怒りを共有するだろう。「貧困は見ようとしないと見えない」。それを見せてくれる点に本書の最大の貢献がある。
だが問題は、その次の問いにある。なにをなすべきか。
前政権は再チャレンジ可能な社会の建設を目標に掲げたが、焦眉(しょうび)の急は再チャレンジ以前にある。編者のひとり浅井春夫は、いまの社会福祉政策が子どもの貧困を克服する方向ではなく貧困児童の排除政策の色彩を強めていることを憂う。とくに重要なのは、表面上の機会均等ではなく実効的な機会の均等を保障するために、貧困層を手厚く支援する「積極的格差」原則の提案である。政策転換を期待したい。
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805270138.html
*0525 ワークライフシナジー―生活と仕事の〈相互作用〉が変える企業社会 [著]大沢真知子
[掲載]2008年05月25日
[評者]広井良典(千葉大学教授・公共政策)
本書は、前著『ワークライフバランス社会へ』での著者の議論を一歩進める形で、なぜ「ワークライフバランス」が日本においてなかなか定着しないかの要因を探るとともに、浸透のための対応策を具体例とともに提示し、これらを通じて「ワークライフシナジー(仕事と生活の相互作用・相乗効果)」という新たな考え方を提案するものだ。
本書が打ち出している特徴的な視点として以下の三つがある。第一に、「労働時間が短い国のほうが労働生産性が高い」という論点を積極的に示していること。第二に、かといって「ワークライフバランスは“生産性向上に寄与するから”重要だ」という議論に終わるのではなく、「足るを知る」ことといった、人々の価値観そのものの転換について論を展開していること。第三に、「ワークライフバランスはストレスマネジメント」という指摘に示されるように、労働あるいは働き方とストレスの関係という、これまで日本で十分に論じられてこなかった視点を重視していること(私は日本人の最大の健康阻害要因は労働のあり方にあると考えている)。全体を通じ、著者自身の個人的な経験も多く盛り込まれていて読みやすい。
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,310
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200805270133.html
*0602 『“食の安全"はどこまで信用できるのか』 [読売]
河岸宏和
出版社:アスキー・メディアワークス
発行:2008年3月
ISBN:9784756151353
価格:¥760 (本体¥724+税)
食品表示が義務づけられているコンビニ弁当はかなり安全、国産だからといって安心とはいえない――。食肉処理場や総菜工場の現場で長年品質管理に携わってきたベテランが、業界では当たり前だが、消費者は知らない“食”のカラクリを解き明かす。(アスキー新書、724円)
(2008年6月2日 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/book/paperback/20080602bk0f.htm
*0601 加害者は変われるか?―DVと虐待をみつめながら [著]信田さよ子 [朝日]
[掲載]2008年06月01日
[評者]耳塚寛明(お茶の水女子大学教授・教育社会学)
DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待にかかわる援助者は、最近すっかり被害者支援、ケアへと力点を移した。被害者に集中し、加害者を敵視するだけの現場の視線の中で、著者はそれでよいのかと考える。臨床事例と事例から作られた架空の挿話が、加害者とは誰か、彼らは変われるか、被害者はなにを望んでいるのかを問う。
加害者の多くは、虐待とDVの被害経験者、目撃者である。大人になった彼らにとって、妻は自分の思い通りになりどんな自分も受け入れてくれる「母」(であるべき)なのだ。加害者を敵視するだけの問題構成は、そうした理解を妨げ適切な対処方策から目をそらせてしまう。彼らは特殊ではなくどこにでもいる。
著者には、虐待やDVの根を個人の心理に求めるのではなく、夫と妻、親と子の間の非対称的な権力関係の中に位置づける社会学的発想が見える。心理学界ではやや異端かもしれないが、私には常套(じょうとう)手段にとらわれずに真の被害者支援を追求する、勇敢な実践家に思えた。
出版社:文藝春秋
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200806030088.html
*経済再生の条件―失敗から何を学ぶか [著]塩谷隆英 [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]高橋伸彰(立命館大学教授・日本経済論)
■元次官が痛感する政策「戦略」の重要性
01年1月の省庁再編に伴い、かつての経済白書は「経済財政白書」と名前が変わった。名前だけではなく、時の政権に媚(こ)びない中立的なかつての白書の分析も、当時の竹中平蔵大臣の言葉によれば「経済財政諮問会議の審議のサポート」に変容した。
変わり果てた白書を見て66年に経済企画庁に入庁し、事務次官を経て99年に退官した著者は「昔の白書を懐かしく思う」という。しかし、ノスタルジーから覚めた著者は心機一転、バブル発生以降の失敗の教訓を「公共政策に携わった者の責務」として「後進に伝え」ようと試みる。失敗の本質は「戦略性の欠如」にあった。高度成長に継ぐ目標を定められないまま、整合性を欠いた政策運営が続けられたのだ。実際、プラザ合意後の円高不況や貿易摩擦への対応を優先し、資産価格の高騰を放置した失敗がバブルを招き、その退治に固執した過度な引き締め策が、銀行のバランスシートに与える影響を看過した失敗の顛末(てんまつ)が90年代の「大停滞」だった。
30年以上に及ぶ政策現場での経験から著者が学んだのは、不況に陥れば長期の目標を棚上げしても景気対策に集中し、好況に転じれば目先の利益よりも長期の目標を追求するという、政策「戦略」の重要性である。その判断を間違えば、97年後半以降の不況の際に財政支出を惜しみ、虎の子の財政構造改革法の効力を成立後1年余りで失った旧大蔵省の轍(てつ)を踏む恐れがある。同様に、一見「勇ましい」小泉改革の行方も、格差を放置すれば必ずしも安泰ではない。「見えざる神の手」に日本の未来をゆだねる改革に批判的な著者は、「改革なくして成長なし」の帰結が「効率一辺倒・弱肉強食の格差社会」に見えるという。
本書には多くの政治家や官僚が実名で登場し、景気判断や政策調整をめぐる議論や交渉の様子が臨場感溢(あふ)れる形で再現される。そこで著者が示すのは、どんなに優れた人間でも間違うということだ。過去の失敗を責めても歴史は変わらない。しかし、失敗から学ばなければ同じ失敗が繰り返されるのである。
◇
しおや・たかふさ 41年生まれ。経済企画事務次官、NIRA理事長など歴任。
経済再生の条件―失敗から何を学ぶか
著者:塩谷 隆英
出版社:岩波書店 価格:¥ 2,100
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210264.html
*0729 「トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ」 小林傳司著 NTT出版
著者が強調するのは、社会が科学技術をどのように受け入れるか、そのデザインを専門家まかせにしておける時代は終わったということである。([朝日]書評(2007/07/29 by山下範久
*民営化で誰が得をするのか [著]石井陽一/市場原理とアメリカ医療 [著]石川義弘 [朝日]
[掲載]2007年08月19日
[評者]小林良彰(慶應大学教授・政治学)
■理念なき「改革」はどこに向かうのか
先の参院選で自民党が大敗した。小泉改革で進められた新自由主義改革が現実のものとなった結果、地域間格差や個人間格差に伴う不公平感が生じたことが、大敗の一因としてあげられる。そもそも、小泉元首相を支持していた者は多かったが、改革の中身をどこまで理解して支持していたのだろうか。
『民営化で誰が得をするのか』は、期せずしてタイムリーな出版となった。著者は、海外移住事業団での駐在経験も持つ神奈川大名誉教授。海外情勢に詳しい目で、日本の旧三公社(国鉄・電電・専売)や、道路公団・郵政の民営化を、米国や欧州・ラテンアメリカ・アジア各国と比較し検証した。
まず世界の民営化を、動機に基づいて五つのタイプに分け、日本における民営化の多くが「政治的配慮」によって行われ、「民営化そのものは目的ではなく、労働問題、政治問題であった」と批判する。旧三公社のうち、国労・動労や全電通という強力な労働組合があった国鉄と電電公社の解体は、総評の崩壊と社会党の没落を招く。一方、専売公社の労組は穏健であったため、日本たばこ産業(JT)は分割されずに済んだと指摘する。
小泉改革における道路と郵政の民営化については、なぜ民営化なのか理念がはっきりとせぬままに構造改革という美辞麗句にくるまれ、あたかも逆らえない世界の潮流かのような思いこみの中、既成事実として民営化が進行しつつあると手厳しい。
経済面の効果も疑問視する。民営化収入で国の債務を償却したり増税を免れたりした国もあるなか、日本の場合は巨額な政府債務の前に焼け石に水でしかなかった。また、郵便料金は変わらず、JRも私鉄と比べて運賃が特段、安いわけではない。こちらも競争原理導入で効果が上がっているとは言い難い。
民営化では、医療も聖域ではない。例えば、大学の独立法人化や国立病院の民間移転など、わが国でも米国流の市場原理が徐々に導入され始めている。『市場原理とアメリカ医療』は、ハーバード大助教授などを経て横浜市立大教授である著者が、日米の大学で医療に携わってきた経験を背景に、米国の医療制度の現状と問題点を詳細に紹介した。
国民健康保険制度がある日本と異なり、米国では自動車など他の保険と同様に医療保険が民営化されており、高額保険の加入者は高水準の医療を受けられる。医師も技術に見合った報酬を受け取ることができ、医療水準が他国に比べて高い。しかしその半面、安い保険の加入者は低水準の医療に甘んじ、国民の2割を占める無保険者は症状がひどくなってから救急救命センターに駆け込むか州立病院の慈善クリニックなどへ行くしかない。
結局、市場原理から得るものもあるが、隣の芝生が緑に見えるが如(ごと)く、何でも民営化しさえすればいいというものではないというのが、両書の著者達(たち)の主張である。財政再建のためなのか、それとも所得再分配のためなのかという民営化の理念を明確にした上で、日本の実情に合わせた公平な実施策を考える段階に来ているのではないか。
◇
いしい・よういち 30年生まれ/いしかわ・よしひろ 59年生まれ。
民営化で誰が得をするのか―国際比較で考える
著者:石井 陽一
出版社:平凡社 価格:¥ 735
市場原理とアメリカ医療―日本の医療改革の未来形
著者:石川 義弘
出版社:医学通信社 価格:¥ 2,520
URL:http://book.asahi.com/review/TKY200708210170.html
*[[◎市民の政策局の本棚06]] より続く
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: